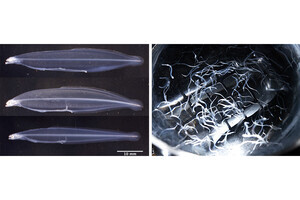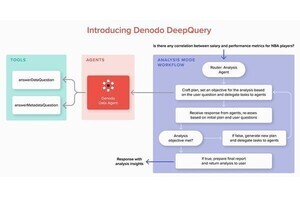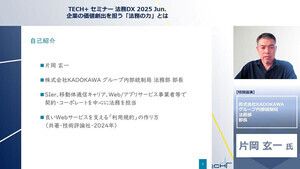ドイツが2011年に「インダストリー4.0」を発表してから12年が経過し、欧州ではデータ共有圏の取り組みが進められている。こうした動きについて、東芝 デジタルイノベーションテクノロジーセンター チーフエバンジェリストでアルファコンパス 代表の福本勲氏は、「日本企業にとって、遠い無関係な国の出来事ではない」と言う。
11月6日~17日に開催された「TECH+ EXPO 2023 Autumn for データ活用 データで拓く未来図」に同氏が登壇。データ連携のためのヨーロッパの動きを中心に、東芝グループの事例を交えながら日本企業がどのように考えるべきかを解説した。
「TECH+ EXPO 2023 Autumn for データ活用 データで拓く未来図」その他の講演レポートはこちら
EUで加速するデータ共有圏の取り組み
講演冒頭で福本氏は、欧州におけるインダストリー4.0に関する昨今の動きを紹介した。ドイツは2019年にインダストリー4.0の新たなビジョンであり、オートノミー、サステナビリティやインターオペラビリティをキーコンセプトとした「Vision2030」を、そして2021年にはスマート製造のユースケースシナリオを定義した「Sustainable Production」レポートを発表。その一方でEUの欧州委員会は、2021年にヒューマンセントリックとサステナビリティ、レジリエンスをキーコンセプトとする「インダストリー5.0」を発表した。ただし4.0と5.0は本質的には大きく異なるものではなく、「今はまだ第4次産業革命の中にある」と同氏は言う。
こうした中、EUではデータ共有圏の取り組みが加速している。データ主権に関する標準を策定するInternational Data Spaces Association(IDSA)のほか、欧州統合データ基盤プロジェクトであるGAIA-X、自動車業界に最適化されたデータ連携基盤の開発環境やプラットフォームなどの提供を行うCatena-Xなど、さまざまな団体が設立され、連携が進む。そのつながる仕組みを実現するために今後グローバルスタンダードになると想定されるのが「アセット管理シェル(Asset Administration Shell、以下AAS)」だ。
「今後は、AASをベースとしたデジタルツインがインターオペラビリティを支えることになります」(福本氏)
多様な機器や人の連携を可能にするAAS
AASは、多様なプレイヤーが業界を超えて連携できる仕組みとしてインダストリー4.0で当初から掲げられていたものだ。異なるメーカーの機器やシステム、人といった現実世界のアセットの情報をサイバー空間で連携するためのインターフェイスとなるもので、現在欧州で進められているデジタルプロダクトパスポート(DPP)の法制化も、AASを前提としている。したがって、日本企業が欧州のサプライチェーンに参画するにはAASへの対応が必須となる。
東芝グループでも、AASへの対応を進めている。同社ではスマートファクトリーやその発展形であるスマートマニュファクチャリングを推進しており、グループ内で培った仕組みを反映した「Meisterシリーズ」というソリューションを社内外に展開している。モノづくりだけでなく、設備機器のメンテナンスや工場内のユーティリティ、アセット管理といったソリューションも提供しているが、ここにAAS対応機能を搭載しており、さまざまな機器や設備を相互接続できるようにしている。
「業界を超えた柔軟なエコシステムの実現を目指しています」(福本氏)
サイロ化されたデータの統合
多くの日本企業では、事業部門ごとにデータが取得され、サイロ化されていることが多いが、データ活用のためにはこうしたデータの統合が不可欠となる。サイロ化されたままではデータ連携基盤のエコシステムに参画し連携をしたとしても、外部データの読み合わせや変換に苦労することになるためだ。一方EUでは外部データを自動的にシステムに取り込むことを目指している。各々のデータが自社の各部門にとってどんな意味があるのかを理解しながら自動処理できるようにすれば、多様なデータを企業間で統合活用できるためだ。
東芝グループでもデータの統合にも取り組んでいる。データ収集活用基盤である「Meister DigitalTwin」を前述のMeisterシリーズの中核に置くことで、部門やシステムの壁を越えてデータを統合できる仕組みを実現した。IoTのデータのほか、ERPやPLM(プロダクトライフサイクル管理)などの業務データもデジタル空間で関連付けて格納し、時系列に蓄積している。さらに、こういったデータモデルを活用するためには、現場の状況の変化を追い、分析して詳細を調べるというプロセスが必要になる。
「そのために、デジタルテクノロジーの活用が重要になるのです」(福本氏)