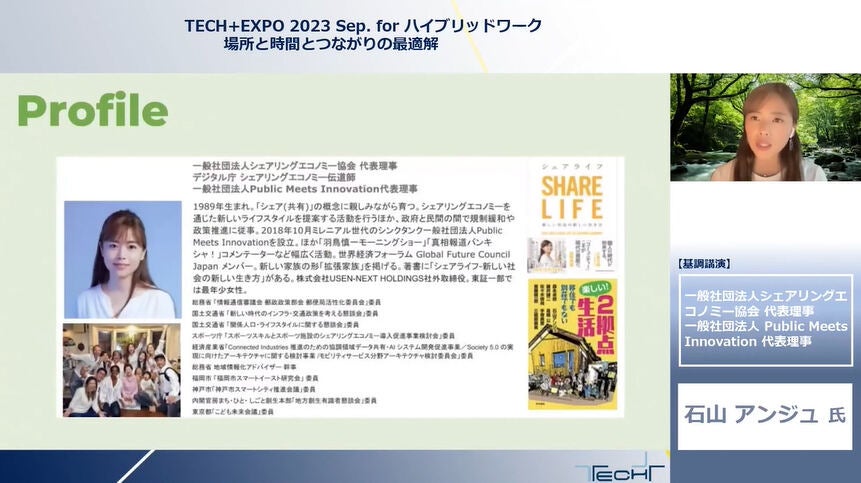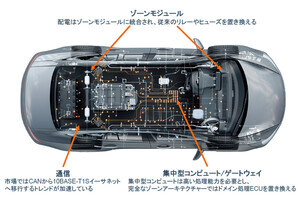「複数の会社や人と仕事をする、全国に複数の家があるといった、仕事や暮らしを分散する思考が、これからの豊かさのスタンダードになる」と言うのは、シェアリングエコノミー協会 代表理事で、Public Meets Innovation 代表理事の石山アンジュ氏だ。シェアリングエコノミーによる新しいライフスタイルを提案する活動を行う同氏は、自らもシェアハウスを運営し、都市と地方の二拠点生活を送っている。
9月5日から8日に開催された「TECH+ EXPO 2023 Sep. for HYBRID WORK 場所と時間とつながりの最適解」に石山氏が登壇。「分散する思考」によって働き方や暮らし、そして社会がこれからどのように変わっていくのかを解説した。
「TECH+ EXPO 2023 Sep. for HYBRID WORK 場所と時間とつながりの最適解」その他の講演レポートはこちら
石山氏が実践する東京・大分の二拠点生活
石山氏は講演冒頭で、実際に自身が行っている東京と大分の二拠点生活を紹介した。大分県豊後大野市では、14世帯で共同所有する入会地に築90年の空き家を月額2万円で借り、Wi-Fiを整備して屋外の気に入った場所でテレワークを行っている。地域でシェアした農機具を使って農業も手掛けているという。
一方、東京では、血縁にとらわれず、“相手を家族だと思ってみる”という意識で一緒に暮らす「拡張家族」がコンセプトのシェアハウスコミュニティを運営している。コミュニティに参加する110人が、このシェアハウス以外のさまざまな地域に分散していて、旅行の際には参加者の家に泊まるといった交流しているそうだ。
「コミュニティの中でも多拠点生活をしているようなものです」(石山氏)
石山氏は海外でもシェアリングエコノミーのサービスを利用した経験を持つ。その1つがコリビングサービスだ。シェアハウスに共有の仕事用スペースも併せ持ったもので、「簡易型の多拠点プラットフォームのようなもの」だと言う。世界中でこういった働き方の変化が生まれていて、暮らすように旅をし、新しい働き方をする、いわゆる「デジタルノマド」と呼ばれるワーカーがこういった場所で交流をしているそうだ。
働き方も暮らしも大きく変わっていく
石山氏は「働き方はさらに大きく変化していく」と強調する。従来は1つの企業に勤め、同じ場所で働きながらスキルを向上させることが市場価値になるという考え方だった。しかし今は、副業やリモートワークも特別なことではないし、シェアリングエコノミーで時間や場所などあらゆるものを提供して収入を得られる。今後はモノや時間、スキル、仕事を複数の会社や個人とやり取りすることになるだろう。報酬は労働の対価ではなく、例えば空いている部屋や使っていない自動車を貸し出したり、料理やペットの世話といった趣味やスキルを提供したりすることが収入になるという。
さらに、暮らしも変わっていく。これまでは、学校や会社に通える場所に1つの家を買う、または借りて、1人または家族や友人・知人と住んでいた。しかしこれからは誰でも複数の家を持てるし、シェアハウスをはじめとする暮らしのシェアリングサービスによって、地域に住む人も固定ではなくなる。つまり、暮らしという空間と人とのつながりも変化していくのだ。
こうした変化は、価値観が変わったことで起きていると石山氏は言う。従来は社会が成長することが前提で、資源を大量に使って大量生産、大量消費しながら経済を成長させてきた。豊かさのステータスは、稼いでモノを所有し、大企業やブランドなど大きなものに帰属することだった。しかし、これからは災害や経済破綻などのリスクと共存していくのが社会の前提になる。依存していた大きなものがなくなってしまう不安を抱えるより、仕事でも家でも人間関係でも、小さな選択肢を複数持っていることの方が安心につながってくる。価値観も、モノは所有するより共有し分かち合うことがむしろ豊かだという方向に変わりつつあるのだ。
「これが分散する思考そのものです」(石山氏)
多拠点生活を後押しする取り組み
複数の家を持ったり、複数の拠点で働いたりする多拠点生活が広まると、その地域に定住せず、観光をするわけでもないが、地域と関わる人々、定期的に訪れる人々が増加する。このような人々は「関係人口」と呼ばれていて、政府も関係人口を増やす取り組みを進めているという。人口が減少しつつある中、多くの自治体は移住を呼び込む政策をとってきたが、それでは国内の総人口を奪い合うだけにしかならない。複数の地域を行き来すれば、どの地域も経済が潤うというわけだ。
「人口をシェアするという考え方です」(石山氏)
こうした動きは世界でも広がりつつある。タイやマレーシア、ポルトガル、ドイツ、フランスなど多くの国で、長期間滞在しながらリモートワークが可能な「デジタルノマドビザ」を発行し、デジタルノマドを積極的に受け入れている。「これは日本政府も検討している」と石山氏は補足した。
国内では「デュアルスクール」という、新しい学校のかたちを取り入れる自治体も増えている。これは、保護者の短期居住に合わせて子どもが地方と都市の2つの学校を行き来し、双方で教育を受けられるというものだ。通常は2つの学校に籍を置くことはできないが、区域外就学制度を活用することで、保護者と一緒に多拠点生活ができるようになっている。