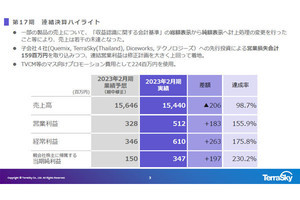テラスカイは10月4日、オンラインとオフラインで年次カンファレンス「TerraSkyDay 2023」を開催した。同社 代表取締役 CEO 社長執行役員の佐藤秀哉氏による「新時代の潮流」をテーマにしたキーノートの内容を紹介する。
テラスカイが示す“新時代の潮流”とは
冒頭、佐藤氏は同社におけるこれまでの変遷を振り返りつつ、新時代の潮流として「DX Ready」「CoE(Center of Excellence)」「デジタルプラットフォーム」の3点を挙げている。DX ReadyとCoEについては、従来から同社が注力していた領域ではあり、これに自社のデジタルプラットフォームが加わった格好だ。
同氏は「DXは潮流というよりは多くの企業が取り組んでいます。当社では2017年から提言しており、当時は第3のプラットフォームということでクラウドなどを活用し、新しいビジネスを創出するというものです。ただ、DXに取り組むのはお客さま自身であり、当社が支援するというよりは、お客さまが考えて取り組むべきだというスタンスです」と述べた。
テラスカイでは、DX Ready=DXに備えるために準備すべきITの要素として「SOE(System of Engagement)/SOR(System of Record)」「Lift & Shift」「マイクロサービス」の必要性を説いている。佐藤氏は「すべて準備したうえで、DXに取り組むべきであり、こうした取り組みを支援している」と話す。
CoEに関しては2019年から本格的に進めており、同氏は「これまでは、お客さまがシステムなどで実現したいことをまとめ、外部のSIerに提案書を作らせて、それを採択してSIerに丸投げしていることが主流でした。この場合だと、仕様書作成やコンペなどを行うためスピードが出ないほか、齟齬も生まれます。そのため、自社サービスなどのSoEの部分については内製化が必要です」と指摘する。
こうした体制を整備するにあたり、人材採用や育成、CoEのグループも形成する必要があることから、同社では体制の整備からトレーニングまでを含めて支援している。佐藤氏は「ガイドライン作成やアーキテクチャの決定、ナレッジベースを構築して、システムの計画策定を一から支援しています」と強調した。
グループ会社のテラスカイテクノロジーズがサービスリリース後の現場の人材を支え、知見・ノウハウの蓄積といったSalesforceプラットフォーム上で稼働するリリース管理システムとして「Flosum」を提供し、顧客を支援している。
自社プロダクトを含めたテラスカイの「デジタルプラットフォーム」
そして、デジタルプラットフォームについては、自社のプロダクトに加え、グループ会社であるBeeXとQuemixの取り組みが紹介された。
佐藤氏は「クラウドは当たり前のように使われていますが、基本的にはパッケージを作っていた人たちがネイティブでSaaS(Software as a Service)として基幹システムなどをクラウドに上げはじめています。ただ単に、パブリッククラウドなどにパッケージを乗せるのではなく、ネイティブに動いています。こうした流れが次の段階として来ています」と説く。
一方、日本におけるバックオフィスの仕組みについて同氏は「従来のパッケージ型ERP(Enterprise Resource Planning)は、パッケージを購入して自前でハードウェアを調達するか、パブリッククラウド上で運用する形です。しかし、現在はオールインワンでクラウドネイティブのソリューションが求められています。この領域はさまざまな企業がサービスを提供していますが、実は中堅~準大手企業のエリアにバックオフィスのSaaSが少ない状況のため、このマーケットにmitoco ERPで参入します」と力を込めた。
同サービスに関しては、テラスカイ 取締役 専務執行役員 製品事業ユニット長の山田誠氏が説明に立った。
既報の通り、mitoco ERPは9月29日から提供を開始しており、Salesforceをプラットフォームとしたサービスでマスター・データを一元化し、グループウェア、経費・勤怠管理のほか、会計から人事給与、販売・購買・在庫管理までの業務システムを含めた幅広い機能が利用できるというもの。
山田氏は「企業・組織内ではさまざまなSaaSが乱立しており、マスターデータの一元管理ができないほか、操作方法がバラバラのためつぎはぎの仕組みとなってしまいます。しかし、mitoco ERPはSalesforceプラットフォームですべて1つのURL、オールインワンで可能としています」と、そのメリットを説明していた。
一方、グループ会社のBeeXでは「SAP S/4HANA Cloud」を中心としたクラウドインテグレーションで支援する。
新規ユーザーには「S/4HANA Public Cloud」をFit to standard(システム導入時にアドオン開発せずに業務内容を標準機能に合わせること)でアジャイル手法を用いて導入を支援。既存SAPユーザーに対しては、「S/4HANA Private Cloud」と「S/4HANA On premise」を訴求していくという。
同様に、グループ会社のQuemixでは量子関連の取り組みを推進していく。すでに同社がオリジナルで開発した量子アルゴリズム「PITE(Probabilistic Imaginary Time Evolution)」は量子優位性の示された有望な材料計算(量子科学計算)アルゴリズムとして、特許を取得し、商標も登録している。
また、量子ビットを活用して環境のセンシングを行う次世代の超高感度センサ装置である「量子センサ」は防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度の「改訂・地下での長距離量子センシングに関する研究」に採択されており、量子科学技術研究開発機構、電力中央研究所と共同で国家プロジェクトとして進めている。
さらに、同社が開発したAWS(Amazon Web Services)上の材料計算プラットフォーム「Quloud」は、誰もが使えるスーパーコンピュータ規模の計算環境を提供。今後は量子コンピュータを活用して、2030年には計算速度を数百倍・数千倍に向上させるとのことだ。