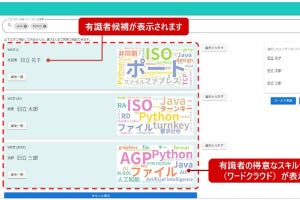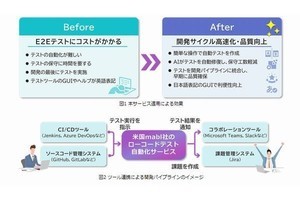日立ソリューションズは8月30日、製造業の脱炭素に向けて、課題抽出から、製品・企業・サプライチェーンにおけるCO2排出量の把握や予測、ESGにおけるサプライヤーの評価まで、トータルに支援する「サプライチェーン脱炭素支援ソリューション」を提供開始すると発表した。同ソリューションは、同社が注力している「企業のSX経営支援の取り組み」の一環。
同日に開催された発表会には、経営戦略統括本部 経営企画本部 担当本部長の野田勝義氏と産業イノベーション事業部 サプライチェーン本部 第3部 部長の小沢康弘氏が登壇し、同ソリューションや日立ソリューションズが進めるSX経営を紹介した。
本稿では、その一部始終を紹介する。
-

左から日立ソリューションズ 執行役員 産業イノベーション事業部管掌 大池徹氏、経営戦略統括本部 経営企画本部 担当本部長 野田勝義氏、産業イノベーション事業部 サプライチェーン本部 第3部 部長 小沢康弘氏
サステナビリティはトレードオフからトレードオンの時代へ
最初に登壇した野田氏は、サステナビリティ時代の新たな潮流や日立ソリューションズの事業全体像を紹介した。
環境や社会問題の悪化により気候変動や資源不足が叫ばれる現代において、サステナビリティの取り組みを企業が推進することは非常に重要視されている。そんなサステナビリティだが、「考え方が時代に応じて進化を遂げてきた」と野田氏は語った。
「経済価値、社会価値、環境価値の関係は、時代と共に進化しています。第1世代は、『経済は利益を生み出しその利益を環境や社会に還元する』という考えでサステナビリティが進められていたのに対して、第2世代では、経済価値と環境・社会価値には重なる部分があり、トレードオフ分は企業がコストを掛けて対応すべきという『トレードオフ』の考え方が主流でした。しかし、現在の第3世代では、『トレードオン』の考え方が必要とされています」(野田氏)
トレードオンとは「一見両立しそうもない二律背反を超え、新たな価値を生み出すことで両立させること」を指しており、サステナビリティに対応させてみると、経済活動は「環境・社会と両立していなければならない」という考え方を表している。
そんな進化を続けるサステナビリティに対応するべく、日立では、プラネタリーバウンダリーのそれぞれの限界点を意識し、地球を守り社会を維持すること、そして一人ひとりのウェルビーイングの実現を両立させるため、複雑化した社会課題を解決することを目指して取り組みを行っているという。
2022年には、日立ソリューションズの新しい50年のスタートに合わせて、VUCA(変化し不確実で複雑、さらに両義性があるという現代の特徴を言い表す言葉)の時代に未来に渡る価値の提供と稼ぐ力を維持強化し、「SXプロジェクト」を立ち上げた。
このプロジェクトは、視点を地球社会のサステナビリティに据え、経済価値と社会価値、環境価値の共存のために、多様なステークホルダーの理解と共感を獲得し、協創をベースに事業活動・企業活動を通じて実現していくものとなっている。
製造業の脱炭素を支援する「サプライチェーン脱炭素支援ソリューション」
このようにサステナビリティへの取り組み強化を進める日立ソリューションズだが、この度、「サプライチェーン脱炭素支援ソリューション」を8月31日より提供開始することを発表した。同ソリューションは、製造業の脱炭素に向けて、課題抽出から、製品・企業・サプライチェーンにおけるCO2排出量の把握や予測、ESGにおけるサプライヤの評価まで、先進的で実績ある欧米や日本の5つの製品・サービスでトータルに支援するもの。
その一環として、製品やサプライチェーンのCO2排出量を高精度かつ詳細に自動報告や分析をすることで、大規模な脱炭素化を支援するプラットフォーム「Makersite」を提供するMakersite GmbHと日本初の販売代理店契約を締結したことも発表している。
サプライチェーン脱炭素支援ソリューションは、「企業・組織のCO2排出量収集・可視化」「製品あたりCO2排出量計算・可視化」「サプライヤCO2排出量測定・管理・削減」「長期・短期の将来CO2排出量予測」「企業としての持続的な削減の取組み」といった課題を解決する。
企業は同ソリューションを活用することにより、SCOPE1~3(CO2排出量の分類)を含め、製品や企業、サプライチェーン全体でのLCA(Life Cycle Assessment)、GHG(Greenhouse Gas)プロトコルへの準拠状況の報告、CO2排出量の算出が可能となるという。
「LCAとは、Life Cycle Assessmentの略称で、ある製品・サービスのライフサイクル全体(資源採取―原料生産―製品生産―流通・消費―廃棄・リサイクル)の環境負荷を定量的に評価する手法のことを指しています」(小沢氏)
加えて、企業の業態に合わせてカスタマイズし、複雑な計算に対応できるシステムや、テンプレートで簡単にカーボンフットプリントを算出できるツールなど、予算や目的に応じて選択できるほか、サプライチェーンの調達・生産能力を加味した供給量、売上や利益の目標値と合わせたCO2排出量をシミュレーションも可能。
専門家がグローバルスタンダード基準で、サプライヤをESGの観点から評価するサービスや、課題の抽出から優先順位付けまでをバックキャスティングで行うコンサルティングサービスも兼ね備えている。
最後に小沢氏は以下のように今後の展望を語った。
「今後の計画としては、2023年にサプライチェーン脱炭素支援ソリューションを販売開始し、その後も社会の変化・進化に合わせた継続的なサービスメニューの拡充を行い、2025年には売り上げ7億円を目指します。そして、最終的に2027年度には売上16億円を達成したい考えです」(小沢氏)