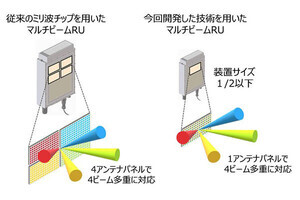富士通は8月28日、「富士通グループ2040年度ネットゼロへの取り組み」というタイトルで同社の環境に関する取り組みの説明会を実施した。
会見には富士通 総務本部 環境統括部 統括部長の濱川雅之氏が登壇し、カーボンニュートラルに向けた日本の動き、富士通のネットゼロ(大気中に排出される温室効果ガスと大気中から除去される温室効果ガスが同量でバランスが取れている状況)に向けた取り組みを紹介した。
本稿ではその一部始終を紹介する。
2030年度に事業活動における使用電力を100%再生可能エネルギーへ
濱川氏は、最初に2020年以降の日本のカーボンニュートラルの動向を紹介した。
「2020年10月には、当時の総理大臣であった菅元総理が『2050年カーボンニュートラル』を宣言しました。そして、2021年4月には、米国主催気候サミットで『2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減、さらに50%の高みに向け挑戦する』という決意表明を行いました。そして、2023年5月には、G7サミットでの岸田総理挨拶では、ネットゼロ 、エネルギー安定供給、経済成長を同時に実現するため、GX(グリーントランスフォーメーション)に挑戦することが語られました」(濱川氏)
そして、政府がカーボンニュートラルに向けた取り組みを行うのに合わせて、環境関連の法規制や投資判断など、企業を取り巻く外部環境は大きく変化しており、企業でのカーボンニュートラルに向けた動きも変わってきているという。
その中で、富士通では、パーパス実現のため、財務・非財務両面の経営目標を設定し、サステナビリティ経営を推進している。そして今回、富士通は新たな環境ビジョン「Fujitsu Climate and Energy Vision」を発表した。
「Fujitsu Climate and Energy Vision」は、90億人を超える人々が、エネルギー・水・食糧などの制約を克服し、豊かに暮らす社会を実現するための目標で、顧客や社会のカーボンニュートラル実現に貢献し、バリューチェーン全体で2040年にネットゼロを目指すというもの。
具体的には、最先端テクノロジーによる革新的省エネを進め、再生可能エネルギーや炭素クレジットの戦略的活用を行うことで、カーボンニュートラルに向けた動きを加速させていく。
また、社会の中でエコシステムをつなぎ社会システム全体としてのエネルギーの最適利用を実現することや、レジリエントな社会インフラの構築、農作物の安定供給や食品ロス削減を実現することなどを掲げている。
「バリューチェーンでのネットゼロを実現するために、温室効果ガス排出削減に向けた国際基準(GHG プロトコル)に従い、スコープ1(事業者自らの燃料使用や工業プロセスによる直接排出)、スコープ2 (他社から供給された電気や熱、蒸気などの使用による間接排出)、スコープ3(スコープ 1・2以外のバリューチェーン全体の間接排出)の全てでネットゼロを目指していきます」(濱川氏)
加えて、温室効果ガス排出削減の目標達成に欠かせない再生可能エネルギーの利用も、2050年度から20年前倒しし、2030年度に事業活動における使用電力を100%再生可能エネルギーとすることを目指していくという。
富士通の環境負荷低減に向けた取り組み
続いて、濱川氏は自社・サプライチェーンにおける環境負荷低減の取り組み事例を紹介した。
スコープ1の燃料電池システムの導入の例として、富士通フロンテックの熊谷サービスソリューションセンターが挙げられた。
同センターでは、環境配慮型発電システムである固体酸化物形燃料電池(天然ガスから発電)を導入し、2020年1月より運用を開始したことで、消費電力量の約50%を燃料電池でまかなえ、CO 2排出量を年間約35%削減できたという。
「今後、熊谷サービスソリューションセンターでは、天然ガスを水素に替えるなど、他の拠点を含めて設備を電化し再エネ利用したり、カーボンリサイクル燃料の活用を促進したりと、グリーンエネルギーへの転換を推進していきます」(濱川氏)
また、スコープ2における再エネ導入拡大については、2021年4月に再エネ切替を完了したと川崎工場(本店)と2022 年 4 月に再エネ電力購入契約を締結した富士通オーストラリアが紹介された。
また、スコープ3でのサプライチェーン上流における推進では、主な取り組みとして「調達額上位の主要取引先のGHG排出削減活動状況の把握」、「CO 2 排出削減の手順やサプライチェーン展開の重要性などを説明」を進めることを明らかにしている。
今後は、SBT WB2℃(産業革命前からの気温上昇を2℃未満に抑制することを規定するとともに、1.5℃までへの抑制に向けた努力の継続に言及するもの)の削減目標での活動を推進し、取引先の目標設定上の課題、取り組みの実態把握と、同社からのサポートなどを提供していく構え。