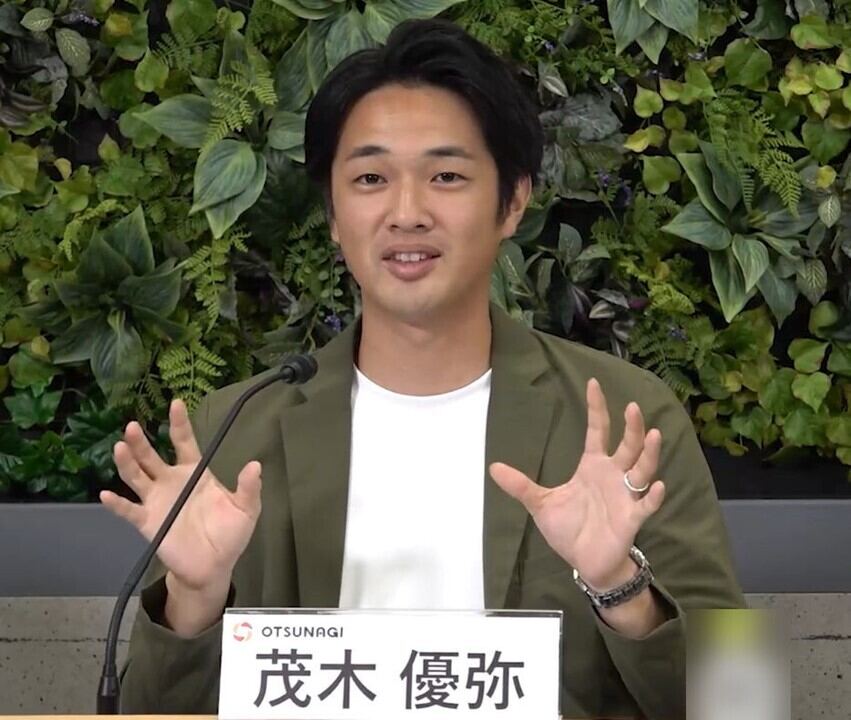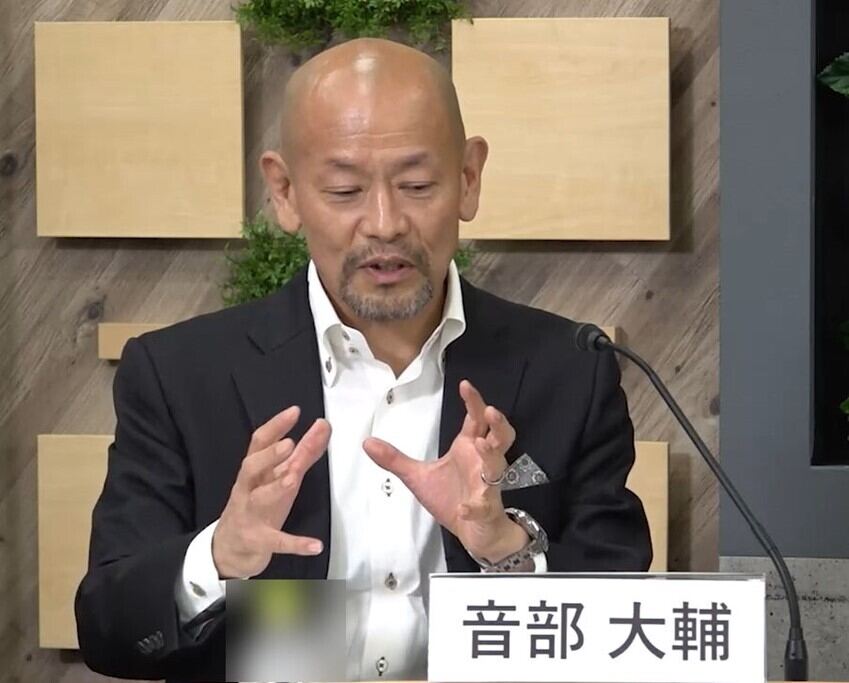8月21日と22日の2日間、マーケティングのサービス・ソリューションの導入を検討するにあたり、利用者に向けて成功イメージと解決策を提供する「TECH+セミナー 専門家とベンダーの対話 トップマーケターが語り合うBtoBマーケティング最前線」が開催された。
1日目の8月21日には、パネルディスカッション「オンライン×対面の時代に! 顧客接点の新定石を考える」が行われ、マーケティング領域で多くの知見と成功体験を持つ4人の専門家が、アフターコロナにおける顧客接点の変化や、マーケティングを進める上で活用すべきソリューションなどについて語った。
パネリストとして参加したのはクー・マーケティング・カンパニー 代表取締役 音部大輔氏、OTSUNAGI 代表取締役 茂木優弥氏、amptalk 代表取締役社長 猪瀬竜馬氏の3人で、ジャパン・クラウド・コンサルティング 代表取締役社長 福田康隆氏がモデレーターを務めた。
顧客接点はリモート/リアルのどちらを優先すべきなのか?
福田氏:コロナ禍で日本企業の多くもリモートでの勤務となり、ZoomやTeamsといった会議ツールを使っての営業活動が増えたと思います。しかし、最近はオフラインでの打ち合わせやセミナーにトレンドが回帰する流れもありますが、現在のトレンドをどう見ていますか?
-

ジャパン・クラウド・コンサルティング 代表取締役社長 福田康隆氏
猪瀬氏:大企業とスタートアップ、テック企業というところでも大きく違うと思っていますが、間違いなくオフラインへ回帰していますね。スタートアップやテック企業では、訪問コストの観点で「オンライン中心」の意識が根付いているでしょう。ただ、受注目前など、大事な話をする瞬間は、オフラインの方が望ましいケースが多いと思います。
一方大企業の場合は、単価の高い商材を売っているケースも多いので、訪問コストが相殺できて、懸念事項にならない場合もあります。特に、訪問先が近い場合は、直接訪問するケースが多いでしょう。
茂木氏:私もオフラインに戻ってきていると感じていますね。私がコンサルティングをしているウェビナーの観点で言うと、スタートアップの場合、顧客に直接話を聞きに行かないとPMF(Product Market Fit)するのは難しいでしょう。そのためオフラインに回帰した上で、ウェビナーは顧客との接点を持つ手段として使うのが良いと考えています。
大企業の場合は、大型契約を交渉する際にはオフラインで会いに行った方が良いでしょう。ウェビナーは購買意欲を高めるコンテンツとして活用すると良いのではないでしょうか。
しかし、いずれにせよ、オフラインのニーズが回帰していても、オンラインのウェビナーがなくなることはないと思います。
音部氏:複雑な情報処理をしないといけないミーティングなど、会場で話した方が状況を把握しやすいこともありますし、今後、オンラインかオフラインかの判断は「情報収集をお互いにどこまでした方が便利なのか」が基準になるでしょう。
ウェビナーを成功させるためのポイント
福田氏:オンラインでの顧客接点の手段として、「ウェビナー」がキーワードとして出てきましたね。ウェビナーを上手く回している会社は、どういうところに注意して行っているのでしょうか?
茂木氏:ポイントが2つあり、1つはシンプルに登壇者のトークが上手いことです。抑揚、間、声の大小に気を使っている登壇者は、すごく良いと思います。
もう1つが録画ウェビナーを上手く活用することです。昨今、タイムパフォーマンスという言葉も多く聞きます。2倍速、1.5倍速で毎日のようにウェビナーを視聴する方もいますから、視聴者が見やすい短尺の録画ウェビナーを活用している企業は、運用が上手くいっていると感じますね。
リモート環境におけるツールの活用
福田氏:リモート環境での業務では、上司が近くにいないので相談できない、部下の様子が見られないのでアドバイスができないという悩みを持っている方も少なくありません。猪瀬さんのところで提供されている商談の自動書き起こしツール「アンプトーク」のように、Web会議を分析してアドバイスしてくれる存在が求められていると思います。実際に、ツールを活用できているお客さまは、どのような利用の仕方をされていますか?
猪瀬氏:個社によって活用法はさまざまです。よくあるケースは、“The Model型”の組織で分業化されている場合、部門間の情報連携を用い、インサイドセールスが架電したデータがフィールドセールス側でも活用できる、というものです。
蓄積したデータをどう活用するかについては、一般的に勘違いされやすいポイントがあります。分析ツールは「AIが課題を示唆してくれて、人間の工数はなく、受注率が悪いAさんが、より優秀なBさんに近づいていく」というイメージを持たれることも少なくありません。しかし、このような機能は、まだ実現が難しいと思っています。分析ツールの導入で工数を100%から10%、20%ぐらいまでは減らせますが、“ラスト1マイル”のところは、人力でフィードバックをしなくてはいけません。
福田氏:こうしたツールはまるで“魔法の杖”のように思われることが多いので、期待値の調整が大事になりますね。
セールス・イネーブルメントの活用
福田氏:「分析できるデータが貯まってくる=マネージャーの負荷がどんどん増大していく」という懸念もありますが、そういったことは、現場で実際に起きていますか?
猪瀬氏:テック企業では、可視化も進んでおり、旧来からデータに基づくフィードバックが行われていたケースが多いです。しかし、大きな企業だと、今まで何もやっていなかったので、可視化によってフィードバックの負荷が増大します。これは、大企業のやる気と課題の大きさによって、打ち手を講じるか否かの判断がされるでしょう。そこで、売上を上げるという目標に到達するための手段である「セールス・イネーブルメント(Sales Enablement)」が注目されています。
音部氏:セールス・イネーブルメントというのは、これがある状態とない状態を比較したときに、具体的にどのような変化が期待できるものですか?
猪瀬氏:弊社が提供するアンプトークもセールス・イネーブルメントの1つです。ある大きなテック系の会社では従来、Zoomでの商談をメンバーに全部レコーディングさせて、マネージャーの方が全部見てフィードバックをSlackで送っていました。そういう企業からすると、アンプトークの導入で商談の解析がAIによって行われるようになり、工数が削減されていると思います。クライアントからも、実際に受注率が改善したというお声をいただきましたね。
分業化された組織体制を全体最適するには?
福田氏:一般的には、ウェビナーはマーケティング部門が検討し、商談になると営業の管轄になると思うのですが、それだと、細分化した部門ごとの課題だけにフォーカスが当たって、経営課題と連動しないこともあると思います。顧客側の体制という点で、ご意見はありますか?
猪瀬氏:「こういう体制の方が良い」という正解は、定義しづらいと思います。相互の情報連携ができていないなどの潜在的な課題に気付いている企業は、多くありません。我々の顧客では、横断的に組織を見ている“営業企画”のようなポジションの方が、見えない課題を顕在化させて解決を目指すケースが多いです。
茂木氏:分業制は確かに大事ですが、分業において起こる弊害は、ウェビナーの内容と、インサイドセールスからのフォローに温度差があり、顧客とのコミュニケーションの齟齬が起きることです。
ウェビナーを成功させるためにどうしたら良いのかと言うと、インサイドセールスが登壇する、もしくはカスタマーサクセスが登壇することだと思います。カスタマーサクセスが登壇すると解像度の高い話ができるので、ウェビナーの満足度が上がりやすくなります。このような考えから、現場の担当者が直接ノウハウを届けられるような組織体制であってほしいなと願っています。
有識者が注目するソリューション
福田氏:ウェビナーや分析ツールなど、1つのソリューションだけでなく、複数のソリューションを組み合わせて使うケースも多いと思います。注目しているカテゴリー、ソリューションはありますか?
猪瀬氏:セールスエンゲージメントツールの今後の動向に注目しています。例えば、OutreachとかSalesloftなどですね。
営業で売れている人、売れていない人の変数は量や質、タイミングなどが影響します。その中でも、アンプトークは“質”の部分を解いていて、会話の質の良し悪しを分析して、直していくサービスです。質に密接に関わっているところが“タイミング”になります。今後、こういったところを示唆してくれるプロダクトが伸びてくると思いますし、日本でも普及してくるでしょう。
茂木氏:ウェビナーの登壇者の質を上げるために、どのような話し方をしていて、どういう言葉を使っているのかという音声解析は大事だと思います。もう1つは、少し月並みかもしれませんが、マーケティングオートメーションです。実際、私はHubSpotを使っていますが、普段の業務を大きく助けてくれていますね。
マーケティングにおけるAI活用 音部氏「大事なのはどの局面で使うか」
福田氏:昨今話題に上がっているAIと、マーケティングの組み合わせは、どう見られていますか?
音部氏:あるとすごく便利だと思います。今やっておかないと、とんでもなく差がついてしまうという議論もありますが、私はそっち側にはまだいないです。
モータリゼーションは、全員が自動車やエンジンの仕組みが分かったから進んだのではなく、そういうことに興味がない人が車の運転をできるようになったことで進んでいきました。AIのエンジニアと自動車のエンジニアが似た概念だとすると、エンジニアではない人たちがAIを使い始めたときに、その影響力や市場規模が大きくなると思います。
そうなった時に必要なものは、運転技術ではなく、「自動車を使うタイミングを正しく選ぶ」判断力です。生成AIの仕組みを知っていて損はありませんが、むしろ「どの局面でAI使うべきなのか」という判断を身に付ける方が有意義でしょう。
茂木氏:どの局面でAIを使うのかという話は、ウェビナーの観点では「全て」だと言いたいです。企画、LPの作成、バナーの作成、登壇、アフターフォロー。このあたりを踏まえて、全てがAIに置き換わり、完全に自動化できると思っていて、そういうプロジェクトを私自身が進めています。AIに代替できるものは全て代替して、あとは生身の人間が喋るということに価値が出てくるので、そういった点も踏まえて、コンテンツを構成していけると上手くいくのではないでしょうか。
福田氏:リモート環境でのセールス、マーケティングは引き続き伸びている市場かなと思います。AIなどの新しいソリューションもたくさん出てきているので、ノウハウをキャッチアップしていく必要がありそうですね。本日は、どうもありがとうございました。