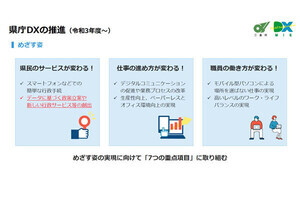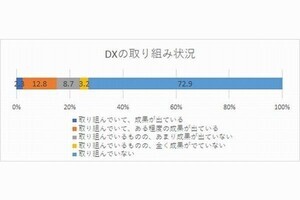小林製薬がDX(デジタルトランスフォーメーション)方針説明会をオンラインとオフラインのハイブリッドにより、8月8日に開催。説明には、同社 代表取締役社長の小林章浩氏と、同 執行役員 CDOユニット ユニット長の石戸亮氏が出席した。
DX実現に向けた社長直下の新設組織
もともと石戸氏は2021年から同社におけるデジタル戦略の社外アドバイザーに就任し、今年からCDOユニット長に就任したという経緯がある。CDOユニットは社長直下の新設組織であり、その中にDX推進グループとシステム部が設けられており、メンバー数は計70人だ。
言わずもがなではあるが、同社の特徴は「アイボン」や「のどぬ~るスプレー」「チクナイン」「命の母」など、印象的な商品名の製品を生産・販売し、環境変化による新たなニーズをいち早くとらえて、文字通り“あったらいいなをカタチ”にしている。
昨今では、小売業における顧客データをもとにした製品開発やヘルスケアデータによる健康促進、ウェアラブルデバイスの普及など、デジタルを伴った変化が加速度的に起きており、こうした状況は同社にとっても大きな機会だという。
自社について、石戸氏は「環境変化をアイデアにするのが得意であり、年間で全社員からの提案は5万7100件に達し、商品数も157ブランド1017SKU(Stock Keeping Unit)と多種多様であるため、さらなる変革を推進する必要がある」と力を込める。
DX推進に向けた3つの戦略
そこで同社では「あったらいいなDX」を進めていくことにした。これは、顧客体験と従業員体験の向上を目指し、すべてのステークホルダーとの接点や体験をDXで改革するというものだ。これを実現するための戦略として同社は「あったらいいな開発のDX」「全社員でDX」「生産性向上」の3つの戦略を掲げ、併せて組織内の風土改革にも取り組む。
小林社長は「当社は医薬品や化学の技術により、お客さまのあったらいいなをカタチにしてきた。従来は医薬品や化学で叶えられなかったことを、デジタルを活用することで創出すれば、顧客体験の向上につながる。そして、お客さまのあったらいいなを当社がカタチにするうえで、業務効率の向上や新しい方法の発見をデジタルで可能にすることが従業員体験の向上となり、当社が取り組みたいDXの姿だと考えている」と説明した。
あったらいいな開発のDX
あったらいいな開発のDXでは、データ・AIを活用した新製品開発プロセスの刷新やデジタルサービスを開発する。データ・AIの活用では、従来は新製品開発の際にアイデア創出のインプットや評価は自分の経験則、身近な物事・人物が主な情報源であり、新規性の高い“お困りごと”を見過ごしがちな側面があったという。
そのため、これまでは国内のみだった社内提案を中国やアメリカなどのグループ会社にも拡大するとともに、世界中のSNS、トレンドといった情報も活用する。
これにより、人力では見過ごしてしまうものをAIの活用でスムーズに発見し、有望なアイデア創出につなげる。データ・AI活用の一例として、国内の全従業員3200人を対象にChatGPTを活用した「kAIbot」の運用を開始している。
また、デジタルサービスに関しては、今年1月にヘルスケア事業部にヘルステック開発Gを設立、同2月に会議体としてヘルステック報告会を開始し、来年1月にはCDOユニットにデジタルに化する新規サービスのディレクションや開発を行う新規サービス開発Gの新設を予定。
IoTデバイスやWebサービス、アプリ、検査、診断、データをはじめ、デジタル新規事業で検討中のアイデアは32件にのぼる。石戸氏は「一気には進められないことから、まず1つの成功事例を生み出していく」と意気込みを語っている。
全社員でDX
全社員でのDXは「Education(人材育成)」「Environment(実践環境の整備)」「Engagement(情報発信、ブランディング)」「Employment(採用、オンボード、評価)」の4つのEを主要アクションとして推進する。
人材育成ではデジタル人材の役割やスキル定義、社員のレベルや目指す役割、スキルに応じた研修プログラムを展開し、全社員、業務で関連する人、チャレンジ意欲のある人の3段階により、オンライン学習プラットフォーム、プログラミング研修、越境学習(他社留学)などのプログラムを用意している。
実践環境の整備は、デジタル人材に向けた情報発信と魅力的で生産性の高い環境づくりを推し進め、積極的な採用を行う。オフィスの増床・改築を進めているほか、6月にLinkedInとnoteの自社アカウント開設、9月にはオウンドサイトの公開を予定。
情報発信、ブランディングについては、実践により創出された成果の社内外への発信 同社の魅力や働く環境の発信に取り組み、デジタル人材が注目するメディアやイベントに積極的に露出していく。
採用、オンボード、評価に関しては、デジタル人材採用の強化に向けてSun Asteriskと協業し、立ち上げ期、育成期、定着期の各フェーズで最適な採用戦略の策定・実行を行うことに加え、現在は新規サービス開発プロダクトマネージャーなど10職種で人材を募集しており、採用強化とともに募集職種を拡大する考えだ。
小林社長は「現状の人事制度ですべて対応できないことが目に見えている。当社が変革しなければならないきっかけだと考えている」と述べていた。
生産性向上
生産性の向上では、従業員体験の向上によりDXを推進していくことから、快適・つながる・安全なIT基盤を提供する。そのために、働き方改革とDWP(デジタルワークプレイス)の充実、全世界でつながる情報基盤、最先端のセキュリティを進めていく。
働き方改革とDWPの充実として、業務進捗の可視化やオンラインツールの活用によりハイブリッドワークの支援、グローバル統合基盤、電子押印、電子帳票などによるペーパレス化と業務効率の向上、クラウドを活用したリアルタイムの情報共有、共同作業を実現する。
全世界でつながる情報基盤の整備に向けては、タイムリーな情報提供ができるデータ活用基盤の構築、CRM/SFAシステムの導入で顧客視点の営業活動の実現、SaaS(Software as a Service)、パッケージの活用による業務標準化を図る。
最先端のセキュリティでは、安全かつ快適に利用できるネットワーク強化やグローバルでのインシデント対応体制、クラウドをベースとした事業継続対策、サービス活用促進のためのクラウドリスク評価を強化していく。
3つの戦略に加えて風土改革にも併せて取り組み、石戸氏は「デジタルの手段だけでなく、すでに社内で実施しているものもあるが、風土も変革していく必要がある。従業員が会社の未来を語る場や外部のIT企業などに社内で講演してもらうことに取り組んでいく」と話す。
DXに取り組むことで、同社では3年以内に「関西でデジタルの仕事をするなら小林製薬」、2030年には「メーカーでデジタルの仕事をするな小林製薬」と言われる状態を目指していくという。