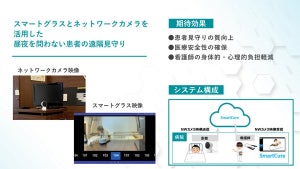ブイキューブは7月24日、メタバースを用いて、製薬業界に特化したデジタル・AIの提供価値・活用ポテンシャルを最先端事例から探るためのイベントである「Pharma Digital Communication Summit」を開催した。
本稿では、「『新』交流時代突入!ポストコロナにおけるヘルスケアイベントのトレンド」というテーマの下、行われたJTBの事例セッションの一部始終を紹介する。同講演には、JTB ビジネスソリューション事業本部 メディカル事業部 営業担当部長の田邊久美氏、同事業部 グループリーダーの小暮一己氏が登壇した。
講演会で求められるのは「他施設の先生とのコミュニケーション」
最初に登壇した田邊久美氏は、「マーケットデータの必要性」について語った。
「新型コロナウイルスが流行する以前の2019年までは、ドクター向けの講演会はほとんどがリアルでの開催でした。しかし、コロナ禍に入り、Web会議、オンラインと対面のハイブリッド、メタバースなど、講演会のスタイルが増えてきました。新型コロナウイルスが5類に移行してから、つまり2023年現在は、このように選択肢がたくさんある状況にありますので、どのような講演会形式が最も有効なのかと悩まれるお客様も増えてきています」(田邊氏)
市場の動向を見てみると、2023年7月以降の開催形態は「ハイブリッドでの開催」が26%、「Webでの開催」が19%と、オンラインを活用した形態が大幅に伸びている状況ではない。
やはり、コロナ禍で大幅に選択肢が広がったとはいえ、「リアル(現地)」での開催が最も多く、55%と過半数を上回る結果となった。
「MRが最も頼りにされている情報は、医師・薬剤師ともに上位に『他施設の薬剤処方情報』という回答が寄せられていることが分かっています。この結果を講演会に当てはめて考えてみると、リアルの講演会においては、他施設の先生方とのコミュニケーションがなくてはならないものなのではないか、との見方ができます」(田邊氏)
この言葉を裏付けるように、リアルやハイブリッドといった講演会の形態にかかわらず、講演会時の「情報交換会」を実施していると回答した人は63%で、他施設とのコミュニケーションに需要があることが分かっている。
医師の6%が体験したメタバース講演会、求められるのは「臨場感」
上記の調査結果には「リアル」「Web」「ハイブリッド」といった選択肢しか反映されていないが、新しい講演会の形である「メタバース」についてはどうだろうか。
「メタバースの採用について『実績あり』という回答は20%となっています。また、2023年2月時点で医師の6%が『メタバースの講演会に参加したことがある』と答えています。参加した医師からは『移動時間が不要で助かった』『積極的に率直な意見が交わせる』といったポジティブな意見も多く挙がった一方で、『肉体的な実感がなく慣れない』『(設定などが)面倒』といった声も寄せられています」(田邊氏)
このように賛否両論が分かれるメタバースでの講演会だが、田邊氏いわく、リアル開催の良さとWeb開催の良さに「医師の働き方改革」という要素を加えると、メタバースでの講演会という形式は良い選択肢となるのだという。
「社外向けビジネスイベントの開催目的として、よく挙げられるのは『通常では得られないコミュニケーションを図りたい(直接会いたい)』というリアルでの開催を希望するものと、『短時間で多くの接点を持ちたい』というWeb開催を希望するものの2つがあります。その2つの良いところを掛け合わせた形式がメタバースでの開催だと私は確信しています」(田邊氏)
5類移行後のイベント形式の最新トレンド
次に登壇した小暮氏は「ディスカッションイベント」と「新しいハイブリッド形式」に分けて、最新のイベントの実施形式のトレンドを紹介した。
「ディスカッションイベントにおいては、コロナ禍前は海外からゲストスピーカーを日本まで呼んで、講演いただくことが主流でした。しかしコロナ禍に入り、オンラインツールが普及するようになってからは、Webを通じて聴講者に講演内容を届けられるようになったため、より手軽かつ容易に実施可能になりました」(小暮氏)
また新しいハイブリッド形式に関しては、「各地域でハイブリッド講演を行う」という形式が増えているのだという。
今までのハイブリッド講演といえば、「集まれる人は集まり、難しい人はオンラインで聴講する」というのが一般的だったが、最近のハイブリッド講演は、第1部と第2部に分かれたシステムになっているのだという。
このスタイルでは、各地域でサテライトオフィスなどのスペースを用意し、第1部は配信場所からその場所に向けてオンラインでの講演を行い、第2部ではその会場ごとにワークやディスカッションといったイベントが行われているのだという。
「昨今では、リアル・Web・新技術それぞれの利点を生かしたイベントが流行しているのです」(小暮氏)