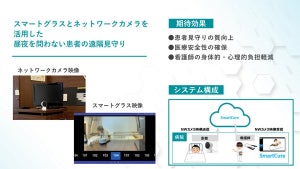ブイキューブは7月24日、メタバースを用いて、製薬業界に特化したデジタル・AIの提供価値・活用ポテンシャルを最先端事例から探るためのイベント「Pharma Digital Communication Summit」を開催した。
本稿では、同イベントに参加した武田薬品工業の基調講演「AIによるMRの情報活動の変化と未来像」の一部始終を紹介する。
同講演には武田薬品工業 JPBUデータ・デジタル&テクノロジー部の常次喜貴氏が登壇した。
デジタルとAIを語る上で耳にする3つの話題
初めに常次氏は、デジタルとAIを語る上で「耳にすることが多い話題」が3つあるとして、以下のように説明した。
「1つ目は『Garbage In,Garbege Out』という言葉です。これは、データ分析の中でよく言われる話で、『ゴミのデータからはゴミしか生まれない』という意味合いで使用されます。特にMR (Medical Representatives:医療情報担当者)の活動においては、自分自身がCRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)へ精緻に入力できていないため、そこから分析されても信用できないという負のサイクルが生まれていることも少なくありません」(常次氏)
常次氏が2つ目に挙げたのは、「デジタルはHowである」という話題だ。この話題は、製薬や医療の業界に限らず、全てのDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む企業で語られるもので、デジタルやAIの導入がゴールになってしまっている企業を諫めるためのキーワードとして使用されることが多いという。
そして、最後に挙げられたのが「AIの台頭」だ。最近、生成AIの勢いはすさまじく、製薬業界においては「MRは不要になるのではないか」という極論もささやかれているのだという。
デジタル時代に製薬業界で起こっている変化
上述したように、デジタルやAIの台頭によって大きな変化が起こっている現代だが、製薬業界では「顧客である医療関係者・医師」と「雇用主である製薬企業」に変化が起きているのだという。
「顧客である医療関係者・医師」に関しては、2024年度に医師の働き方改革が施行されるということを目前に控え、薬剤・疾患関連情報の収集を効率化していく動きが盛んになっているという。例えば、「インターネットサイト」や「インターネット講演会」などを通じての情報収集を進めたいという医師の数が大幅に増加しているとのこと。
また「雇用主である製薬企業」に関しては、薬剤費の抑制や新薬創出コストの増加といった理由から、「創薬のDX」「MRのDX」「RWD(リアルワールドデータ)の活用」「SaMD non-SaMDの展開」「人材・デジタルへの投資」といった動きが加速度的に増加しているのだという。
「MRの立場で考えてみると、こちらも大きな変化が起こっています。1つ目の大きな変化は、『MR数の漸減』です。MRの数は2013年度をピークに毎年減少しているということが分かっています。加えて『雇用形態』や『営業職種』の変化も大きなポイントです。雇用形態は、派遣型・製薬所属・請負型という3つの形が登場し、職種に関してはフィールドセールスやインサイドセールスといった新しい役割が誕生しているなど、大きな変化が起こっています」(常次氏)
「投薬による予後を予測できる」未来へ
さらに、常次氏は以下のように、デジタル化・DX推進が進んだ医療業界の未来を占ってみせた。
「このようにデジタル化・DX推進が進んだ医療業界はどのような未来を迎えるのでしょうか。私は『デジタルを通じて必要な情報にいつでも、どこでもアクセスできる世界』を迎えることになると思います。医療業界で言うならば『目の前の患者さんの必要な情報にすぐアクセスできる』『学術知識に長けたチャットボットに問い合わせができる』『投薬による予後を予測できる』といったことが例として挙げられます」(常次氏)
常次氏はこのような未来を迎えるためには、「データ・デジタルの集積」「高精度なモデル/システムの開発」「医療関係者の需要/行動理解」といったことが必要になると言い、製薬ドメイン知識と最新技術を駆使した人による組織的な取り組みが必要と語った。
「このように語ると、『では、理想の未来では人は必要ないのではないか?』と考える方もいるかもしれませんが、そのようなことはありません。未来にはまだ見ぬ課題がまた出てきますし、そこには新しいテクノロジーも登場するでしょう。なぜなら、それをうまく活用して新たな価値を作っていく必要があるからです」(常次氏)
最後に常次氏は、未来を創るために「変わるもの」と「変わらないもの」について述べた。
「変わらないものは『医療関係者との信頼関係を築くこと』、『必要な情報を必要なタイミングで届けること』、そして『顧客の変化を捉え、先回りして考えること』です。一方で変わるべきものは、『経験と勘に基づいてヒトが活動すること』、そして『人を中心としてデジタルを活用すること』です」(常次氏)