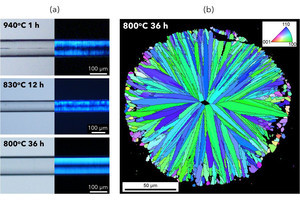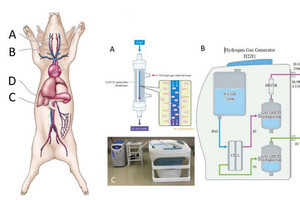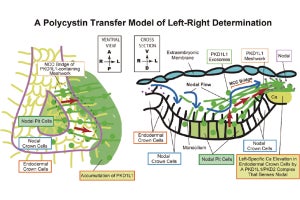米国・デポール大学と埼玉県立自然の博物館など複数の大学および博物館の計7者は7月12日、埼玉県の天然記念物である、約1000万年前の巨大ザメ「メガロドン」(Otodus megalodon)1個体に由来する「楯鱗」(じゅんりん:軟骨魚類特有の原始的なウロコ)化石を検討。部分的内温動物であることを利用して栄養分の消化吸収を促進する遊泳速度の遅いサメだったという新説を発表した。
同成果は、デポール大の島田賢舟教授、埼玉県立自然の博物館の山岡勇太学芸員、三重大 教育学部の栗原行人教授、群馬県立自然史博物館の髙桒祐司地学研究係長(学芸員)を含む国際共同研究チームによるもの。詳細は、地質時代を通じた生命の歴史と古生物学を扱う学術誌「Historical Biology」に掲載された。
メガロドンはネズミザメ目オトーダス科に属し、体長は最低でも15m、比較的水温の低い海域では最大で18~20mに達したと推定されている巨大ザメの古生物(現生の最大のサメであるジンベエザメは10~13mぐらい)である。主に歯や希に脊椎骨の化石が、世界各地の新第三紀の海成層から発見されており、さまざまな海生哺乳類の骨化石に残された噛み跡や歯化石の地球化学的な分析から、当時の海洋生態系の食物連鎖網の上位に位置していたと考えられている。しかしその生物像については、未解明の部分も多く残されているという。
日本では、1986年に埼玉県在住の関根浩史氏によって、現在の同県深谷市(旧・大里郡川本町)菅沼の荒川河床に分布する約1000万年前の後期中新世の土塩(つちしお)層から1個体に由来する73本のメガロドンの歯群化石が発見された(この個体は全長11.7mと推定された)。また、その歯群に伴って石灰化軟骨や楯鱗の化石も産出していたが、これまで詳細な研究が行われてこなかったという。そこで今回の研究では、これらの石灰化軟骨と楯鱗化石を詳しく調べることにしたとする。
具体的には、土塩層産メガロドン歯群化石に伴って産出した小岩塊を分解処理したところ、モザイク状の石灰化軟骨の破片と589個の楯鱗を回収。メガロドンの石灰化軟骨の組織の形態と配列が現生サメ類のものとほぼ一致していたことから、現生サメ類と共通の軟骨成長機構を有していたことが判明したという。
そして楯鱗は形態から3タイプに分類でき、その大きさは最大径で0.3~0.8mmで、この値は現在の外洋性のサメ類(ネズミザメ目やメジロザメ目)の楯鱗と比較できる値だとした。このことから、メガロドンの体サイズの例外的な巨大化は必ずしも楯鱗の巨大化を引き起こさなかったことが明らかにされた。
さらに、楯鱗化石の多くに特徴的な3本の並行する小突起の「小歯状突起」を確認。現生サメ類の皮膚表面は小歯状突起を持つ楯鱗で隙間なく覆われ、突起が連続して体の前後方向に無数の細かい溝を形成することにより、遊泳時の表面摩擦抵抗を軽減していると考えられている。また現生の外洋性のサメ類においては、それぞれの種の楯鱗の小歯状突起間の距離(IKD)と遊泳速度にはある程度の相関があることが知られており、遊泳速度が大きい種ほどIKDの値が小さい傾向があるという。
楯鱗化石のIKDの平均は約100マイクロメートルであり、この値からメガロドンの大まかな遊泳速度は、時速約2.0km(時速0.9~3.0km)と推定された。この値はいくつかの仮定や制約に基づいており、極めて暫定的なものだが、高速遊泳するサメではなかったことを示す重要な証拠とする。
いくつかの先行研究では、メガロドンは高速遊泳(時速4.8~5.1km)するとされていたが、今回の研究結果はそれらとは対照的なものとなった。化石記録から海生哺乳類を餌としていたのは間違いないため、研究チームではメガロドンは普段ゆっくりと泳ぎ獲物を襲う時だけ爆発的な泳ぎをしたと考察しているという。
また、メガロドンは体温保持機構として部分的内温性を持っていたと推定され、これが体サイズの巨大化への重要な要因の1つと考えられてきた。先行研究では、メガロドンが部分的内温性を持っていたことの要因として高速遊泳が考えられてきたが、今回の研究結果はそれらの説も支持しないものとなったとする。
そこで新たな仮説として、メガロドンは部分的内温性によって生み出される代謝熱の大部分を、餌である哺乳類の大きな肉片の消化と、栄養の吸収を促進するために使った可能性があることを提案することにしたという。もし同説が正しければ、部分的内温性の機能的役割の重要性はオトーダス科サメ類の進化の内で時代的に大きく変化したことが示唆されるとした。つまり、白亜紀後期の体長約3mの「クレトラムナ」では部分的内温性を生み出す主要因は高速遊泳だったのに対し、体長15m以上のメガロドンという巨大化の進化過程において、大きな肉片を消化・吸収する方向へと変化したことが考えられるとする。
研究チームは、地球上に存在した最大の肉食動物の1つであるメガロドンの生物像を明らかにすることは、海洋生態系の進化における大型肉食動物の役割を理解する上で重要としている。