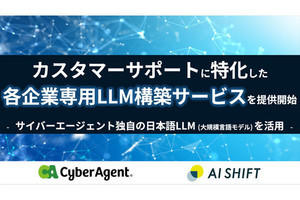米ServiceNowは5月16日~18日(現地時間)にかけて、年次イベント「Knowledge 2023」を米国ラスベガスのThe Venetian Convention & Expo Centerで開催した。
イベント2日目には、ServiceNowの社長兼COO(Chief Operating Officer、最高執行責任者)のCJ Desai氏が「Innovations in the Now Platform」と題した講演で、同社が提供する業務アプリケーション基盤である「Now Platform」の最新情報を紹介した。本稿では同日の発表内容とともに、ゲスト登壇者の発言を紹介する。
Amazon、Marsが語ったNow Platform導入の経緯
Desai氏は冒頭、「当社が最初に提供したプロダクトはITSM(ITサービスマネジメント)サービスだった。現在はオンボーディング(組織への人材定着)、調達業務、SCM(サプライチェーンマネジメント)など、企業のさまざまな業務にアウト・オブ・ザ・ボックスのサービスを提供しており、エンタープライズ全体のインテリジェントプラットフォームを目指している」と同社の立ち位置をあらためて説明した。
同社が提供するNow Platformはアップデートを年2回実施しており、毎回、世界の都市・州名が製品名に付けられている。2023年4月11日には「Utah(ユタ)」がリリースされた。Desai氏は2023年9月に「Vancouver(バンクーバー)」、2024年には「Washington D.C.(ワシントン)」と「Xanadu(ザナドゥ)」を提供するロードマップを示した。
「プラットフォームのアップデートは従来通り、年に2回実施していく。細かな機能群の新規リリ-スは毎月行っているが、AIによってさらに機能リリースのスピードを加速できると考える」(Desai氏)
講演では、同社が注力しているITオートメーション、デジタルエクスペリエンスの製品デモンストレーションとともに、製品導入企業がゲスト登場した。
ITオートメーションのテーマでは、米AmazonのITインフラやIT運用ソリューションなどの管理部門であるOpsTech ITでWorldwide Directorを務めるMike Stone氏が登壇した。同部門では5000人のIT関連人材を抱え、業務オートメーションやサービスデリバリ、工場におけるロボットなどのテクノロジー導入も担っているという。
Stone氏はNow Platformを導入した理由について、「在庫状況を把握するにあたり課題があったほか、個々の問題を解決するためにツールを導入していく中で、ビジネスを効率化するためにITプラットフォームが必要だったからだ。また、ITプロフェッショナルがチームとして稼働できるように人材を管理し、ダイナミックにシームレスな業務体験を届けることも重要だった」と述べた。
デジタルエクスペリエンスのテーマでは、チョコレートのM&M'sなどを提供する米MARS Global Business Services(GBS), President Angela Mangiapane氏が登壇した。
Mangiapane氏が管掌するGBSでは、請求書の支払いなどの経理や人材管理といった同社のバックオフィス業務のデジタル化を推進しているという。
「ポータルが複数あり、更新をたびたび行う必要があるなど、社員のフラストレーションに繋がる業務が多かった。部門の対応能力を高めるためのデジタルケイパビリティを構築し、摩擦の少ない環境を作るためにNow Platformの導入を決めたが、人が中心となる体系を作り出すことが重要と考えた。そのために、私はまず、社員の意見を聞き、現状の問題を定義した」とMangiapane氏は振り返った。
生産性向上させる生成AIのユースケースを創出
講演の後半では、同社が初日の基調講演で注力することを発表した生成AI(ジェネレーティブAI)について、米ServiceNowの戦略が明かされた。
同社は米マイクロソフト、そして米OpenAIと共同して自社のLLM(Large Language Model、大規模言語モデル)のAIを開発し、新たな生成AIソリューションを提供する。
加えて、Desai氏は、「特定の作業や問題解決に特化したドメイン特化型LLMの開発に注力する」と発表した。現在は、Now Platform専用のデータでトレーニングしたLLMを開発しており、IT部門の業務向けの専用AIチャットボットや、カスタマーサービス業務におけるQ&Aフォーム、顧客事例の概要に基づくナレッジ記事の作成などに活用していく予定だという。
「企業が独自のデータを使用してチャットボットをカスタマイズできるように、データ最適化と顧客に帰属するデータのプライバシーを両立させる。企業全体の生産性を向上させる多数の生成AIのユースケース創出を検討している」とDesai氏。
ドメイン特化型LLMの開発に関連して、同日に米ServiceNowはNVIDIAとエンタープライズグレードの生成AI機能の開発に向けたパートナーシップ締結を発表した。
米ServiceNowは、LLM開発向けのクラウドサービス「NVIDIA NeMo」など、NVIDIAが提供する複数サービスを利用してLLMの開発を進める。同時に、生成AIを利用したツールでNVIDIAのIT運用の効率化も支援するという。
講演にはサプライズゲストとして、NVIDIA Co-Founder CEOのJensen Huang氏が登場した。Huang氏によれば、生成AIの登場は「IBMのSystem/360登場以来のコンピューターの再発明」だという。
Huang氏は、「専門分野に応じた生成AIを作ることで、人の知性とスキルを向上させられる。AIが専門のチップをデザインしたり、アーキテクトの役割を担ったりと、人間ができないことをAIが実行することで、人間とのコラボレーションの可能性も広げられるだろう」と生成AIへの期待を語った。