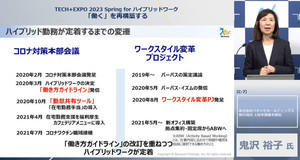社会人になって、同窓会や友人の結婚式など旧友と再会する機会が増え、それと同時に自分の過去を振り返ることも多くなったという読者も多いのではないだろうか。
筆者の中学生や高校生の記憶をたどってみると、勉強系の科目よりも体育や音楽の授業が好きで、授業中も数学の公式なんてそっちのけで部活中に試してみたいフォーメーションを考えているような、決して褒められる学生ではなかったように思う。
そんな筆者でもテストの時に友人から頼られる勉強科目があった。それが後に今の記者という仕事の根源を支えてくれる「国語」だ。
国語においては、同級生にテスト前に勉強を教えるだけでなく、大学生の時には家庭教師として高校生相手に古文や漢文を教えていたこともあったし、ベネッセグループが運営するベネッセ文章表現教室で作文や言葉の表現方法を小学生に教える講師をしていたこともあった。
そんな曲がりなりにも教育に携わったことのある筆者ゆえに、ずっと気になっていたことがあった。
「現代の教材はとんでもないところまで進化しているのではないだろうか……?」
GIGAスクール構想をはじめとした教育現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)について筆者も多くの取材を担当してきたが、教材についてはあまり取り上げてこなかったように思う。
そこで、教育業界のトップランナーであり、筆者が大学生時代にお世話になっていたベネッセコーポレーションの方に「IT技術×教材」の最前線について伺ってきた。
-

左から「進研ゼミ 中一講座」VRコンテンツ開発担当(英語)柏原稜氏、「進研ゼミ 中一講座」商品責任者 石川 悦子、「進研ゼミ 中一講座」VRコンテンツ開発担当(社会)末吉美和子氏、「進研ゼミ 中一講座」VRコンテンツ開発担当(情報編集)松井喬平氏
「360度VIEW」で現実では体験できない世界を疑似体験
今回、筆者が紹介いただいたのは、中学1年生向け進研ゼミが4月から提供を始めた「ハイリコム学習」という名前の教材だ。
昨年の10月に同教材がお披露目された際にも、弊誌内でサービスの概要はお伝えしているが、「ハイリコム学習」とは、抽象的な学習が増える中学生のために開発された教材だ。現実では触れること・体験することのできない学びの対象に、疑似体験や「360度VIEW」を通して「没入する=ハイリコム」経験をすることで、難易度が上がる学習の補助を行うVRゴーグルを活用したコンテンツだ。
3月20日には第1弾となる社会・英語・部活動という3つのコンテンツがリリースされ、進研ゼミ中学講座を受講する中学一年生の手元に届いたという。
「進研ゼミ中一講座では、スマートフォン向け専用アプリ、スマートフォン用VRゴーグル、専用タブレット向けアプリを受講生のみなさんに提供することで、VR教材による『ハイリコム学習』を実現しました。最近では、中学生にあがる時点で自分のスマートフォンをお持ちのお子さんも多く、また、幼い頃から電子機器の扱いに慣れている世代のみなさんなので、このようにスマートフォン向け専用アプリを活用した教材でも問題なく使用いただけると思っております」(石川氏)
またコンテンツの提供方法だけでなく、VRを活用するにあたって心配な「目の健康」についても何度も改善を繰り返して提供に漕ぎつけたという。
「開発にあたって小児科の専門家の方に何度もご相談し、11歳以上のお子様が安全に使えることを配慮したレンズを独自に開発しました。さらに、目の疲労感や気分の悪さなどがおこらないように、コンテンツの時間の長さや目の動きなどを何度も検討し、コンテンツに改良を加えました。このようなさまざまな配慮を重ねたことで、安全にハイリコム学習を体験いただけるようにできたと自負しております」(石川氏)
筆者は仕事柄、何度もVRコンテンツを使用したことがあるが、確かに目が痛くなったり、気分が悪くなったりしたのは1度や2度ではない。そもそも筆者が乗り物に酔いやすい性質であるのも関係しているのだろうが、自ら進んで体験してみたいと思ったことはあまりない。しかし、ベネッセがここまで自信を持って太鼓判を押すならぜひ体験してみたい。
早速、3月にリリースされた社会・英語・部活動のVR教材を体験してみよう。