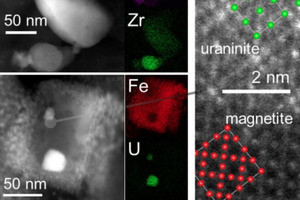今回の研究成果は、福島第一原発から南西方向約2.8kmに位置する、事故後に閉鎖された小学校の建物内部を、2016年に初めて調査した際のものだとする。特に1階、2階の廊下床面に残留している粉塵、そして建物外の集積した粉塵と表層土壌が参照試料として採取され、分析に用いられた。
まず、表層土壌中のCsMPを定量するために開発された手法を、従来よりも75倍高い放射能で汚染された汚染粉塵/土壌にまで適用できるよう、粒径選別がより細分化された。この改良型定量法を小学校粉塵試料に適用したところ、建物1階の床に残留していた粉塵から1m2あたり490個~2480個、2階の床の残留粉塵から73個~200個のCsMPが計測された。
また、CsMPを通常の土壌から分別するしきい値よりも低い、すべてのホットスポットを計数すると、より小サイズのCsMPが存在する可能性も示唆されたという。これらの結果から、玄関のある1階の方が多く粒子が存在することと、建物東側により多くの粒子が存在していることが判明した。
また、粉塵全体の放射能に対するCsMPの放射能の割合(RF値)を計算したところ、1階が6.9%~39%、2階が4.5%~6.6%だったとする。幅広いRF値は、粒子を含む大気の流入とその後の水溶性セシウムを吸着した土壌粉塵の流入が、一定の割合ではなかったことを示唆するとしている。
一方で、屋外では粉塵、表層土壌ともにRF値が一様に1.5%程度であり、原発事故後の一連のセシウム放出過程で、大量の水溶性セシウムが均等に沈着したことが示されている。また、屋外と比較して建物内の粉塵のRF値は非常に高く、建物内部には一連の降雨による水溶性セシウムの沈着がないことから、建物内に流入した原発事故直後の大気中に、高い割合でCsMPが含まれていたことを示唆しているとした。
今回の研究成果から、建物の開閉状態によっては、CsMPが建物内部に流入して粉塵として残ることが明らかにされた。研究チームは今後、今回の研究と同様の手法を用いながら、複数の建物内部にこの粒子がどの程度流入しているのかを検証し、その存在を認識、適切に対処することで、安全性の向上につなげることが期待されるとしている。