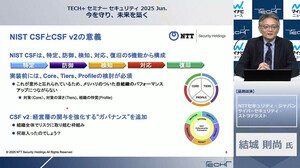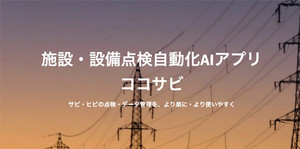建設業界と聞くと、皆さんはどんなイメージを持つだろうか。
本来であれば、国や生活を支える魅力的な産業にもかかわらず、「3K(「きつい」「汚い」「危険」の頭文字をとって作られた略語)」の代名詞的な業界として知られていることもあり、マイナスなイメージを持つ人も少なくないのではないだろうか。
野原ホールディングスが今年2月、全国の大学1~3年生の男女1,000人を対象に行った「建設業界のイメージ」調査では、「建設業界への志望意向」について「受けるつもりはない」が69.1%で最も多い結果となった。このように、「残業・休日出勤が多い」「給料が低い」「デジタル化が進んでいない」といったイメージから、就職活動の際に志望する学生が少ない不人気な業界としてのレッテルを貼られてしまっている側面も否めない。 そんな業界をDX(デジタルトランスフォーメーション)により「働く場所としてもカッコよく、魅力的な、学生の人気業界にしたい」と、建設現場のDXを推進しているのが野原ホールディングスグループCDOの山﨑芳治氏だ。
本誌では前編と後編に分けて、日本の建設業界の現状や今後の建設DXの未来をひも解いていく。後編となる今回は、建設業界はなぜDXに取り組むべきなのか、建設業界の未来はどうなっていくのかについて紹介する。
BIMに挑戦してもらうために必要な「実績作り」
前編で、建設プロジェクトの前段階にある設計工程を最重要視する「フロントローディング」に転じることが、これからの建設業の生産性向上に重要であり、それを実現するツールがBIM(ビム/Building Information Modeling)であると紹介した。BIM活用を愚直に進め、BIM本来の使われ方を実現していくと同時に、業界を変えていくための業界関係者へのアプローチも行っていく必要があるという。
「現場所長は現場の利益を上げることが最優先であるため、BIMに挑戦することへ抵抗を持つ方もまだまだ多い印象です。BIM導入の初期段階では、やはり、BIMソフトの購入などのコストやソフトの操作への慣れなどの手間がかかります。そのため、「BIM活用」という追加の業務を受け入れてもらえるようにしていく、かつ、目に見える形でメリット・成果を出していく必要があります。まずは、実績作り、具体的な成果の発表などを通して現場所長のレベルに納得してもらえるようにすることが重要になってくると見ています」(山﨑氏)
この実績作りのために、野原ホールディングスは東急建設と2022年夏に実証実験の公表を行っており、2022年度も他の複数ゼネコンとBIMを使った実証実験を実施している。(2023年度以降もその数を増やしていく予定)
建設業界を変革することで魅力的な職場に
これらの現状を踏まえて、山﨑氏に野原ホールディングスの考える建設業界の未来について語ってもらった。
「最終的な目標は、全工種を対象にして、フロントローディングを完成させることだと思います。そして、フロントローディングの完成で終わることなく、その先の『建設業界を働く場所として魅力的な場所にする』という最終的な業界全体のゴールにも寄与していきたいと考えています」(山﨑氏)
山﨑氏は、建設業界をデジタルによって変革する、つまり、DXを実現することで、3Kのイメージが払拭された魅力的な職場になると考えているのだという。
遅くまで仕事があることや休暇が取りにくいことなどは、BIMによるフロントローディングで設計図に含まれる情報が増えることで、工事に必要な詳細な情報を全て表しきれない従来の設計図を現場で調整するというな工程を省くことで業務効率化を実現して解消できる。また、工事現場=危険が付きまとうというイメージも、事前にVRなどを活用してシミュレーションを行うことで最大限のリスクを回避できるようになるという。
業界全体を変革する大きな構想だが、なぜ野原ホールディングスがこの取り組みを推進しているのだろうか。
「言葉を選ばずに言えば誰もやらないから、ですね。しかし、事業的な意味合いで考えれば、弊社が取り組むのが一番スムーズだと思います。弊社は専門商社として、昔から各プレイヤーの間にあり、つなぎ合わせる役目を担ってきており、全方面に顔が利きます。1つの会社だけではフロントローディングはできませんし、各工程をつなぐこともできないため、データで工程と各企業をつなげるハブ機能を弊社が担うのは合理的だと思います」(山﨑氏)
最後に、山﨑氏に今後の展望を聞いた。
「今後は、実証実験や情報発信を通して世論を作っていくことを重要視していきたいです。まずは建設業界のことを知ってもらい、そして業界の意識を変えていくこと。そういった活動の先で『建設業界が憧れの職業です』と言ってくれる子どもたちにたくさん会えることを期待しています」(山﨑氏)