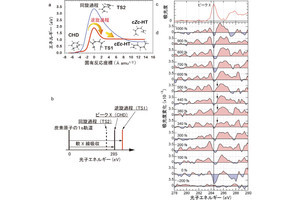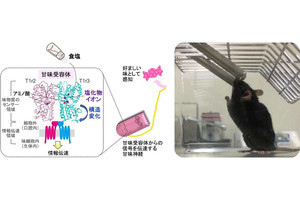東京大学(東大)は3月10日、島嶼(とうしょ)に生息する哺乳類について、そこで極端な体サイズの進化を遂げた種では絶滅率が高くなることを、大規模なデータ解析により明らかにしたと発表した。
同成果は、東大大学院 新領域創成科学研究科の久保麦野講師、国立科学博物館 人類研究部の藤田祐樹研究主幹らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「Science」に掲載された。
地中海諸島においては、大陸の祖先種と比較して体重がわずか1%程度になったゾウや、逆に祖先種の200倍にまで大型化したジャコウネズミなどの化石が出土している。このように島嶼では大型動物が小型化し、逆に小型動物が大型化するという「島のルール」と呼ばれる特有の進化法則が知られている。さらに島嶼においては、こうした体サイズ以外にもさまざまな変化が起こることが知られており、これらの一連の形態学的な変化を総称して「島嶼化」あるいは「島嶼シンドローム」と呼ばれている。
-

島嶼化の典型例である、絶滅したゾウの一種「Palaeoloxodon falconeri」の復元骨格。地中海のシシリー島から化石が見つかっており、肩までの高さは成獣のオス(左)でも1m弱しかない。その祖先種であるヨーロッパ大陸で発見されている化石ゾウ「Palaeoloxodon antiquus」(右奥)と比較すると、体重は1~2%程度しかなかった。写真:久保麦野氏(出所:東大Webサイト)
特に捕食者のいない孤立性の高い島(海洋島)では、対捕食者行動が失われることが要因となり、島嶼の哺乳類に共通して、脳の縮小、走行能力の低下などが起こったとされている。こうした島嶼での特殊な進化により、人為的な影響による絶滅が起こりやすくなると考えられてきた。しかし、体サイズの変化の大きさと絶滅しやすさの関係は明らかになっていなかったという。
そこで研究チームは今回、1400本を超える網羅的な文献調査と標本調査に基づき、島嶼に生息している哺乳類のうち、現生種1231種(1種が複数の島に生息する場合があるため、全部で1539集団)、絶滅種350種の体サイズ、祖先種からの体サイズの変化率、絶滅リスクのデータを収集したとする。
それらのデータをもとに検討を行った結果、体サイズの変化の大きさと絶滅しやすさには正の相関があり、島嶼に生息する哺乳類の中で、極端な体サイズの変化が起こった種ほど絶滅リスクが高いことが判明したという。体サイズの変化は島嶼化程度の指標になるが、島嶼化による形態学的な適応進化が、絶滅の素因を作ってしまったことが示されているとする。また、島に固有な種、中でも海洋島の固有種ほど絶滅しやすかったことも解明された。このことから研究チームは、島嶼の動物の保全を考える上で、その種の島嶼化程度を考慮して優先的に行うことが必要であるといえるとしている。
-

体サイズの変化量と絶滅リスクの関係。(A)現生種。絶滅の恐れがない種(オレンジ)と恐れがある種(赤)で比較。(B)現生種(緑)と絶滅種(青)で、体サイズの変化量が比較されている。現生種では絶滅の恐れがある種で、そして絶滅種で、より体サイズの変化量が大きいことがわかる。動物の右の数字は、祖先集団からの体サイズの変化量の平均値。これが1より大きいと祖先種より大型化し、1より小さいと小型化している(出所:東大Webサイト)
続いて、今回の研究で収集された化石種の記録から、過去2300万年間の絶滅率の時代変化が調べられた。すると、絶滅率は現代人(ホモ・サピエンス)の島への渡来時期と非常に強い関連性が示されたという。島嶼において哺乳類と現代人が共存する時代では、それ以前の現代人がいない時代に比べて絶滅率が16倍にも増加していたとする。一方で、サピエンス以前のヒト(原人や旧人段階のヒト族の種)の場合には絶滅率は約2倍に上昇するにとどまっており、サピエンスとサピエンス以前のヒトでは、島嶼の生態系に及ぼす影響に決定的な違いがあったことも確かめられた。
-

島嶼に生息する哺乳類の絶滅率の時代変化。横軸は年代(単位は百万年)で現在が右端、縦軸は島嶼の哺乳類の絶滅率を示す。前期更新世から中期更新世にかけて絶滅率は微増にとどまるが、後期更新世に現代人が登場し世界に拡散するタイミングで、島嶼での絶滅率が激増する(出所:東大Webサイト)
ダーウィンの研究でも有名だが、島嶼は「進化の実験室」とも呼ばれ、非常に興味深い生物進化の事例を数多く見ることができる場所として知られている。その一例が、今回の研究対象とされた巨大化・小型化した哺乳類だ。ただし、それは体サイズの変化のみではなく、さまざまな形態学的・生理学的・生態学的な特徴の変化を伴っていたことが考えられるという。今回の研究では体サイズのみが着目され、その変化量と絶滅率との関係が解明された。研究チームは今後、島嶼化に伴う体サイズ以外の変化についても分析を進めることで、絶滅に対する脆弱性を高めてしまった生物学的な背景についても明らかにできることが期待されるとした。