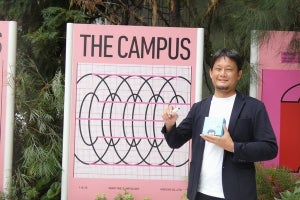SB C&Sは2月8日、「子どもたちの未来を創造するために~自治体で取り組んでいる教育改革~」というテーマの下、オンラインパネルディスカッションを開催した。
同社は、教育機関向けプラットフォームに関する優れた専門知識やサービス、ソリューションを提供する企業として、 Appleより「Apple Authorized Education Specialist(AAES)」の認定を受けている。そんな同社が開催したパネルディスカッションには、さまざまな工夫を凝らし、「子どもたちのために授業をどう変えていくか」という本来的な視点を重視した教育改革を先進的に行っている大分県中津市、京都府舞鶴市の教育委員会のメンバーが参集した。
大分県中津市教育委員会 教育長の粟田英代氏、指導主事の小野次也氏、京都府舞鶴市教育委員会 教育長の奥水孝志氏、指導担当課長の岡本恵理子氏、教育振興部長の濵野滋氏が登壇し、各市における取り組みを披露するとともに、教育方針、端末の利活用などの学校間や教員間の格差について議論を交わした。
本レポートでは、同パネルディスカッションの一部始終を紹介する。
舞鶴市と中津市に見る先進的な教育改革とは
最初のテーマは「教育目標や方針について」だ。
舞鶴市では、小中一貫教育で単元や学習過程を丁寧につなぐ「探究し、学び続ける授業デザイン『舞ラーニング』」という授業方式を推進している。これにより、次世代に活躍が期待されている子どもたちにとって必要な能力である「知識および技術」「思考力、判断力、表現力」「学びに向かう力、人間性」を身につけることを目指しているという。
「舞ラーニングを実施するにあたっては、『見通しを持つ』『自分の考えを持つ』『学び合い深め合う』『学びを確かめ振り返る』『新たな学びにつなげる』という5つのステップが大切になると考えています」(奥水氏)
「見通しを持つ」第1段階では、「なぜこうなるんだろう」という興味関心を持って課題と向き合う。「自分の考えを持つ」第2段階では、「こんな風に考えてみよう」と自分と向き合う。「学び合い深め合う」第3段階では、自分の考えを周りと共有する。そして、「学びを確かめ振り返る」第4段階では、その考えを振り返り新たな自分を向き合っていき、「新たな学びにつなげる」第5段階へと続く。こうした5つの段階によって、舞鶴市は児童・生徒たちが踏むこと支え、主体的な学び手を育てていくことを目標としている。
「この5つのステップを意識することで、単元や1時間の授業の中で主体的かつ対話的な深い学びを実施することができると考えています」(奥水氏)
一方で、中津市は自立する力を育て、社会で活躍できる人材の育成のため、「みんな活躍授業」の実現に向けて授業を行っている。
「みんなが活躍している姿とは、授業の最初から最後まで一人ひとりが知識や技能を活用し、自分であるいは友達と思考したり表現したり判断したりすることで授業の狙いへと迫っている姿だと考えています」(粟田氏)
この「みんな活躍授業」を推進することによって、「学び方を学ぶための土台ができる」「全員が同じ土俵に乗った授業の流れができる」「お互いを認め合う風土ができる」といった3つのメリットが得られているという。
端末の利活用の格差を埋めるために実施していること
続いて、「端末の利活用などの学校間、教員間の格差について」というテーマで議論が行われた。
舞鶴市は、この課題に対して「舞GIGAスクール推進計画 4WD構想」を打ち出している。「舞GIGAスクール推進計画 4WD構想」とは、3つの研修を通じてICT支援員によるサポートと舞GIGAスクールプロジェクト会議による課題整理と答申を行うというものだ。
具体的には、ワクワクする学びに挑戦する教員を育成する「授業づくりリーダー研修」、チーム学校によるiPad活用促進とワクワクする学びへの挑戦のためアドバイザーによる月1回の訪問や授業研究を行う「舞GIGAスクールモデル校」、ワクワクする学びへ向かうための情報モラル教育を行う「情報モラル教育研修会」、各校の校内研修として年4回オンラインでiPad活用の基礎研修を行う「iPad活用基礎研修」が行われている。
こうした取り組みにより、教員が一枚岩となって教育へのICT活用推進を進めて、格差をなくすことに成功しているという。
また中津市では、舞鶴市と同じように全教職員に向けた研修を開催しており、これによって個のスキルアップを図っているという。加えて、各学校から推進委員を集める形でICT活用教育推進委員会を組織化し、ICTを活用した授業づくりや管理・運用についての情報交換や今後の取り組みに関する競技を行っている。
「令和4年度(2022年度)の各学校のゴールとして、児童・生徒がiPadを活用した授業を1日2~3回程度実施すること、教職員のスキルアップ研修を校内で3回以上行うこと、持ち帰り学習を週に1回以上実施することなどを掲げています。現在、これらの実現に向けて取り組みを進めています」(粟田氏)
ディスカッションの最後にこれから取り組みたいことを問われ、各市の教育長である粟田氏と奥水氏は以下のように話して締めくくった。
「ICTの活用によって不登校の生徒たちや支援が必要な生徒たち、また、外国人で日本語がまだ不自由な生徒たちなど多様な子どもたちの学びを広げていきたいです。『すぐに調べられる』『何回でもやり直せる』という特性をもったデジタル教材は、このような子どもたちの未来を明るくしてくれると確信しています」(粟田氏)
「教師になった以上、良い授業をしたいというのは全ての教員の願いであることは間違いありません。しかし、教育は正解がないから難しい。少しでも良い授業を多くの子どもたちに届けるためにわくわくする学びを続け、また、わくわくする街作りを推進していきたいと思っています」(奥水氏)