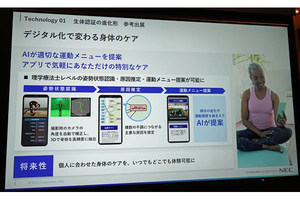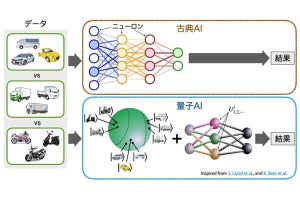富士フイルムの企業CMが好きだ。同社の研究員が登場し、その研究内容を分かりやすいビジュアルと説明で伝えてくれるあのCMだ。CMを見るたびに「そんな技術があったのか……」と感心し、“イノベーション"を連想させる印象的なBGMにゾクゾクして、「世界は、ひとつずつ変えることができる。」という最後のコピーに心を打たれる。
-

富士フイルムの企業CM「世界は、ひとつずつ変えることができる。」シリーズ 提供:富士フイルム
そんな富士フイルムが注力している事業の1つに「医療×AI(人工知能)」というものがある。CT(コンピュータ断層撮影)画像から主要臓器を瞬時に抽出し、病変を検出、そしてレポートの作成までをAI技術を活用した支援技術で行う。医師の知識や経験を注ぎ込んで開発された支援機能は、肉眼では判断が難しい異常もすぐに高精度で見つけ出す。
医療AIを世界中に届け、疾患の早期発見と医療従事者の業務効率化する同事業は、デジタル庁が「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」に貢献している個人や企業に表彰する「2022年度 good digital award」の健康/医療/介護部門で優秀賞を受賞した。
富士フイルムは医療業界に“AI"というメスをどう入れるのか。医療に関するテクノロジーの最前線に迫った。
世界中で抱えている医療課題
医療業界が抱える課題は山積みだ。高齢化が加速している日本の国民医療費は右肩上がりで、厚生労働省の調査によると、2025年の国民医療費は48兆円、2040年になると67兆円を超える見通しとなっている。
特に2025年は、戦後の第一次ベビーブーム(1947年~1949年)の頃に生まれた「団塊の世代」が全員75歳以上の後期高齢者になる。これにより、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上になり、医療費は今後も増加の一途をたどることになる。
医療課題を抱えているのは日本だけでない。世界に目を向けてみると、人口増加による医療費の増大や、医療サービスの地域間格差、医師や看護師などの人材不足といった同様の課題を抱えている。世界の医療費の約8割を先進国が占めており、1700万人の医療従事者が不足している状況だ。
「本気で世界中の医療格差をなくしたい」ーーそう語るのは、富士フイルム メディカルシステム開発センター長の鍋田敏之氏。鍋田氏が掲げる未来図とは。
富士フイルム株式会社
執行役員 メディカルシステム開発センター長 兼 富士フイルムホールディングス株式会社 ICT戦略部次長 鍋田 敏之
1994年東京工業大学 総合理工学部 電子化学専攻修士修了後、富士写真フイルム株式会社(現・富士フイルム)入社。2017年医療ITソリューション事業部長へ就任、医療AI技術ブランド「REiLI」を立ち上げた。18年メディカルシステム開発センター長を兼任し、医療IT・AIを核に据えた付加価値の高い医療機器・サービスの開発をけん引。19年ICT戦略部次長就任、全事業グループにおける製品DX戦略の加速を推進。22年より現職。
70年前から取り組んでいる医療DX
富士フイルムは1999年、病院内の画像データを管理・保管するプラットフォームである 医用画像情報システム(PACS)の提供を開始した。PACSとは、「Picture(画像) Archiving(ファイル保管) and Communication(通信) System(システム)」の略語で、機器から出てきた医療画像データすべてを束ねるものだ。
従来は画像を物理的なフィルムで管理していたが、PACSでは画像データとして医療画像撮影装置から受信する。撮影した画像データは、ネットワークを通じてデータベースに転送され、保管・管理される。従来のようにフィルム倉庫を持って管理したり、フィルムを持って移動したりする必要がなく、画像をデータとして永久に保存できる。業務の効率化だけでなく人的ミスの回避にもつながるシステムだ。
富士フイルムのPACS「SYNAPSE」は2021年3月時点、世界で5700の医療機関に展開しており、日本だけでなく世界でシェア率1位を獲得している。鍋田氏は、「高いシェア率を維持できているのは、医療にDXの波がやってくる前から取り組んでいたから。1990年代当時、航空宇宙業界で働いていたエンジニアなどの天才たちを引き抜き、日本だけでなく世界に目を向けて開発を続けてきた」と自負する。
医療業界にAIというメスを入れる
そして同社が医療分野へAIを本格展開させたのは2018年。PACSと2008年に開発した3D画像解析システムから得られる大量の画像データと、同社が70年以上培ってきた医療画像処理技術を掛け合わせたさまざまなAI技術を「REiLI(レイリ)」というブランドとして体系化した。
日本語で、賢いさまを表す言葉「怜悧(れいり)」を由来とするREiLIは、どのようなことを実現させるのか。富士フイルムは医療技術に対して、4つの切り口でAIというメスを入れている。
画像の高画質化
1つ目の切り口は「高画質化」だ。CT画像やMRI(核磁気共鳴画像法)画像の解析をAIで高度化させている。具体的には、画像ノイズや画質を繰り返し演算処理により制御する独自技術を採用しており、これにより、低線量放射線でも視認性に優れた画像が提供できるという。
CT画像やMRI画像の視認性を高めることができ、診療のワークフローの改善にもつながる技術だ。
臓器のセグメンテーション
2つ目の切り口は「臓器のセグメンテーション」。CT画像やMRI画像から、膵臓や腎臓、肝臓、肺など主要臓器を自動で抽出し、内部の構造までセグメンテーションする。例えば、脳の区域は100以上の区域にセグメンテーションすることができる。今後は、対象を全臓器に広げる考え。
また構造が緻密な血管の自動抽出も可能で、非常に細かい部分まで3Dモデルで再現できる。このAI技術は手術のシミュレーションへ活用でき、医師の手術支援にも貢献しているとのことだ。
「全身の主要臓器の抽出技術はほぼ完成している。いまはさらなる周辺臓器や亜区域の抽出を開発している真っ最中だ」(鍋田氏)
コンピュータによる病変の検出
3つ目の切り口は「コンピュータによる検出」だ。同社のAIは、臓器の自動抽出とセグメンテーションを行うだけにとどまらず、病変を検出したり計測したりできる。
例えば、胸部CT画像を解析して、肋骨骨折の可能性がある箇所を検出したり、肺のCT画像から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による肺炎の特徴的な画像所見を有する可能性がある領域をマーキングしたりできる。
「CT画像やMRI画像、X線画像など複数の入力情報を処理できるこのマルチモーダルAIは、将来的には、診断が難しい2次元のX線画像に対して、CT画像で得られる知識を重ね合わせることで病変を検出できる可能性がある。つまり、このAI技術を応用することで『実際には撮影していないCT画像を明確に思い浮かべながら、X線画像を診断できる』製品ができるかもしれない」(鍋田氏)
ワークフローの効率化
最後の切り口は「ワークフロー全体の効率化」。同社のAI技術を活用した支援技術は病変を検出・計測した後、レポート作成の支援も行う。医師の所見を生成する技術で培った自然言語処理のノウハウを、所見文構造化技術に活用している。日常業務において医師の知識のデータベース化を目指している。
富士フイルムが描く画像診断の最終形態はこうだ。CT/MRなどの画像に対して、AI技術を活用して画像をチェックする。何らかの異常・所見があれば、それをもとに医師の読影の優先順位を調整する、また内容に応じて専門医に割り当てて、通知する。そして、レポートも自動で作成され医師がそれを確認するーー。
読影医がAI技術を利用してワークフローを効率化、画像診断を高度化することで、診断の質が向上するだけでなく、医師は激務から解放されるだろう。しかし、「AIに対して誤った認識を持ってはならない」と鍋田氏は指摘する。
「どれだけ技術が進歩してもAIが医師を超えることはできない。AIの教師データは医師が作っているからだ。ただ、世界に医療格差があるように、医師にも技術や知識にバラツキがある。AIをうまく活用することで、自身の診断の質を向上することができるようになるし、誤診の防止にもつながる。AIは医師を超えられないが、“最高の助手"にはなれるだろう」(鍋田氏)
世界から医療格差をなくすために
富士フイルムは、世界中の医療格差をなくすために、AI技術の活用範囲を拡大させている。2021年時点で、70カ国以上でAIを活用した製品を展開している。小型化したX線機器とAI技術をシームレスに連携し、場所に依存せず撮影したその場で最先端のAI技術を活用できるようにした。
-

X線機器とAI技術のシームレスな連携を実現。撮影したその場で最先端のAI技術の活用を可能にした
また、診断支援だけにとどまらず病院の業務や経営の支援にも注力している。富士フイルムは、院内のあらゆる診療情報を漏れなく統合し、統合したデータをさまざまな目的に応じて活用できるプラットフォームを提供している。AIによる支援機能やBIダッシュボードで新しい価値を創造する。
さらに2022年4月には、国立がん研究センターと共同で、工学的な知識が少ない医師でもAIの開発ができるプラットフォーム「SYNAPSE Creative Space」を開発。同社が目指すのは、医師の研究が加速し、社会実装の道筋が明確化して、ビジネスとして収益化していく未来だ。「AI開発の民主化を実現したい」(鍋田氏)
富士フイルムは今後も、AIとPACS、医療機器やサービスを組み合わせ、医療AI技術を活用した製品・サービスを世界中に展開していく。2023年までに100カ国、2030年までに196カ国、つまりすべての国と地域に導入することを目指す。鍋田氏は、「医療現場が業務の負荷から解放され、世界中の誰もが高品質な医療を低コストで受けられる未来をつくっていきたい」と笑顔を見せた。
今回の取材を終えた後、一日中、頭の中で例のBGMが流れ続けていた。世界がひとつずつ変わることで、筆者の「125歳まで生きたい」という夢も叶うかもしれない。