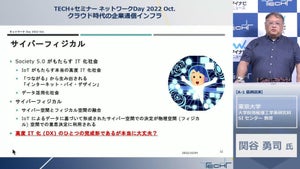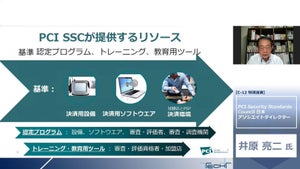大企業がシステム開発を行う際、その大部分を外部の開発会社などに委託するケースが多い。しかし、それではどうしても開発に時間がかかったり、現場事情との乖離が生まれてしまったりする。
そんな中、可能な限り現場社員が主導してアプリを開発することで、スピーディーにDXを進めているのが日清食品グループだ。IT系企業ではない同グループは、どのようにして現場主導の開発を可能にしたのだろうか。
10月25日、26日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+ フォーラム 業務効率改善Day 2022 Oct.自社にいま必要な『業務効率化』を見極める」に日清食品ホールディングス 情報企画部 デジタル化推進室 兼 日清食品 ビジネスソリューション本部 ビジネスストラテジー部の山本達郎氏が登壇。同グループが進める現場主導のデジタル化推進について語った。
全社一丸となって挑む日清食品グループのDX
チキンラーメンやカップヌードルでおなじみの日清食品グループ。即席麺やカップ麺、宇宙食ラーメンなど、さまざまな“世界初”を生み出してきた同グループは、現在、「DX」という領域で新たな挑戦に取り組んでいる。
そのベースとなっているのは、中長期成長戦略で示された3つのテーマだ。具体的には「既存事業のキャッシュ創出力強化」「新規事業の推進」、そして「EARTH FOOD CHALLENGE 2030 (有限資源の有効活用と気候変動インパクト軽減へのチャレンジ)」である。
これらを実現するために、同グループは社内改革に着手。ビジネスモデル自体の変革に加え、効率化による労働生産性の向上を目指している。
改革のポイントとなるのが「社員の意識改革」である。日清食品グループでは経営トップから全社員に向けて次のようなスローガンが打ち出されている。
“DIGITIZE YOUR ARMS(デジタルを武装せよ)”
「このスローガンを通じて、デジタルだからといってIT部門に任せっきりにせず、社員一人一人が自主的に自らの業務を見直し、自らで学び、活用していく組織文化や意識改革の必要性を訴えています。朝礼や社内報などを通じて、経営トップ自らがメッセージを発信することで、社員の意識改革を促してきました」と、山本氏は言う。
単なるツールの導入やシステム開発だけでなく、組織文化の醸成や意識改革という点にまで踏み込んでいるところからも、日清食品グループがDXに並々ならぬ熱量で取り組んでいることが分かるだろう。
現場社員が主導することでコストダウンとスピーディーな開発を実現
日清食品グループでは、RPAツールの「UiPath」、ローコード・ノーコード開発ツールの「kintone」「PowerApps」を採用し、それぞれの特性に応じて使い分けている。
「RPA、ローコード・ノーコード開発ツールの台頭により、誰もが業務の自動化やシステム開発に取り組めるようになったことも、現場主導でデジタル化を推進する上ではポイントになりました」(山本氏)
では、具体的にどのような取り組みを進めているのか。
まずはRPAの開発と活用だ。対象となるのは、システムを開発するには費用対効果が低く、人手で行うしかなかった小さな業務である。例えば、システムからのデータダウンロードやExcelへの転記・加工、メールの作成、システムへの入力やデータチェックなど、幅広い業務にRPAが活用されている。
ただし、「単純に目の前の作業をRPA化するだけでは効果は限定的」だと語る山本氏から、大きな効果を生み出している営業部門の活動事例が紹介された。
同グループの中核事業会社である日清食品では、全国8ブロックの営業拠点からプロジェクトメンバーを選抜、日清食品ホールディングスのIT部門と連携してセールス業務の業務改善とデジタル化を図っている。
その際、最初からRPA化を進めるのではなく、業務全体の見直しから始めるのがポイントだ。まずはセールス業務の現状を調査し、改善候補業務を選定する。改善候補業務については、標準化や重複部分の整理などを行うほか、不要な業務の廃止も検討する。そうやって業務の棚卸しを行い、最後に残った「手作業」をRPA化するという流れだ。業務を移管・集約してRPAを実行することができれば、得られる効果はより大きくなるという。
次に、山本氏はkintoneを用いたアプリ開発の事例を具体的に紹介した
「コロナウィルスの感染拡大を受け、2020年2月に国内グループ約3,000名を原則在宅勤務へ移行しました。その際、紙や捺印が伴う業務については、ペーパーレス化、ハンコレス化を早急に行う必要がありました。そこで、kintoneを活用し、社内の決裁書や申請書などの申請から承認までのワークフローを電子化し、スマホでいつでもどこでも承認できるようにしました」(山本氏)
こうした同グループの取り組みにおいて特徴的なのが、徹底した現場主導型のDXであることだ。アプリ自体も、ローコード/ノーコード開発ツールを活用して、非エンジニアである現場社員が自ら開発するという。
その結果、短期間・低コストでの開発が可能となり、環境の変化にもスピーディーかつ柔軟に対応できるようになった。また、IT部門のリソースについても、システム間連携などを要する高度なアプリの開発に割けるようになったそうだ。