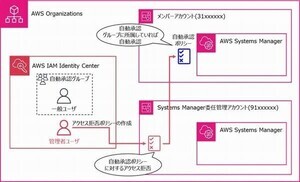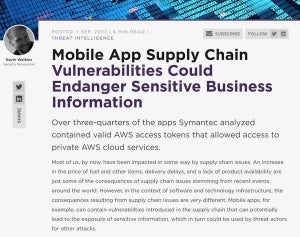宇宙・海・南極大陸を超え、人類はデータという広大な領域に踏み込んだ
世界有数のクラウドベンダーの一つがAmazon Web Services (AWS)だ。提供しているサービスの種類は実に多く、スケーラビリティも高い。世界規模の企業が膨大な量のデータを利用するためにAWSのサービスを使っており、ミッションクリティカルな分野での採用も進んでいる。そんなAWSの年次イベント「AWS re:Invent 2022」が11月28日より、スタートした。
AWSは新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)の影響から、この2年間re:Inventの開催を自粛してきた。今年は3年ぶりの開催となったが、今回のオンサイト参加者は5万人以上、オンラインでの参加者は30万人以上と報告されている。
オンサイト参加者の数は前回よりも減ったことになるが、オンラインでの参加者を加味すると世界中での参加者はむしろ増加したことになる。
AWSは毎年re:Inventで多くの新サービスを発表する。もともとAWSが提供しているサービスは多岐にわたる上、その数は年々増えている。個々のサービスの善を取り上げるだけでもかなりの数になる。加えて、re:Inventの基調講演では矢継ぎ早に新しいサービスが発表されるので、全体像を捉えるのはとても大変だ。
2022年のAWS re:Inventの基調講演でAWSの最高経営責任者(CEO: Chief Executive Officer)であるAdam Selipsky氏は、「宇宙 (Universe)」や「海 (Ocean)」 「南極大陸 (Antarctica)」をモチーフに取り上げて、同社や顧客が取り組む問題を比喩しながら説明を行った。
宇宙のように膨大なデータ、ブラックホールのように難しい課題、探索が進んでいない未知の深海に似た膨大で見通しの悪い問題、南極大陸のように過酷な環境で対処するように、現実においてもシビアな要求を解決するツール――Selipsky氏は、人類がこれまで宇宙や深海や南極大陸の探索に費やしてきた取り組みを、現在のITやクラウドに対する取り組みに対比しながら説明を行った。
もう一つ、大きなモチーフとして取り上げられたのは「想像 (Imagination)」だ。Selipsky氏は、想像の世界を実現していくにはスケーラビリティ制約の撤廃、まるで異なるアイディアの統合、他者とのコラボレーションが必要だと指摘し、これらを実現するためにAWSが新しいサービスを導入したと語った。
2022年の基調講演で発表された「NEW!」は約20
前夜のナイトライブイベントでの発表を除けば、Selipsky氏の講演がre:Invent 2022最初の基調講演となる。この2時間の基調講演の間にAdam Selipsky氏が取り上げたAWSのサービスは多彩だ。そして、基調講演で初めて発表する新しいトピックとして、約20のサービスや新機能が発表された。
主な新機能に関しては、次のページから詳細を知ることができる。
- Announcing Amazon OpenSearch Serverless (Preview)
- AWS announces Amazon Aurora zero-ETL integration with Amazon Redshift
- AWS announces Amazon Redshift integration for Apache Spark
- AWS Announces Amazon DataZone
- Announcing Amazon Redshift integration for Apache Spark with Amazon EMR
- AWS Announces Two New Capabilities to Move Toward a Zero-ETL Future on AWS
- AWS Announces Five New Capabilities for Amazon QuickSight | Business Wire
- New question types for Amazon QuickSight Q
- Amazon QuickSight announces Paginated Reports
- AWS Announces Three Amazon EC2-Instances Powered by New AWS-Designed Chips
- Announcing Amazon EC2 C7gn instances (Preview)
- AWS Announces Amazon Security Lake
- AWS announces Amazon EC2 Inf2 instances (Preview)
- Announcing Amazon EC2 Hpc6id instances
- AWS Announces AWS SimSpace Weaver
- Amazon Connect forecasting, capacity planning, and scheduling is now generally available
- Amazon Connect announces Contact Lens agent performance evaluation forms (Preview)
- Amazon Connect now provides step-by-step guides in agent workspace (preview)
- AWS Announces AWS Supply Chain
- AWS Announces AWS Clean Rooms
- Introducing Amazon Omics
これら発表に共通しているのは、それぞれが目的の異なるサービスということだ。繰り返しになるが、AWSのカバーする範囲は多岐にわたるため、それぞれの領域で必要とされる新機能が導入されているのだ。
企業ユーザーとしては注目したいのは「AWS Supply Chain」
本誌の読者は企業ユーザーが多いことを踏まえ、今回は数ある新サービスの中から「AWS Supply Chain」を紹介したい。
「AWS Supply Chain」はAmazon.comの30年近くにわたる経験に基づいて開発された意思決定支援サービスだ。サプライチェーンの可視化、サプライチェーンデータの自動統合と分析、リアルタイムモニタリング、傾向の提示、正確な需要予測などを行い、リスクの軽減とコストの削減に寄与するという。
ここ数年、サプライチェーンにまつわるリスクは高まっている。従来の自然災害などによる問題に加え、地政学的な問題やサイバー攻撃、新型コロナウイルス感染症(COVID‑19)の影響など、前例のない需要と供給の変動にさらされている。
このような状況で企業は、的確に需要に対応しつつコストの削減を図る必要があるという、これまで以上のストレスを抱える状況になっている。
「AWS Supply Chain」は、リアルタイムでデータを収集および分析を行って視覚化、さらに機械学習機能などに基づいてリスクを知らせるなど、意思決定に役立つ動作を提供してくれる。
こうしたツールを実際に活用できるかどうかは状況によって異なるが、導入および活用が可能である場合には大きなメリットが得られる可能性がある。サプライチェーンに関与する業務に携わっている場合は、調査の対象に加えておきたいサービスだ。
なお、発表時点でAWS Supply Chainの提供に日本は含まれていないが、ユーザーからの要望に応じて提供を行うとしている。