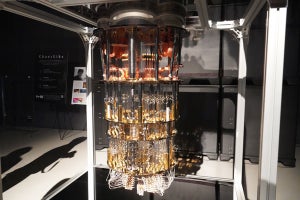昨年にパートナーエコシステムの形成に10億ドルの投資を明らかにし、エコシステムに注力するIBM。昨今ではハイブリッド/マルチクラウドにより、企業は1社単体の製品のみの利用ではなく、複数ベンダーの製品を利用することが当たり前になりつつあり、IBMのみならず多くの企業でエコシステムの形成に身骨を砕いている。
本稿では、今年1月に同社の米IBMでエコシステム・ゼネラル・マネージャーに就任したKate Woolley(ケイト・ウーリー)氏と日本IBM 常務執行役員 テクノロジー事業本部 副本部長兼パートナー・アライアンス事業本部長の朝海孝氏に、これからのエコシステムについて話を聞いた。
直販から協業・協調型に変化したIBM
--まず、改めてパートナーエコシステムの重要性について教えてください。また、IBMとしての“パートナーエコシステム”とはどのようなものでしょうか?
ウーリー氏(以下、敬称略):IBMにおけるエコシステムの定義として、ディストリビューターやリセラー、システムインテグレーター、ISV(Independent Software Vendor)などのビジネスパートナーに加え、ハイパースケーラーやソフトウェアベンダーといった戦略的パートナー、技術パートナーもエコシステムの範囲に含まれます。
なぜ、いまエコシステムなのかと言えば、シングルベンダーとともに、お客さまにどのようにアプローチして共創するのか、ということが重要になっています。
そのため、シングルベンダーとのビジネス上の付き合いというわけでなく、エコシステム内でのパートナーという位置づけです。当社は戦略としてエコシステムの重要性を再認識し、フォーカスするとともに投資を行うなど、エコシステムを優先事項の1つとして判断しました。
これまで、直販でビジネスを行っていたお客さまはグローバルにおいて5000社程いましたが、現在はIBMが直接つながりがあるお客さまは400社まで絞り込んでいます。
朝海氏(以下、敬称略):誤解がないように説明すると、5000社のうちIBMをメインに据えているお客さまばかりではありません。そのため、直販だけでは見方が狭いことから、パートナーと共同で広範囲にわたり、サポートすることで価値のある提案につなげていくという意味合いです。
お客さま視点では、これまでIBMは直販による提案のイメージが強かったのですが、協業・協調型に変化しています。
IBMのエコシステム戦略
--IBMにおけるエコシステムの戦略は?また、具体的な投資の内容を教えてください。
ウーリー:私は今年1月にエコシステムのジェネラルマネージャーに就任しましたが、着任してからの100日間で100のパートナーと話し合い、意見をもらいました。その中でも、2つのテーマがよく話題にのぼりました。
1つは、ビジネスがしやすいパートナーになってほしいということ、2つ目は戦略的な方向性に関するものでした。まず、ビジネスがしやすいパートナーになるためにCRMの専用サイトとして「IBM Partner Portal(IBM パートナー・ポータル、日本でも提供)」を立ち上げています。
これは、パートナーからのフィードバックとSalesforceプラットフォームにもとづき、パートナーのエクスペリエンス(体験)をシンプルかつ合理的に改善するパートナーとIBMをつなぐ新しい取り組みです。
例えば、何かしらの取引が発生した際はIBM パートナー・ポータルに案件を登録すれば、すぐにパートナーと共有できる機能があります。従来は10日間以上かかっていましたが、現在では2日間に短縮されています。
また、今後はパートナー向けのプログラムの拡充を予定し、先日にはパートナーへのトレーニングや人材育成なども無償で提供すると発表しています。これまではIBM単体でしたが、今後はエコシステムのパートナーも含めるなど範囲を広げていきます。
投資に関しては2022年はブランド特化型パートナーセラー(製品担当営業)は倍増し、テクニカルパートナーセラーは35%増加しました。さらに、戦略的パートナーとさらなる関係を深めるためにシステムインテグレーターや大手IT企業などを対象に、リソース、サポート面含めて2023年も投資は継続します。
IBMの“新生エコシステム”
--GMに就任して、エコシステムの担当者として感じたことはありますか?また、昨年に分社化したKyndrylもパートナービジネスは重要です。関係性は、どのようにお考えですか?
ウーリー:パトーナーの方々には、“IBMが変化している”ことを実感していただいていると思います。ビジネスの関係性を深めるとともに、成長していくというポジティブな反応もありました。
また、Kyndrylは、われわれのエコシステムの一環を成すと同時に、重要なパートナーです。そのため、強いパートナーシップをエコシステム内で継続していきます。
朝海:例えば、従来であればIBM社員向けにしか提供していなかった研修プログラムなどをパートナーに開放し、同じレベルの情報にアクセスできるようにしています。これまで、IBMに聞かなければ把握できなかったものが、ダイレクトにパートナーの社員さんがアクセスできるようになったため、ポジティブに受け止められています。
分社化した理由としては、IBM内ではIBM製品を中心としていた一方で、市場はハイブリッド/マルチクラウドにシフトしており、1社ですべてのソリューションを作れない時代になっています。
これまではIBM製品とバッティングする他の製品があったとしても意図的に採用しないというバイアスがあったかもしれませんが、分社化したことでIBMの資本も入っていないことから、選択肢は広がります。
また、IBMとしても選択肢は広がるため、お互いにエコシステムは拡がります。1社ですべてやろうと考えると軋轢はあったかもしれませんが、お客さまからしてみれば水平統合が進むため今の時代に即してシフトしていると感じるのではないでしょうか。
Kyndrylは、最大のパートナーであると同時に、人脈やスキルなどを含めてIBMの戦略としても引き続き重要なため、分社化によるデメリットが出ないようなメリットを見出しています。
--日本のパートナーとの関係性はいかがでしょうか?
朝海:少し前のIBMであれば再販していただくパートナーのことをエコシステムと呼んでいたと思います。
現在は、ハイパースケーラーやソフトウェア企業、システムインテグレーターなどを含めて、すべてエコシステムに集約しています。
それぞれのパートナーからの要求には多様性があるため、全世界共通の組織で把握することで、ナレッジが蓄積され速やかに横展開できることから、さまざまなニーズに対応することが可能です。
そのため、より迅速に高い価値を提供できるようになっており、“新生エコシステム”の強みです。
従来のイメージを払拭
--エコシステム形成に関して何か課題はありますか?また、今後の展望について教えてください。
ウーリー:課題はマインドセットの切り替えではないでしょうか。朝海が言ったように10~20年前は「再販する」ということがエコシステムのイメージとなっていました。
しかし、IBMの新しいアプローチは、従来の考え方をシフトさせることです。そのため、新生エコシステムは、従来の意識をシフトするとともに裏方として支えています。そのためにはパートナー、顧客、市場、IBMに対する理解が必要です。エコシステムは一部だけではなく、広い意味でのパートナーシップだからです。
今後もIBMにおけるエコシステムは優先事項です。私としては今後3~5年以内にエコシステムからの収益を倍増させ、パートナーとともに成長していきます。
朝海:マインドシフト、人的資源を投入していくことに加えて、同一の製品を取り扱うだけでは大きくは変わらないと思っています。そのため、エコシステム内で採用しやすい、使いやすいなど、パートナー自身が提供する製品ともシナジーがある環境が必要です。
そのため、契約形態の変更や製品自体も採用してもらえるように先進的な製品も含めて利用しやすい形にしていく必要があります。
先日にはAIのIBM Watsonに関して、パートナーに加え、お客さま、開発者がAIを活用した独自ソリューションを提供しやすくするためにIBM Watson Natural Language Processing、同Speech to Text、同Text to Speechの3つのライブラリをリリースしています。
これらのライブラリは、例えばAIをソフトウェア企業に採用してもらうためにはAIの部分だけクラウドだと、ソフトウェアのモジュールに入りません。そのため、ライブラリとして切り出して、個別にライセンスできるようにしています。
Natural Language Processingは自然言語処理、Speech to Textは音声認識、Text to Speechは音声合成です。まず、第1弾としてこの3つを発表しています。
自然言語処理は、ユーザーが多ければ多いほど精度は向上していくため、共通項としてIBM製品を利用してもらえればメリットを提供できると考えています。ビジネス規模を大きくするということは水平統合の裾野が広がるため、そのような状況にシフトしていきます。
--今後の優先事項はどのようなものでしょうか?
ウーリー:繰り返しになりますが、パートナーがビジネスを行いやすくし、当社が必要不可欠な存在になることが挙げられます。そのためのツールやプロセスの構築など、さまざまな投資を通じてパートナーへのサポートを提供し、パートナープログラムも拡充していきます。
朝海:特に、日本ではサービス主導の市場のため1社に任せたいという文化は残っています。
このような状況下において水平統合を進めていくことは、従来は一括請負というイメージからのパラダイムシフトを起こすことにつながります。また、ITの役割は人の補完から人ができない領域に変化しています。
そこで、新たな気付きを得れば社会構造全体が変化しますし、よりよい社会になると考えています。このような環境にシフトしていくことは非常に大きなテーマであり、IBMだけでの話ではありません。そのため仲間を増やし、ITで日本社会に貢献できればと強く感じています。