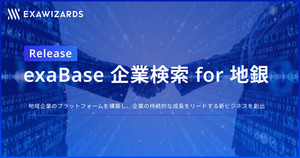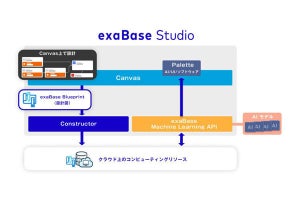AI(Artificial Intelligence:人工知能)を利用したサービスを手掛けるエクサウィザーズはこのほど、「Web3時代×AI」をテーマに、年次イベント「ExaWizards Forum 2022」を東京都内で開催した。
新型コロナウイルス感染症の大流行を経て、徐々に経済活動再開の兆しが見える中で、政府も「骨太方針2022」においてWeb3の環境整備について本格化していく方針を定めるなど、徐々にWeb3やメタバースなどの新技術を用いた事業の土壌が整いつつある。
こうした環境の中で開かれた今回のイベントから、本稿では、米イェール大学の助教授で半熟仮想の代表取締役でもある成田悠輔氏による、Web3時代のAIとDX(デジタルトランスフォーメーション)を軸とした基調講演についてレポートする。
私たちの生活の中でAIが活用されている場面として最も分かりやすいのは、EC(Electronic Commerce:電子商取引)サイトのレコメンド(推薦)機能だろう。過去のユーザーの購買行動や、近しい属性の人がよく買っている商品をAIが学習し、より高精度に購買につながると思われる商品をレコメンドするような機能だ。
このような実世界でのAIの活用について、「現状ではまだ、Webビジネスやゲーム業界など、一部の産業のみに限定されている」と成田氏は指摘していた。今後はさらに広い領域でAIの利活用が進むであろうことは想像に難くない。これからAIの利活用において、成田氏が重要視しているのは「公共領域」だという。例えば医療や司法、警察、軍事、労働、教育などへのAI活用だ。
同氏によると、公共領域の問題解決のためにAIを用いる際には、2つのレイヤーに分けて考える必要があるそうだ。まずは「ミクロなレイヤー」での活用について紹介する。ミクロなレイヤーとは、言い換えると、個々人の問題を解決するためのAIの活用だ。
私たちは近年、スマートウォッチやスマートグラスなどのウェアラブル端末を用いて、以前とは比べ物にならないほど多くの身体情報を容易にデジタル化できるようになった。心拍数や血圧などがデータとして取得できるようになると、心臓発作の予防および予測がスマートウォッチで完結することが可能になるだろう。
将来的には睡眠時間やストレスレベルなどのデータから、精神状態なども適切に把握できるようになるはずだ。これらのデータを用いて、日々の生活の中で重篤な疾患を予防して健康を増進させるような行動変容を促す仕組みが作られるのではないだろうか。このように、AIを用いることで医療が個々人の生活に密着し、「ミクロな」レイヤーでの問題解決が進むと予想できる。
もう一方は「マクロなレイヤー」でのAI活用だ。上述のミクロなレイヤーでのAI活用の例は徐々に現実味を増しているが、政策の設計などマクロな問題解決のためのAI活用はほとんど進んでいない。
成田氏は、新型コロナウイルス感染症流行下での支援金政策を例として挙げ、「マクロなレイヤー」でのAI活用について紹介した。日本では厚生労働省を起点に、コロナ禍でひっ迫する病院の経営を支援する目的から、数兆円もの多額の補助金や病床支援金が支払われた。日本だけでなく、アメリカでも同様の補助金政策が取られたようだ。
これらの補助金は感染者を受け入れるための病床増設や、人員の雇用増加、設備の導入を促す目的で行われたわけだが、アメリカで行われた調査によると、補助金は感染者の受け入れ数には影響を与えなかったことが明らかになっているのだという。つまり、コロナ禍での補助金政策によって政府から病院へいたずらにお金が流れただけだったようだ。
ところで、AIや機械学習をシンプルに表現すると、ある入力値を与えられたときに最も確からしい値を出力するための計算ルールを作る一連の技術や仕組みだと言い換えることができる。
そこで、コロナ禍における補助金のような政策設計をAIや機械学習の視点から考えると、各病院の経営状態や感染者の対応履歴などを入力値として与えたときに、各病院への適正な補助金支給額を出力するようなルールを作ることができれば、まさに理想的な「マクロな」AI活用になると言えるはずだ。
では、なぜこのような公共政策に対するAI活用は進んでいないのだろうか。成田氏はマクロなAI活用を阻む3つの壁を紹介した。
1つ目の壁は、標本数の少なさだ。人を対象としたミクロなレイヤーでのAI開発と比較すると、マクロなレイヤーでAIを開発する際に使用できるデータの標本数は国や自治体の数によって制限されるため、教師となるデータがそもそも少ないのだ。スモールデータから学習しなければならず、大量のデータに基づいて学習ができるAI開発とは大きな差があるとのことだ。
2つ目の壁は、教師データを作成する難しさだ。上述のように、そもそも作成できるデータの数が少ない上、倫理的な観点などからさまざまな条件を割り振ってA/Bテストのような比較検討ができない。サイコロを振るようなランダムなデータを収集した比較ができず、社会が偶然生み出したデータを用いるしかない難しさがある。
さらに根本的な難しさをもたらす、3つ目の壁は、AIモデルを評価する際の損失関数、目的関数、価値観数が不明確である点だ。コロナ禍での補助金政策を例にすると、何が政策の成功であり、何が失敗であるのかを正確に判断する指標が定まっていない。この指標は民意や世論によっても変化するものであり、例えば画像の中に人が含まれているか否かを判断するような画像認識AIのタスクと比較しても、そのAIの性能を評価する難しさを想像いただけるだろう。
成田氏が現在最も興味を持っている課題は、デジタル技術を用いて民主主義や資本主義を表現する手法なのだという。言い換えると、現在は主に紙と鉛筆を用いて手作業で行われている、選挙に代表される民主主義のプロセスを、いかにデータ化するのかといった挑戦である。
成田氏は民主主義について、「人々がどのような政策を求めているかを表す民意のような情報に対し、何らかの意思決定を行うためのルールやアルゴリズムを適用して、最終的な判断を行うプロセスと言い換えることができる」と説明していた。
その最たる例が選挙だ。住民によって投票用紙に記載された候補者名や政党名が入力となり、多数決のようなルールを適用することで議席数や当選者が決まるのが選挙の一連のプロセスだ。
先に述べた通り、民主主義のプロセスは、機械学習におけるデータの入力に基づいた意思決定のタスクに置き換えられる。成田氏によると「現在のデジタル技術やデータ環境であれば、選挙よりもはるかに豊かな民主主義を実現できるはず」だという。現代は選挙以外にも民意を汲み取れるチャネルを多数用意できるからだ。
その例としては、SNS(Social Networking Service)への書き込みが挙げられる。他にも、政治家が行う街頭演説を聞いた際の通行人の反応や態度は、カメラ映像の解析などから明らかになるだろう。また、テレビで政治に関するニュースを視聴した際の生体反応などもスマートウォッチから取得できる。
このように、選挙という意識された行動だけではなく、無意識下での行動までもが民意を測る際の指標になり得るのだ。これらのさまざまな情報源から取得可能なデータを組み合わせることで、それぞれの政策課題についての民意をより機微に把握できるようになる。入力値および出力値をそれぞれ多チャネル化できれば、これまで以上に高次元化された現代的な民主主義を実現できるというのが、成田氏の考えだ。
これまでのAI開発や活用は、ビジネスにおいて何らかのKPI(Key Performance Indicator)を最適化するような、目的関数が明らかな場面を中心に進められてきた。今後ビジネス領域を超えて公共領域でAIを活用するためには、AIが手段を改善するためのツールを超えて、目的関数を自ら発見できるレベルまで技術が発展する必要があるだろう。会社の問題から社会の問題へと、AIのさらなる高度化と利用拡大が楽しみだ。