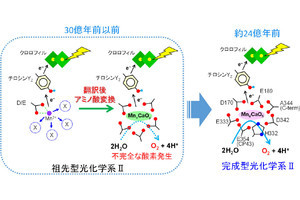東京慈恵会医科大学(慈恵医大)、東京大学(東大)、北九州市立自然史・歴史博物館、ブラジル・リオデジャネイロ州立大学の4者は8月25日、脊椎動物が水中から陸上に進出する際して、肺の形態を「非対肺」からヒトと同様の「対肺」へと変化させていたことを明らかにしたと発表した。
同成果は、慈恵医大 解剖学講座の辰巳徳史講師、同・岡部正隆教授、リオデジャネイロ州立大 Zoologia-IBRAG講座のカミラ・クペッロ講師、同・パウロ・M・ブリト教授、東大大学院 理学系研究科の平沢達矢准教授、北九州市立自然史・歴史博物館の籔本美孝名誉館員らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、生物学と医学全般を扱うオープンアクセスジャーナル「eLife」に掲載された。
地球上の生命はおよそ40億年前から38億年前に水中で誕生したと考えられている。その後、長らく水中でのみ生活し、そして進化してきたが、約4億年前に脊椎動物の一部が上陸を果たしたとされる。
陸上は、浮力がなく、乾燥しており、紫外線なども降り注ぐなど、水中とはまったく異なる生活圏であり、その環境へ適応するには、新たな機能を獲得したり、身体の構造を大きく変化させたりすることが必要だったと考えられている。
そうした、陸上への進出に際して必要とされた臓器の1つが、肺である。水中での呼吸用器官であるエラでは陸上では呼吸ができないため、大気から酸素を取り込む肺を獲得する必要があった。肺は、生物が陸上へ進出し、そして広く拡散していくために、その形態や機能を大きく変化させていったことが推測されている。
ヒトの肺は胸腔内に左右2つあり、それぞれが気管支により1本の気管へと接続されている。しかし肺などの軟組織は化石としてほとんど残らないため、原始的な肺、陸上進出する前に使われていた肺はどのような形態をしていたか、また肺がどのように進化してきたのかは不明だったという。
そうした中で研究チームは今回、現存する水中で生活をする肺を持つ魚(古代魚とも呼ばれている)と、陸上生活をする有尾両生類を用いて、それらの肺の形態を、シンクロトロン放射光X線を用いた詳細な画像解析を行うことで比較することにしたという。