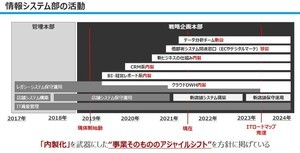自動車業界に変革の嵐が吹き荒れている。テクノロジーの進化はMaaSやCASE※といった潮流を促しており、さまざまな業界からの新規参入者も続出。カーボンニュートラルなど社会問題への対応も急務だ。
こうした変化に適応できなければ、どれだけ歴史のある企業といえども、簡単に沈んでしまう。だからこそ、自動車メーカー各社は資金と人を投じて、技術力を磨いてきた。
そんな中、広島県に本拠を置く自動車メーカーのマツダは、リソース不足という課題を克服するために、ボウリングでいうところの“一番ピン”に集中することを決めた。結果として、これがあらゆる課題解消につながる一手となったという。
マツダはどのようにして一番ピンを見つけられたのか。2月24日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+ EXPO 2022 for LEADERS DX Frontline―変革の第一歩を」に、マツダ シニアイノベーションフェロー 人見光夫氏が登壇し、同社の取り組みと考え方について語った。
※ 2016年にメルセデス・ベンツが発表したコンセプトで、「Connected(コネクテッド)」「Autonomous(自動運転)」「Shared & Services(シェアリングとサービス)」「Electric(電動化)」の頭文字をつなげた造語。
“何も持っていないマツダ”と酷評された過去
マツダは現在、MBD(Model Based Development;モデルベース開発)に取り組んでいる。MBDとは、コンピュータ上に製品の「モデル」を構築し、技術開発や構想、商品開発、実証実験などの一連の流れを全てモデル上で実行する手法だ。
MBD導入により開発生産性が何倍にも向上したというマツダだが、そこに至るまでの道のりは決して楽なものではなかった。
「2000年代初頭、バブル経済崩壊の後遺症で、わが社は存続の危機に立たされていた」と、人見氏は振り返る。
危機に陥ったマツダはその後、フォード傘下で開発受託したエンジン開発に多くの人員を配置するようになり、エンジンの先行技術開発の人員はわずか30人程度にまで縮小することにした。他の大手メーカーが1,000人以上の開発部隊を確保したのとは対照的なこの選択が、その後のマツダを苦しめることになった。
厳しい燃費規制が敷かれ、電気自動車などの次世代環境車がもてはやされるようになるにつれて、マツダは「ハイブリッドや電気自動車といった環境対応技術を何も持っていない」と酷評されるようになったのだ。
「先行開発部門の人員補強は期待できない中、少人数で厳しい環境規制にどう対応し、長期的な技術力や競争力をどう担保するのか。他社がハイブリッド、電気自動車などの大物技術を準備する中、マツダはどうするのか。環境改善という大義や世間の酷評にどう対応するのか。課題は山積みでした」(人見氏)
数多くの課題に対峙した人見氏は、ここで1つの思考法にたどり着いた。それは、「たくさんある課題の中からどれかを選んでやろうとするのではなく、課題の連鎖の“頭”になっている部分を見つけて、そこに集中する」という考え方だった。
“全ての課題を解決する核となる箇所――すなわちボウリングの“一番ピン”である。
一番ピンに集中し、課題の改善へ
多くの課題がある中でマツダの制約となっていたのは、人と資金、一言で言えば「開発リソース」である。やることは山のようにあるのに、人と資金が足りないため、あらゆる取り組みが停滞してしまうのだ。
そこで人見氏が制約を解消するためにとった方針は、「内燃機関の究極の姿を描き、そこへ向けて迷わずに進む」というものだった。なぜなら、課題の中でも改善の余地が大きいのが内燃機関(エンジン)だったからだ。
エンジンの効率改善は、エネルギー損失の低減にほかならない。人見氏は、エネルギー損失を制御する因子を圧縮比、比熱比、燃焼期間、燃焼時期、壁面熱伝達、吸排気行程圧力差、機械抵抗の7つに特定した。
人見氏はこの7つの制御因子の「理想」と「現状」を整理し、それぞれの因子がどれだけ理想から離れているのかを可視化。さらに、現状を理想に近づけるための3ステップを設定し、理想に向けた道筋を作った。
「燃費計算をしたところ、30~40%の改善余地がありました。内燃機関の改善はまだまだ十分にいけるし、規制対応もできると確信しました」(人見氏)
世の中では電気自動車のニーズが高まっている時期だったが、内燃機関搭載車の割合は急激には減らず、2040年でも自動車市場の約70%を占めると見られていた。であれば、内燃機関の改善は企業の責務でもある。これにより、マツダは課題の1つでもあった「環境問題への大義」も手に入れることができた。
こうした方針を打ち出した結果、マツダは高効率直噴ガソリンエンジン「SKYACTIV-G」や、クリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D」の開発に成功。世界中のメーカーや研究機関などから称賛されるまでに至ったのである。
マツダ復活の流れは、人見氏が掲げた「内燃機関の究極の姿を描き、そこへ向けて迷わずに進む」という方針から始まったと言える。理想像が決まったからこそ、他社の動向を気にする必要がなくなり、さまざまな課題を全て同時に進める必要がなくなった。それに伴い、制約となっていたリソース不足も解消できた。内燃機関開発を進めたことで、ハイブリッドに匹敵する燃費が出せるようになり、環境改善という大義にも対応できた。結果として、“何もないマツダ”という世間の酷評を跳ねのけることにつながったのだ。