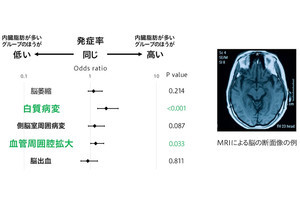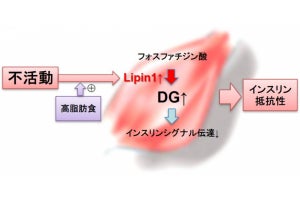北海道大学(北大)は12月1日、脳の視床下部(全身代謝・体温・食欲などを司る脳の一部)の背内側核と呼ばれる神経核において、食後に活性化し食欲を抑える働きがある神経細胞を発見したと発表した。
同成果は、同大大学院獣医学研究院の戸田知得助教らの研究グループによるもの。詳細は代謝学の専門誌「Molecular Metabolism」に掲載された。
近年、世界中で肥満の人が増加しているとされるが、肥満は心臓病や脳卒中などのリスクを増加させるだけでなく、ガンや精神疾患との関係性も報告されるようにもなってきた。
肥満の原因の1つに食欲があり、その食欲を調節する機能は脳の視床下部にあることが知られている。これまでの研究では、遺伝子欠損マウスが用いられることが多かったが、生まれる前から1つの遺伝子が欠損していると神経細胞や神経回路の発生・発達に影響を及ぼす場合もあるため、生理的な条件で食欲を調節する神経の解明が十分であるとは言えないのが現状だという。
そこで研究グループは今回、活性化した神経細胞を蛍光タンパク質で標識できるマウスを使って、食後に脳内のどの神経細胞が活性化するかの調査を行ったほか、特定の神経細胞を人工的に活性化または抑制した時にマウスがどの程度エサを食べるのかの測定や、蛍光タンパク質で標識された神経細胞を1つずつ採取し、細胞内に発現する遺伝子の網羅的測定などを行ったという。
空腹になったマウスにエサを与えて30分後、1時間後または2時間後に活性化している神経細胞を標識したところ、1時間および2時間後に視床下部の背内側核において活性化する神経細胞が増加していることが確認されたものの、これまで満腹中枢と言われていた視床下部の腹内側核や弓状核を含むその他の脳部位では変化していないことも確認されたという。
また、人工的に背内側核の神経細胞を活性化させた場合、マウスの食事量が低下したほか、抑制させると食事量が増加することも確認。この際、神経細胞を活性化させると場所嗜好性が変化することも確認され、心地よさや幸せ感、興奮などといったポジティブな感情にも影響を与えることが示唆されたとする。さらに、当該神経に発現する遺伝子を調査したところ、ダイノルフィンなどの内在性オピオイドの前駆体であるタンパク質「プロダイノルフィン」ならびに、食後に十二指腸や空腸の細胞から分泌される消化管ホルモンとしての作用が有名である「CCK(cholecystokinin)」を発現するグルタミン酸作動性神経であることが判明したという。
研究グループによると、脳内にもCCKを持つ細胞が存在していること自体は知られているが、多くの研究では神経細胞の分類に用いられることが多く、CCKを分泌しているかは十分に分かっていないとしている。今回の研究でもCCKの分泌よりも、グルタミン酸を分泌することが重要であると思われるとしており、食事の1時間後には視床下部背内側核においてプロダイノルフィンおよびCCKを発現する神経細胞が活性化し、満腹感や心地よさなどを増加させていることが、正常体重のマウスがどのように満足感を感じるのかについてのメカニズムの一部を示すものであるとしている。
なお、研究グループでは今回の成果を踏まえることで、食べ過ぎて肥満にならないようにすることや、拒食症の解消への応用などにつながっていくことが期待されるとしている。