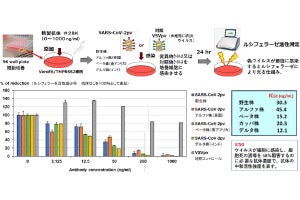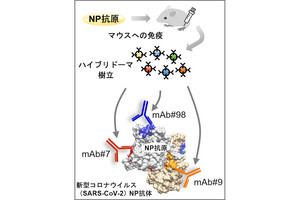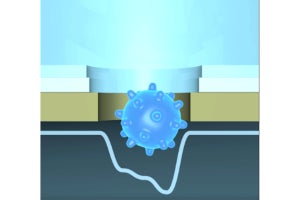理化学研究所(理研)、東京大学、静岡県立総合病院、静岡県立大学の4者は6月18日、血液がんに罹患していない日本、米国、英国、北欧の約77万人を対象に、生まれながらのDNA配列を持つ体細胞と後天的に変異した体細胞が混じった状態(モザイク)である「体細胞モザイク」を解析し、それを持つ人は30人に1人の割合であること、高齢者ほど持つ人の割合が増えること、持つ人は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)などの感染症において、重症化するリスクが高いことなどを明らかにしたと発表した。
同成果は、理研 命医科学研究センターゲノム 解析応用研究チームの劉暁渓研究員、同・寺尾知可史チームリーダー(静岡県立総合病院 免疫研究部長/静岡県立大 特任教授兼任)、同・鎌谷洋一郎客員主管研究員(東大大学院 新領域創成科学研究科 教授兼任)らが参加する国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の医学を扱った学術誌「Nature Medicine」に掲載された。
感染症のリスクは加齢に伴って高まることが知られているが、その関連因子は明らかになっていない。そうした中で、白血球が自分のクローンを作るように増殖する「クローン性造血」が、さまざまな健康被害と関連していることがわかってきたという。
クローン性造血の特殊な形態として「体細胞モザイク(mCA)」があり、白血球のサブタイプであるリンパ球の異常により、大規模な染色体再配列が引き起こされることで生じると考えられている。mCAは白血球数の異常と関連することが知られていることから、研究チームは、mCAを持つ人は感染症にかかるリスクが高いのではないかと考察。今回の研究では、国内外5つのバイオバンクに登録されている計76万8762人の血縁関係のない多民族の個人を対象に、血液DNAを基にしたSNPジェノタイピングアレイデータの解析を実施することにしたという。バイオバンクの内訳は、英国のUKバイオバンク(UKB)、米国のMASS GENERAL Brighamバイオバンク(MGBB)、フィンランドのFinnGen、日本のバイオバンク・ジャパン(BBJ)、米国のコロンビア大学バイオバンク(CUB)の5つだという。
解析の結果、これまでの報告と同様に、mCAを持つ人の割合は年齢とともに増加し、特に男性に多く見られたという。また、末梢血の全染色体にmCAが10%以上存在する人の割合は、40歳未満で0.5%、80歳以上では26.5%に達し、男女別では男性の方が高いことが確認されたという。
また、mCAは性染色体における男女差が大きいことから、性染色体を除く常染色体だけについて調査したところ、mCAが10%以上存在する人の割合は、40歳未満の人では0.27%だが、80歳以上の人では4.6%、男女別ではやはり男性の方が高いことが明らかとなったという。
-

血液に体細胞モザイク(mCA)が10%以上存在する人の割合の年齢推移。(A)全染色体にmCAが10%以上存在する40歳以上の人の割合。40歳未満で0.5%、80歳以上では26.5%(53倍)に達し、男女別では男性の方が高かった。50歳を過ぎた辺りから男女で差がつき始めるのが見て取れる。(B)常染色体(性染色体以外)だけに限定しての、mCAが10%以上存在する40歳以上の人の割合。40歳未満で0.27%、80歳以上では4.6%(17倍)であり、こちらも男女別では男性の方が高いことが確認された。50歳いかのときはわずかに女性の方が多いぐらいだが、55歳から60歳ぐらいにかけて男女差が開き始めるのがわかる (出所:理研Webサイト)
さらにUKB、MGBB、FinnGenのデータを用いて、肺炎や急性呼吸器感染症などの既知感染症のメタ解析を実施したところ、mCAを持っている人はmCAを持っていない人に比べ、疾患のリスク指標であるハザード比が任意の感染では1.2倍、敗血症では2.7倍、呼吸器感染症では1.4倍、消化器感染症では1.5倍、泌尿器系感染症では1.2倍と、mCAを持つ人は感染症、特に重症感染症を発症するリスクが高いことがわかったという。
-

英UKB、米MGBB、フィンランドFinnGenのデータが用いられたメタ解析の結果。mCAを持つ人は持たない人に比べて、感染症への任意の感染のハザード比は1.2倍、敗血症では2.7倍、呼吸器感染症では1.4倍、消化器感染症では1.5倍、泌尿器系感染症では1.2倍であることが確認された (出所:理研Webサイト)
同様に日本のBBJのデータでも調査が行われた結果、がんの既往歴がなく、かつ常染色体mCAを持つ人は常染色体mCAを持たない人に比べて、敗血症による死亡リスクは2倍、肺炎による死亡リスクは1.4倍であることが確認されたという。
加えて、UKBの719人の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の入院症例についての調査も行ったところ、UKBへの登録時(2010年)には44人(6%)がmCAを持っていた一方で、COVID-19感染歴のない対照群33万7877人におけるmCAをもっていない割合は3%ほどであり、危険因子の調整を施したところ、mCAを持っている人はCOVID-19の発症による入院リスクが1.6倍高くなることがわかったとしている。
CUBのCOVID-19患者871人を対象にした調査でも、COVID-19転帰(病気が経過してほかの状態になること)と、世界保健機関(WHO)のCOVID-19進行度に基づいて、患者を(1)軽症、(2)中等症、(3)重症(死亡を含む)の3つのカテゴリに分類したところ、mCAを持つ人の割合は、それぞれ軽症患者では5.8%(16人に1人)、中等症患者では13.9%(7人に1人)、重症患者では16.9%(6人に1人)と、重症になるほど高くなることが判明。mCAが高齢者における新たな感染症の危険因子であることが示されたとする。
-

CUBのCOVID-19患者871人における、進行度別のmCAを持つ人の割合。軽症患者では5.8%、中等症患者では13.9%、重症患者では16.9%と、重症になるほど割合が高くなることが見て取れる (出所:理研Webサイト)
なお研究チームでは、今後、なぜmCAが重症感染症の危険因子となるのかを解明することで、標的予防のための戦略を立てることができるかもしれないとするほか、現在のワクチン接種に対する免疫力やその持続性が、mCAの有無により変化するかどうかを調べることも、感染症学の興味深い研究対象となり得るとしている。