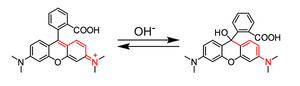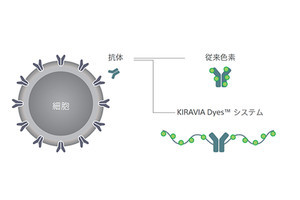東京工業大学(東工大)は、化学反応の経路を予想する理論計算に基づき、凝集誘起発光色素(AIE色素)を設計・合成することで、溶液中では発光せず、固体状態では、分子が吸収した1個の光子を蛍光として放出する確率(発光量子収率)が100%に近い色素の開発に成功したと発表した。
同成果は、東京工業大学物質理工学院応用化学系の大学院生・岩井梨輝氏、小西玄一 准教授、京都大学福井謙一記念センターの鈴木聡 博士、九州大学、大阪大学、仏ナント大学の研究グループによるもの。詳細は、Angewandte Chemie International EditionのWeb版に公開された。
AIE色素は、一般的な蛍光色素とは逆に、希薄な溶液状態では発光せず、固体や凝集した状態で強く発光する性質を持ち、センサや分子イメージングなどへの応用が期待される蛍光色素である。理論計算は、AIE色素の分子設計法として最も簡便かつ迅速だが、実在系で計算から合成・物性検討まで行った例はほとんど知られていなかった。
研究グループは、ベンゼン環が二重結合で連結されたスチルベン類に着目、二重結合のまわりを炭化水素鎖で縛った「橋かけスチルベン」をモデルとした。スチルベン類は、光を照射すると二重結合のまわりで大きな構造変化を起こすことが知られている。
溶液中でも固体中でも強く発光するフェニルスチルベンをAIE色素にするためには、励起(れいき)された分子が溶液中では蛍光を放射しない状態にする必要がある。研究グループは、量子化学をベースに化学反応の経路を計算する方法を用い、橋かけスチルベンのポテンシャルエネルギー曲面を算出した。
ポテンシャルエネルギー曲面とは、特定のパラメータに対して系のエネルギーを表したもので、原子からなる構造の特性を理論的に研究するうえで有用な概念である。
橋かけ部位の長さを変えたスチルベン誘導体について励起状態の溶液中での性質を計算した結果、二重結合を強く縛った場合(n=5,6)には化学反応が蛍光発光する経路を通り、二重結合を緩やかに縛った場合(n=7)には分子が失活して蛍光を放射しないことが予測された。
実際にそれぞれの構造の分子を合成して光物理的な性質を検討した結果、n=7の場合のみ、AIE色素としての特性を示した。また、エネルギーダイヤグラムの各状態と、分子が放射・吸収・散乱する光のスペクトルを測定・解析して得られたデータはよく一致し、理論計算による光物理過程の予測精度が高いことが示唆された。
n=7の橋かけスチルベンは発光のオン・オフをほぼ完璧に行うことができ、サイズが小さく非侵襲(ひしんしゅう)性があり、分析対象の形状や物性に大きな影響を与えることがない。
本研究は、化学反応経路を探索する手法によってAIE色素を合理的に設計することが可能であることを実証した。
研究グループによると、今回用いた設計手法を反応経路自動探索手法や、AIなどの情報科学の手法と融合することで、求める機能を発揮するAIE色素の迅速な開発が行えるようになることが期待されるとしている。また、この設計手法が、AIE色素以外のさまざまな発光材料の設計や光物理過程の予測・解析に役立つものであるとした。
今後の研究では、AIE色素の発光原理の確立を目指すとともに、AIE色素を応用した材料開発を展開していく予定であるとコメントしている。