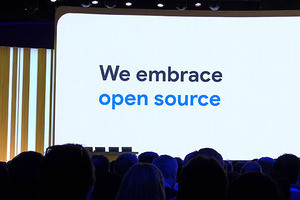クラウドは運用コストと資本コストを抑え、市場投入までの期間を短縮し、絶え間なく変化するニーズに対応できる能力を提供する。そのため、ここ数年でオンプレミス中心のIT環境からクラウドの利活用が加速すると見られてきた。しかしながら、Googleによると、クラウド上で動くワークロードはまだ20%程度である。
セキュリティ、運用の負担、ライセンスポリシーなど既存環境への影響を避け、オンプレミスとクラウドを組み合わせた複雑な環境を管理・運用していくのは容易ではない。そうした課題から、数年前に予測されていたほど迅速なペースでハイブリッドクラウドの採用が進んでいないのが現状だ。
また、ベンダーロックインも危惧されている。クラウドベンダーに強く依存するクラウド環境になってしまうと、テクノロジーの柔軟性を失い、突然の仕様変更やサービス停止のリスクにも直面する。あるアナリストは、88%もの企業がマルチクラウドを採用すると予測している。だが、戦略的に取り組まなければ、プロプリエタリな基盤とAPIで固められたクラウドサービスの断片化が起こる環境、運用コストの増加に悩まされることになり得る。
米サンフランシスコで開催されたGogole Cloud Next '19 (4月9日~11日)、第1日目のキーノートは、そうした既存システムのモダナイズに対する企業の不安の払拭を大きなテーマとしていた。
- 全てをクラウドに移さずにITインフラをモダナイズする方法は?
- 2つのアーキテクチャをブリッジして移行する方法は?
- ロックインを避け、柔軟性を保つ方法は?
数多くの企業のCIOとのミーティングを重ねてきたというEyal Manor氏(エンジニアリング担当VP)が、ある大手リテール企業のCIOの次のようなコメントを紹介した。
「クラウドベンダーに依存しないオープンソース技術のみで構築したい。それがリスクを抑えてクラウドへの投資を進められる唯一の方法になる」
最初の大きな発表は「Anthos」だった。昨年のNext '18で発表した「Cloud Services Platform」の正式サービスである。
Cloud Services Platformは、コンテナ化されたワークロードやサービスを管理するためのオープンソースプラットフォーム「Kubernete」と、それをサービスメッシュ化する「Istio」を組み合わせたクラウド活用をサポートする。Kubernetes環境をオンプレミスで動作させる「GKE On-Prem」とともに、ハイブリッドクラウドの採用を検討する顧客に、サービスの構築、実行、管理をシンプルにするソリューションを提供する。ハイブリッドクラウド・ソリューションである。
しかし、それだけでは「顧客が抱える大きな問題の1つが未解決のままです」とSundar Pichai氏 (Google CEO)。Anthosでは、Amazon Web Services (AWS)やMicrosoftの Azureのようなサードパーティクラウドも対象にしたマルチクラウド対応を行う。環境ごとにコンフィギュレーションをカスタマイズする煩雑な方法から解放し、首尾一貫した体験で、アプリケーションを柔軟にデプロイ、管理できる。Accenture、Cisco、Dell EMC、HPE、Intel、Lenovo、NTTコミュニケーションズなど、30社を超えるハードウェア、ソフトウェア、システム インテグレーションのパートナーとともにに、ハイブリッドやマルチクラウドのアプローチをとる顧客をサポートする体制を整えた。
Jennifer Lin氏 (プロダクトマネージメント担当ディレクター)は、「マルチクラウドやハイブリッド戦略を打ち出す企業は珍しくはありません。しかし、それを皆さんが実際に達成できるようにするプラットフォームはAnthosだけです」とアピールした。
ひと口にクラウド・ソリューションといっても、産業や企業ごとにニーズや目的が異なる。顧客がそれぞれに適した方法を見いだせなければ、真のソリューションにはなり得ない。そうした顧客個々の要求を満たして目標を達成できるように、Googleはビジネスソリューションプロバイダーとして顧客を深くサポートする体制を強化してきた。例えば、金融、ヘルスケア、小売り、製造、通信、メディア&エンターテインメントにフォーカスした「デジタル移行ソリューション」を用意、スペシャライゼーションパートナーの分野にマーケティング・アナリティクス、IoT、セキュリティトレーニングの3つを追加した。
そうした取り組みの成果は、基調講演にPhilips、JPMorgan Chase、Colgate-Palmolive、Kohl'sといった様々な産業からのパートナーが次々に登場したことに現れていた。
ただし、そうしたエンタープライズ戦略の王道を行くようなGoogle Cloudに対して、初期の頃にあった独自性が損なわれていると見る向きもある。大手企業での採用例を紹介し、パートナーとの協業の成果を強調するのは、他のエンタープライズ向けサービスを提供する企業もやっていることだ。
だが、そうした王道戦略が実際に成果を出しているのも事実。問題は、そこにGoogleらしさがあるか、否かだ。
それを意識していたのかは分からないが、第1日目の基調講演の最後に、オープンソースソフトウェア(OSS)ベンダー7社とデータ管理/アナリティクス分野での戦略的提携を発表した。
Confluent (Apache Kafka)、DataStax (Apache Cassandra)、 Elastic (Elastic Search)、InfluxData (InfluxDB)、MongoDB (MongoDB)、Neo4j (Neo4j) and Redis Labs (Redis)といったOSSベンダーが提供するマネージドサービスをGoogle Cloud Platform (GCP)に統合。ユーザーはGoogle CloudのコンソールからOSSベンダーのサービスを導入・管理できるようになり、料金請求もGoogle Cloudのサービスにまとめられる。
提携を通じて、OSSベンダーの課題となっている"サービスのマネタイズ”に新たなオプションをもたらし、GCPでオープンソースを活用してアプリケーションを構築する幅広い選択をユーザーにもたらす。オープンソースのデータ管理/アナリティクス・プラットフォームは今日数多くのクラウド・アプリケーションの基盤となっている。オープンソース・コミュニティとの共存共栄を通じて、技術の成長や市場の拡大を促す。Googleらしい発表だった。
このように第1日目 (4月9日)の基調講演は「モダナイズ」にフォーカスした内容だった。次のレポートでは、それを踏まえた2日目 (4月10日)の内容を紹介する。モダナイズに踏み出した企業が浴する恵み、新たな可能性についてだ。