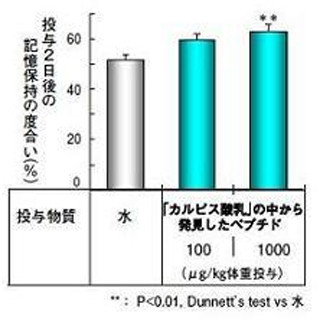東京大学は1月4日、「麹(こうじ)菌」などの糸状菌(カビ)が、細胞どうしで連結する際に隔壁に開ける穴を、糸状菌特有の細胞小器官「オロニン小体(Woronin body)」が開閉して細胞間の連結を制御している仕組みを発見し、さらにこれによって麹菌が酵素を生産するために働く細胞と休む細胞を区別していることを明らかにしたと発表した。
成果は、ユトレヒト大学大学院生のRobert-Jan Bleichrodt氏、同・Han. A. B. Wosten教授、東大大学院 農学生命科学研究科 応用生命工学専攻の丸山潤一助教、同・北本勝ひこ教授らの国際共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、科学誌「Molecular Microbiology」2012年12月号に掲載された。
麹菌は、古くより日本酒・しょうゆ・みそなどの日本の伝統的醸造産業で用いられている。日本酒造りでは「アミラーゼ」を生産し、蒸米のデンプンを分解、酵母のエサとなる糖を供給する。そしてしょうゆやみそ造りではプロテアーゼを生産し、大豆のタンパク質をペプチドに分解、味や香りの形成に貢献するという具合だ。
最近注目されている甘酒や塩麹では、麹菌の作る酵素が健康や美容の機能性に重要な役割を果たしているといわれている。このように、麹菌は多種多様な酵素を生産することで、醸造において重要な役割を担っているのだ。
麹菌は糸状菌であり、細長い細胞が連なった菌糸を伸ばしながら生長する。細胞と細胞の間は隔壁で仕切られているが、中心に小さい穴「隔壁孔」が開いているので、隣り合う細胞どうしは常に連絡していると考えられてきた(画像1)。
しかし実際に、隣り合う細胞が常に連絡をして同じ活性で働いているのか、それとも隔壁孔を閉じて働く細胞と休む細胞を区別しているのかは、これまでわかっていなかったのである。
丸山助教と北本教授らはこれまでの研究で、「固体培養」(日本の醸造で行われている蒸米などの固体上で培養をする手法)の麹菌のコロニーに水をかけると先端細胞が溶菌することを発見しており(画像2)、オロニン小体(画像3)という糸状菌に特異的に存在する細胞小器官が隔壁孔をふさいで、隣の細胞が溶菌の巻き添えに遭わないようにすることなどを明らかにしてきた(画像4)。
このオロニン小体は1864年にロシアの菌学者Mikhail Stepanovich Woroninに発見されてから、2000年になってようやくアカパンカビでそれを構成するタンパク質分子が同定され、分子レベルの解析が可能になったといういきさつがある。現在でもその働きや形成機構について、まだ解明されていない部分が多い糸状菌特有の細胞小器官だ。
丸山助教と北本教授らは、今回ユトレヒト大学のWosten教授らと共同研究を実施。そこで、通常の生育条件でもオロニン小体が一部の隔壁孔をふさぐことを発見したのである。
さらに、その隔壁孔の近くを顕微鏡で見ながらレーザー光で切断し、隣の細胞からの内容物の流出が早く止まるかどうかで、細胞間の連絡の状態を調べた。その結果、オロニン小体が隔壁孔をふさぐと、隣り合う細胞どうしの連絡が止まることが判明(画像5)。
その生理的意味を調べるため、「グルコアミラーゼ」などの酵素遺伝子の発現量について、蛍光タンパク質をレポーターとして細胞ごとの解析が行われた。すると、野生株では酵素の発現量が高い細胞と低い細胞が見られたが、オロニン小体を欠損した株では発現量が全体的に一様になることが確認されたのである(画像5)。
つまり、オロニン小体が一部の隔壁孔をふさぎ、隣り合う細胞どうしの連絡を止めることにより、酵素生産で働く細胞と休む細胞を区別していることを明らかにしたというわけだ。
今回の成果は、オロニン小体が通常の生育条件でも隔壁孔をふさぐことを発見、そして酵素を生産するために働く細胞と休む細胞を区別するメカニズムを解明した、糸状菌で初めての発見となる。
今後、隔壁孔をふさぐオロニン小体の働きを制御することによって麹菌の酵素生産をコントロールすることが可能になり、日本酒・しょうゆ・みその品質の向上、さらに甘酒や塩麹の機能性を増強できるようになることが期待されると、研究グループはコメントしている。