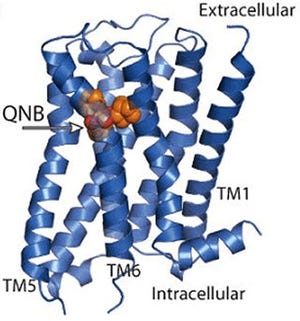東北大学は、嗅覚検査によってパーキンソン病における認知症発症を予測できることを明らかにしたと発表し、パーキンソン病では認知症を合併しやすいことが知られているが、嗅覚検査を行うことで認知症の早期診断・早期治療が可能になるものと期待されるとした。成果は、東北大学大学院医学系研究科神経内科学分野の武田篤准教授、馬場徹医師らの研究グループによるもので、詳細な研究内容は国際科学雑誌「Brain」に掲載された。
武田准教授らの研究グループは、これまでもパーキンソン病における嗅覚障害について研究テーマとして取り組んできた。今回の研究では、重度の嗅覚障害を認めるパーキンソン病患者における3年以内の認知症発症が極めて高率である一方で、嗅覚障害のない患者からは認知症の発症が見られないことを世界で初めて明らかにしたものである。
ほとんどのパーキンソン病患者では、その経過中に認知症を合併することが明らかとなり、大きな問題となっている状況だ。ドーパミン補充を主たるターゲットとする現在の薬物療法はパーキンソン病の運動機能障害の改善に有効性を示すものの、認知機能障害を含む多彩な非運動症状に対しては無効である。実際のところ、現在はパーキンソン病の予後を最も大きく左右するのが、合併する認知機能障害の程度であるという具合だ。
従って、今後のパーキンソン病治療に於いては、認知症の早期発見と治療介入の方法論を確立することが急務となっている。しかし、現在のところパーキンソン病における認知症発症を早期に予測する適切なバイオマーカーがなかったというわけだ。
今回の研究では、認知症を伴わないパーキンソン病患者を対象に「Odor Stick Identification Test for Japanese(OSIT-J:オシット・ジェイ)」という、産業技術総合研究所で開発された日本人向けの嗅覚検査法を実施し、それによって将来の認知症発症を予測することができるかどうかが調べられた。
研究には44名のパーキンソン患者が参加したが、その内の10名が3年間の外来通院中に新たに認知症を発症。その全例が、研究参加時に重度の嗅覚障害を伴っていたことが確認された。
また、重度の嗅覚障害を伴う患者ではパーキンソン病に特有な運動障害が軽度であっても脳萎縮および脳代謝異常が目立つことも判明(画像)。パーキンソン病では、嗅覚に関連した脳領域に特に病変が出現しやすいことが以前から指摘されていたが、重度の嗅覚障害を伴うパーキンソン病患者ではこれらの脳病変が重度であるために認知症を発症しやすかったものと推測された。
今回の研究によって嗅覚検査がパーキンソン病における認知症の予測に有用であることが示されたことから、今後はパーキンソン病における認知症の早期診断・早期治療あるいは予防が可能となり、予後の改善が計られるものと期待されると、研究グループではコメントしている。