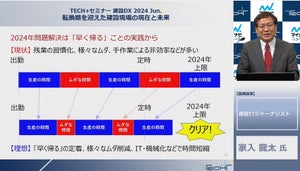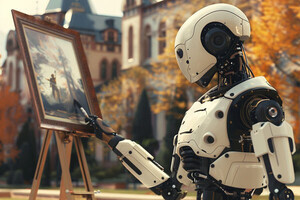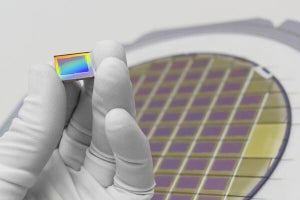名古屋大学 大学院理学研究科の森郁恵教授と甲南大学 理工学部の久原篤講師らの研究チームは、線虫を用いた研究により、神経細胞が別の神経細胞へ2つの相反する情報を伝えていることを発見した。同成果は、英国科学雑誌「Nature Communications」(オンライン版)に掲載された。
現代科学において、神経ネットワークで行われる情報処理の解明は、数多く存在する脳の疾患の原因解明や治療などの医療面、脳の情報処理を手本としたスーパーコンピュータの開発など、多くの分野への応用が期待され、世界中で研究が行われている。しかし、その情報処理の複雑さから、情報の解読は難しい問題とされており、特に人間の脳は約1000億個の神経細胞からできているため、それらがつながり合う神経のネットワークは天文学的な数の組み合せになることが、脳の情報伝達の解析におけるハードルの1つとなっている。
研究チームでは、神経ネットワークが302個の神経細胞から作られている線虫「C.エレガンス」と呼ばれる実験動物を使い、一定の温度下で飼育された後に温度勾配上に置かれると飼育されていた温度に移動するという行動特性をもとに、神経ネットワークの情報処理の仕組みを発見するために研究を進めてきた。
今回、研究チームでは、従来の遺伝子操作技術に加えて神経活動を自由に遠隔操作する技術を使い、神経ネットワークに関わる新しい情報処理の仕組みを発見した。具体的には、神経活動を遠隔操作する手法として、特定の色の光を当てることで働くハロロドプシン(HR)というたんぱく質を使って、C.エレガンスの神経活動の変化と温度への行動対応を調査した。HRは、黄色の光を当てると細胞内に塩化物イオンを取り込み、神経活動を低下させることが知られており、今回、HRを線虫の温度感知神経細胞(AFD)に導入して、AFDの神経活動を行動中に人工的に操作した。
これまでの研究から、AFDの活動が上昇する時はAFDから神経情報を受け取る介在神経細胞(AIY)の活動も上昇するため、AFDはAIYを興奮させる情報を伝えていると考えられていた。しかし、今回、HRを用いてAFDの活動を30%ほど低下させると、AFDと接続しているAIYの活動は30%ほど上昇したことが確認された。
つまり、この結果から、AFDからAIYに「興奮性(プラス)」の情報だけでなく「抑制性(マイナス)」の情報も伝えられていることが明らかになり、これまで「1つの感覚神経細胞は、1つの介在神経細胞に対して、興奮性か抑制性のどちらか一方の情報しか伝達しない」と考えられていたことを覆す、神経情報処理の新しい概念を発見したこととなる。
また、AFDの活動を抑制して70%低下させるとAIYの活動も70%低下したことから、この場合には興奮性と抑制性の両方の情報が伝わりにくくなっていると考えられるという。
さらに、線虫は、神経細胞が興奮性と抑制性の情報を制御することで、高温または低温な方へ移動していることも判明した。
なお、感覚情報の処理に関わる神経システムは、人間と線虫で類似していることから、人間の脳においても今回の研究で発見された神経情報処理の仕組みが当てはまる可能性が高いと考えられ、今回得られた成果は今後、人間の脳の情報処理の仕組みや脳疾患の原因などの解明に役立つものと期待されるという。