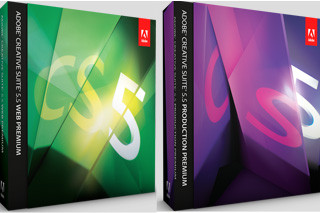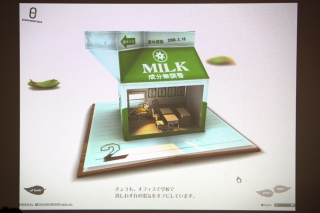ついに「Adobe CS5.5」が発表された。「CS5.5」の発売が待ち遠しいが、今回は改めて復習の意味もこめて、「Flash CS5」に搭載されている主な便利機能のうち、「TLFテキストエンジン」を試してみたい。
「Adobe CS5」体験版はこちらから
TLFテキストエンジン
TLFテキストとは、Text Layout Frameworkを利用したテキストフィールドのこと。従来のクラシックテキストよりも詳細な設定が可能となっている。このTLFは、「CS4」の時には、拡張機能としてベータ版が提供されていた。CS5では従来のテキストフィールドと同じ操作方法で作成できるように、Flash本体に組み込まれている。
ただし、ActionScript 3.0(AS3.0)、Flash Player 10以上でないとこのTLFは機能しないので、注意しよう。
TLFテキストとクラシックテキストの機能比較
クラシックテキストからTLFテキストになって追加された機能を以下に挙げた。
- 詳細な文字スタイル:従来の文字装飾に加えて、行送り、合字、ハイライトカラー、下線、打ち消し線、大文字と小文字、数字スタイルなどが可能。
- 詳細な段落スタイル:複数列にわたる余白の幅、最終行の位置揃えオプション、インデント、一行目インデント、段落間隔、コンテナパディング値の設定が可能。
- 日本語テキスト属性の制御:縦中横、文字組み、禁則処理タイプ、行送りモデルなど日本語独自のルールを設定可能
- 複数のテキストコンテナをリンク:複数のテキストコンテナをリンクすることで、1つのテキストコンテナと見なすことが可能。
- 双方向テキスト:右から左(アラビア語など)と左から右(英語)の表現と混在が可能。
TLFテキストにも、呼び方は違うが、クラシックテキストと同じテキストの種類が用意されている。
表:クラシックテキストに対応するTLFテキストの種類
| クラシックテキスト | TLFテキスト |
|---|---|
| 静止テキスト | 読み取り専用 |
| ダイナミックテキスト | 選択可能 |
| テキスト入力 | 編集可能 |
実際に使用してみよう
TLFで特筆すべき機能のひとつが、テキストコンテナのリンクだ。これは、ふたつ以上のテキストコンテナにリンク設定をしておけば、コンテナ間でテキストのフローが可能となるというもの。実際に、この機能を試してみよう。
1.AS3.0タイプの新規ドキュメントを用意したら、「テキストツール」をクリック。
2. プロパティパネルで、テキストを「TLFテキスト」、タイプを「選択可能」とする。
3. ステージをドラッグして、任意の大きさのテキストボックスをステージ左端に作成し「1234567890」と入力。数字と数字の間には改行を挿入し、全体が見通せるようにフォントサイズを24pxと設定。フォントファミリー、スタイルなども選択する。
なお、この設定は、テキストボックスに対して行われるわけではなく、テキスト1文字単位で設定される。
4. 図のように、ステージに高さが同じくらいの空のテキストボックスを3つ作成する。
5.ステージにある4つのテキストコンテナすべてをリンクしよう。テキストには上下に小さなボックスがあり、上側にあるものをスレッド入力ポイント、下側をスレッド出力ポイントと呼ぶ。これらによって、出力から入力にリンク設定ができる。リンクする方法は簡単で、リンクしたいふたつのテキストコンテナのうち一方のポイントをクリックして、もう片方もクリックするだけだ。クリックする順番は、入力/出力どちらが先でもかまわない。
6. 左端にある数字を10文字とも選択してサイズを大きくすると、リンクしているテキストボックスに繋がっているのが確認できる。
以下に、リンクの操作方法をまとめた。ほとんど直感的にリンクとリンク解除ができるので、試してみてほしい。
テキストボックスのリンク操作方法
- リンク接続はスレッド入出力ポイントをクリック後、接続したいテキストボックスをクリック
- リンクの解除は、繋がっているリンクをダブルクリック
- テキストボックスからテキストが溢れて表示しきれていないときはスレッド出力ポイントに赤い+マークが表示される
- 赤くなったスレッド出力ポイントをクリック後、ステージをクリックすると属性が同じ新しいテキストボックスが複製される
textLayout_1.0.0.595.swzとは?
SWFを作成すると、「textLayout_1.0.0.595.swz」というファイルが同じフォルダ内に作成される。これは、TLFテキストを使用したSWFで必要なファイルだ。WEBサーバーにアップロードし忘れても、AdobeのサイトからFlash Playerがダウンロードするため問題はないが、同じフォルダにFTPアップロードしておくのが安心だろう。次回はボーンツールの「スプリング」を試していきたい。