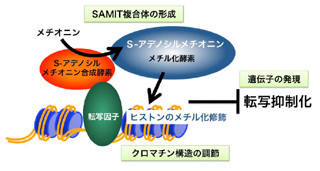理化学研究所(理研)は理研VCADプログラム、京都大学再生医科学研究所、大阪大学タンパク質研究所の研究者らの協力のもと、眼組織のもと(原基)である胎児型の網膜組織「眼杯」を、マウスES細胞から試験管内で立体形成させることに成功するとともに、生後型の網膜組織全層の立体再構築を実現したことを発表した。同研究成果は、文部科学省の「再生医療の実現化プロジェクト」の一環として行われ、英国の科学誌「Nature」4月7日号に掲載された。
ES細胞やiPS細胞などの多能性幹細胞は、すべての種類の体細胞に分化する能力(多能性)を有しており、試験管内で医学的に有用な細胞を産生する提供源として注目を集めている。例えば、ある細胞種が生体内で変性するために起こる病気に対し、ヒトES細胞・iPS細胞などから分化させた細胞を移植して治療しようとする再生医療は、難病克服の切り札として期待が寄せられている。
研究グループは、これまでに、ES細胞などから神経細胞やその前駆細胞を効率良く分化させる方法として、無血清凝集浮遊培養法(SFEBq法)と呼ばれる簡便な方法を開発していた。同手法は、ES細胞やiPS細胞を分化誘導する際に、通常の細胞培養で添加する牛血清や増殖因子を除いた培養液で培養する方法で、3,000個程度の細胞を凝集させ浮遊状態で培養するというもの。
すでに、同方法で、マウスやヒトのES細胞・iPS細胞から、中脳ドーパミン神経細胞、大脳神経細胞、網膜細胞、小脳細胞、視床下部内分泌細胞などに試験管内で分化誘導することに成功しており、現在、この技術の応用として、パーキンソン病や加齢黄斑変性などの治療を目指した前臨床研究が、理研、先端医療センター研究部門、京都大学などの共同研究で進められている。
しかし、単純な1、2種類の細胞の移植で治療できる疾患は限られており、難病の治療などを含むより多くの場合には、生体内と同様に複数の種類の細胞が複雑な組織構造を形成して働く必要があった。そのため、多能性幹細胞からこうした「複雑な組織構造」の立体形成を試験管内で再現できるかが、基盤技術上の大きな課題となっていた。
研究グループでは、これまでの基礎的な脳発生の研究成果を基に、「複雑な組織構造」の立体形成の研究を続けてきており、ES細胞からのSFEBq法による「試験管内での3次元自己組織化技術」を開発してきた。その成果の一部として、2008年にはマウスやヒトのES細胞から層構造を持った大脳皮質組織の立体培養に成功した。これは画期的な成果であったが、形成した組織は、胎児型での大脳発生の初期の構造を有するというところまでで、生後型の大脳に見られる程の複雑な組織構造の形成には至らなかった。

|
|
図1 網膜組織の基本構造。網膜は光を感知する感覚組織で、光を受容し電気信号に変換して脳へ伝える「神経網膜」と、その外側を包むように存在する「色素上皮」の2つの組織からなる。光を直接受容する細胞を視細胞と呼ぶが、色素上皮は視細胞の生存と機能に必須の役割を果たす。そのどちらが変性したり、傷んだりしても、著しい視機能の低下をもたらす |
眼の主要機能部である網膜組織は、初期胚の間脳組織に由来する中枢神経系組織で、複雑な組織変形を経て形成していく。今回、研究グループは、より高度で複雑な網膜組織構造の試験管内での形成に挑戦した。

|
|
図2 網膜組織の原基(眼杯)の発生。哺乳類胚の発生初期に、間脳の一部が左右に袋状に突出してできた「眼胞」が網膜の起源である。眼胞の体表面に近い部分は神経網膜に、間脳に近い部分は色素上皮に分化する。神経網膜の部分は、胎生10~11日の間に内側に陥入する。その結果、網膜は色素上皮を外側の壁、神経網膜を内側の壁にした2重構造の杯型の「眼杯」を形成する |
具体的な手法としては、まず、網膜前駆組織への分化に適した培養液を検討するなどの改良を行った(改良SFEBq法)。また、胎児型の網膜前駆組織が、上皮構造(1層の細胞のシート構造)を持つことに注目、上皮構造を安定化させることが知られているラミニンやエンタクチンを含む細胞外マトリクスタンパク質の混合物を培養液に添加することで、5割以上の培養細胞を網膜前駆組織(Rx というマーカー遺伝子を発現する)に分化誘導することに成功した。

|
|
図3 改良SFEBq法によるES細胞からの網膜前駆組織の分化法。マウスES細胞を酵素でバラバラの細胞に分散したものを、3,000細胞ずつウェル(細胞のための小さなくぼみ)に入れ、凝集塊を作らせる。網膜への分化に最適化したラミニンなどの細胞外マトリクスタンパク質を含む培養液で数日間立体浮遊培養すると、網膜前駆細胞へ高効率に分化する |
次にこの改良SFEBq法を用いて、7日間ES細胞の細胞塊を浮遊培養し続けると、細胞塊の中に形成した網膜前駆組織の上皮構造に大きな変化が起きることが判明した。最初に網膜前駆組織(Rx陽性)が細胞塊の外へ向かって、袋状に突出しだし、その後、さらに2日間培養する過程で、袋状の網膜前駆組織のうち細胞塊本体から遠い部分が、今度は袋の内側に向かって自然に陥入するようになった。この結果、網膜前駆組織は、培養開始10日目までに内外の2層の上皮シートからなるカップ状の構造を形成した。
これは、胚発生過程の網膜の原基である「眼杯」に酷似しており、形だけでなく、局所のマーカー遺伝子の発現パターンも眼杯と同様であった。胚の中と同じく、2層の上皮シートのうちカップ状の外側の壁は、色素上皮からなり、色素を蓄積することも判明した。
一方、陥入して形成した内側の壁は、神経網膜の前駆組織に特異的なマーカー遺伝子を発現していた。眼杯は、マウス胎児では胎生10~11日に完成し、直径300μm程度のサイズで、マウスES細胞から形成した眼杯もこれとほぼ同じサイズであったとしており、このように多能性幹細胞から複雑な器官の原基の3次元形成に成功したのは、世界で初めての成果だという。
複雑な眼杯の形成も、ES細胞を単純に均一に凝集させた細胞塊から生じ、しかも均一な培養液の中で浮遊培養しただけで実現できた。単純な要素(この場合は細胞)の集合が、外部からの細かい指示がないにも関わらず、自然と複雑な構造を形成することを「自己組織化」というが、今回の場合は「ES細胞から複雑な眼杯の自己組織化が起きうる」という現象を発見したこととなる。
次に、自己組織化の機序を解明するために、特別に組み上げた長期立体培養用顕微鏡による3次元多光子励起蛍光イメージングを数日間かけて行い、細胞凝集塊からの眼杯形成過程を詳細に検討を行った結果、ES細胞由来の網膜前駆組織は、まず色素上皮と神経網膜の領域に自発的に分かれ、神経網膜の組織は外からの力などで変形するのではなく、自らの力で内側にくぼんで行くことが分かった。すなわち、網膜前駆組織には元々「眼杯の形」を作るプログラムが内在されていて、それが発揮できる環境で培養すると、自然と眼杯を形成する自己組織化が誘発されることが判明したという。
加えて、眼杯形成における内在的な「自己組織化プログラム」についても解析を実施し、力学計測法や独自に開発した組織内圧の解析法を用いて、網膜前駆組織の1層の細胞シートである上皮構造の中での力学特性の動態を調べた。その結果、以下の3つの「組織構造の局所ルール」を順序だって発揮することで、この複雑な眼杯の形が決定していくことが明らかとなったという。

|
|
図5 ES細胞由来の眼杯の自己組織化の機序とシミュレーション。今回の研究での解析の結果、胎児眼でもES細胞培養でも、眼杯の形成は4つのステップからなり、たった3つの「組織構造の局所ルール(青字)」によって、その形を決定していることが判明した。そのルールで網膜組織の変形についてコンピュータシミュレーションを行ったところ、この3つのルールだけで眼杯組織の形が3 次元的に再現されることも明らかになった |
培養7日までに形成した網膜前駆組織は、ES細胞塊の本体から丸く飛び出した上皮の袋状の構造を示している(胚の眼胞と良く似ている)。次の2日間の間に
- 飛び出した眼胞様の袋の中で、ES細胞塊本体から遠い部分が神経網膜の前駆組織に運命付けされ、その部分が他の部分より構造的に「変形しやすい柔軟な組織」になる。これは、神経網膜組織では、細胞の中のバネに当たるミオシンが不活性の状態(柔らかいバネの状態)になるためである。
- 次に、色素上皮と神経網膜の境目の細胞が特別な「くさび形」に変わり、色素上皮と神経網膜の「折り返し部分」で鋭角なカーブを形成する。
- 最後に、神経網膜組織が盛んな細胞分裂により急速に面積が大きくなり、それにより横方向の圧力が生じて、自らを眼杯の内部へ変形させ、陥入して行く。
研究グループは、これらの局所ルールが働いていることを実験的に観察するとともに、コンピュータによる組織形成シミュレーションを用いて、これらの3つのルールだけで確かに眼杯の形が決定できることも証明した。
さらに研究グループは、試験管内でES細胞から3次元再構築した眼杯組織(胎児型網膜組織)から、生後の眼で見られるような多層の神経網膜組織(生後型網膜組織)の形成に挑戦した。分化培養10日後に、形成したES細胞由来の眼杯組織を細いピンセットで単離し、さらに14日間立体浮遊培養を行なった(合計24日間の培養)。その結果、その間に眼杯の内壁である神経網膜組織の細胞が盛んに分裂して、自然と重層化するようになり、培養24日後には、神経網膜を形成する6種類の主要細胞(視細胞、水平細胞、双極細胞、アマクリン細胞、神経節細胞、ミュラー細胞)のすべてを含み、しかも、それらが生後の眼組織に見られるように順序正しい層状構造を形成した。
また、神経網膜組織内のシナプスの形成も形態的に確認しており、分化培養10日後には直径300μm程度のカップ状であった神経網膜は、24日間の培養後には2mmの直径に達する大きな上皮構造になっていた。

|
|
図6 自己組織化によるES細胞からの神経網膜全層の立体形成。ES細胞由来の神経網膜を培養10日後に切り取り、さらに2週間、高濃度の酸素下で3次元浮遊培養を行ったところ、大きく均一に成長し、生後の網膜で見られる視細胞をはじめとする網膜細胞が整然と多層をなした立体構造を形成した |
これまで、眼杯の形成原理について相反する仮説が出されていたが、今回、網膜前駆組織自体が持っている内在的な自己組織化プログラムで眼杯形成が起こることが明確に証明されたことで、1世紀にわたる論争に結論を与え、組織・臓器の形の決定機構に新しい概念が導入されたこととなる。
今回の成果は、高度の機能性を有する「人工生体組織」を試験管内で多能性幹細胞から形成させ、それを移植する「次々世代の再生医療」の可能性を拓く画期的なものと期待される。
多能性幹細胞由来の人工網膜組織については、これまでの細胞移植法のアプローチでは十分な組織再生が見込めなかった神経網膜でも、再生医療の実現に近づける一歩となることが期待でき、特に視細胞のゆっくりとした変性・壊死により起こる網膜色素変性症は国内に数万人の患者が存在し、失明に至る重篤な網膜疾患だが、その多くは遺伝性で、原因となるいくつかの遺伝子も同定されているものの、これまで有効な治療法はなかった。今回の研究成果により、多能性幹細胞から視細胞を含む神経網膜の立体組織を形成し、しかもmm単位のスケールで実現したことで、患者の傷んだ神経網膜に重層する「網膜シート組織移植」の材料作製が、試験管内で可能となる道筋がついたことになる。
研究グループではすでにヒトES細胞からの立体網膜組織の形成技術の開発を進めており、1~2年の間にヒト人工網膜の産生技術を完成させることを目指し、発生・再生科学総合研究センターの網膜再生医療研究チームとの共同研究で、サルなどの中型実験動物へヒト人工網膜組織を移植し、その有効性を確認する「前臨床研究」へ進める予定としているほか、多能性幹細胞由来の立体網膜組織は創薬、毒性試験、病因研究などでも幅広く利用することが可能であるため、緑内障(神経節細胞の変性)などの治療法の開発などにも利用されることが期待されるという。