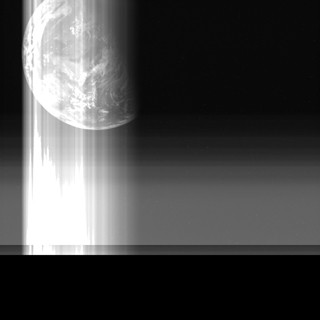国立天文台の渡部潤一教授ほかの研究グループは9月22日、小惑星探査機「はやぶさ」の地球大気圏再突入時の観測データから、探査機本体がバラバラになって光り輝いた時の最大の明るさが、中秋の名月を超えるほどであったことを見い出したと発表した。
国立天文台は「はやぶさ」の大気圏再突入に際し、JAXAとは独立して地上観測チームを編成し、2010年6月13日深夜、オーストラリアのクーバーペディ近郊で同現象の光学的な観測に成功した。
「はやぶさ」本体は地球大気に突入し、流星として発光し、分裂しつつ複数回にわたって爆発的に明るくなった。この時の明るさは、同チームのほとんどの観測装置で観測限界を超えていたため、通常の方法では明るさの算出は不可能だった。
しかし同グループは観測データを詳細に解析し、最大時の明るさのデジタル画像フレームに、「ゴースト像」が写り込んでいることを発見し、その明るさを測定した。
ゴーストは光源に比べて非常に光量が小さく、今回の観測に用いられたデジタルカメラのシステムではその差が約5万倍、約11.7等の差があることがわかっている。同じ条件でベガなどの基準星を撮影して計算すると、このゴーストの元になった「はやぶさ」本体の見かけ上の最大発光時(22時22分20秒頃)の明るさはマイナス13.0等と算出された。
2010年中秋の名月の夜、9月22日23時の月の位相角は約10度で、月までの距離の変化や大気減光や誤差などの細かな要素を無視すれば、マイナス12.4等となる。これより、「はやぶさ」本体の流星現象としての最大発光時の明るさ(絶対等級)は、今年の中秋の名月の明るさを超えてその約3倍に達していたと、同チームでは結論づけている。