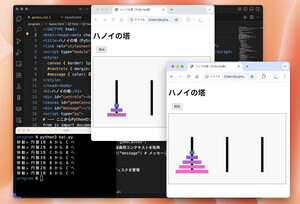では、どうすれば企業は1台も漏らすことなくクライアントPCの省電力化を実現できるのだろうか?

|
Systemwalker Desktop Patrol V14gの省電力設定をユーザーに促す画面。「対処」というボタンを押せば、ポリシー通りの設定に変更される。前回起動時に用いた電力量・電気代・CO2も表示される |
大西氏は、「まずはユーザーの省資源に対する意識を向上させることが大切」と話す。いくら省電力の設定を施したPCを配布しても、ユーザーがそれを変えてしまっては元も子もない。
同製品では、ポリシーを基に企業内のPCの省電力を一括管理することができるのだが、ポリシーに違反しているPCの画面には警告を表示する。警告を受けた場合、画面の「対処」というボタンを1回押すだけで、ポリシー通りの設定に変更されるので、ユーザーはほとんど手を煩わせられることはない。
同じ画面には、前回のPC利用時に消費した電力量・電気代・CO2排出量も表示される。これにより、ユーザーは日々、自分がPCを用いることでどのくらい電力・電気代・CO2を排出したのかを知ることができる。自身の行為が数字として可視化されることは、省エネに取り組むにあたってモチベーションの向上につながると言えよう。
管理者向けのレポートでは、全社・部門単位で、消費電力・電気代・CO2の削減量を把握することができる。加えて、管理者は「省電力の設定が行われていないPC」や「一定時間以上稼働しているPCや夜間に稼働しているPCの数」まで把握することが可能だ。
先に、ユーザーがPCの省電力設定を変更する理由の1つとして、ウイルススキャンを夜間に実行させるためと述べたが、同社が省電力に関する社内調査を行った際も同じ意見が多かったそうだ。こうした意見を反映して、同製品は、指定時間になるとスタンバイ状態を解除してウイルススキャンを実行し、終了後にはスタンバイ/休止状態にする機能を装備しているという。
加えて同氏は、「あえて、ユーザーに対して"管理している"ことを示すことも大事」と語る。これまで、クライアントPCで運用管理関連のソフトウェアを動作させる場合、ユーザーに気付かせないよう、こっそりとエージェンを動かすことが多かったが、そうではなく、「あなたの省電力の状況を監視してますよ」と知らせるべきというわけだ。一種の抑止効果である。
そのほか、同氏はEラーニングを活用して省電力意識の向上を図ることも有効であると説明する。
情報漏洩に関する議論でもよく言われることだが、どれほど堅牢な保護の仕組みを構築したとしても、それを利用するユーザーが穴となっては何の意味もない。まずは、ユーザーがその仕組みの重要性をきちんと理解したうえで、運用していく必要があろう。企業で省電力を推進する際も、省エネとコスト削減の2つの側面から必要であることを、社員に理解してもらうことが大切だと言える。「千里の道も一歩から」ではないが、1台のPCでは微々たる量の電力・電気代・CO2排出量も全社として見れば、相当な量になるはずだ。まずは、自分のPCの省電力設定を見直すことから始めてみてはいかがだろうか。