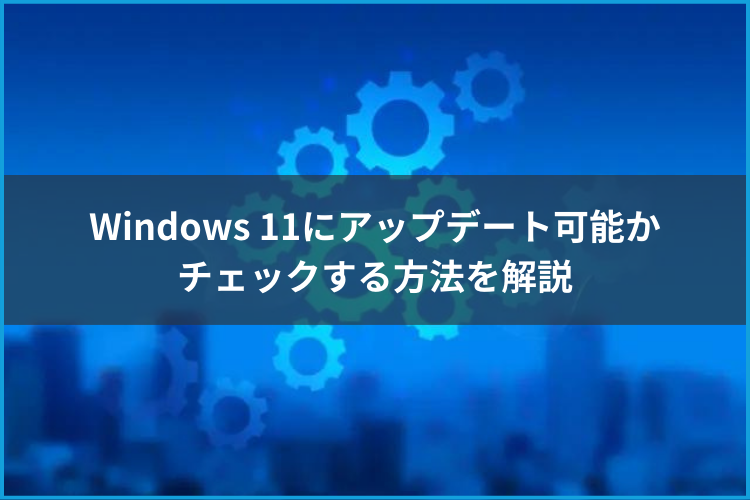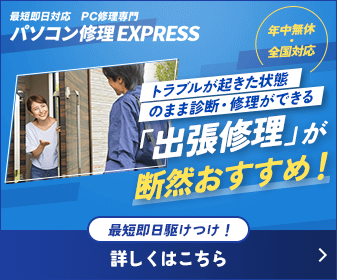避けたほうがいいパソコン修理業者の紹介をする
避けた方が良いパソコン修理業者の特徴は、主に以下のとおりです。
・ホームページがない
・会社名・住所がわからない
・ホームページに料金を明記していない
・修理できない場合や追加料金についての説明がない
・なんの資格も取得してない
・口コミでの評価が悪い
・SNSの投稿の質が悪い
ホームページがない
パソコン修理業者で、今時ホームページを持たない会社はほとんどありません。チラシや口コミで良さそうだと思った会社も、まずはホームページがあるかどうかチェックしてみましょう。
悪徳業者は万が一違法な営業がバレたときのために、ホームページをあえて作らないケースが多いです。
会社名・住所がわからない
運営会社や、その所在地が分からない業者にも依頼しない方が良いでしょう。悪徳業者は違法な営業を摘発されないように、架空の社名を名乗ることがあります。社名を調べ、創業年数や会社規模を知ることで信頼を図ることも可能です。
見積もりをとる前に、まずはどのような会社かチェックしておきましょう。
ホームページに料金を明記していない
悪徳業者は料金を公にせず、あとから高額な費用を請求してくるケースがあります。元々の価格が分からなければ、「話が違う」と食い下がることもできません。
また見積もりの内訳が不透明な業者にも要注意です。内訳をごまかし、料金を水増ししている可能性があります。
修理できない場合や追加料金についての説明がない
修理内容によっては業者側の手に負えない場合や、当初想定していなかった追加作業が必要になる場合もあります。本来、事前にこうした場合の対応については、業者から説明があるはずです。
もし何の説明もない場合は要注意。修理できない場合もキャンセル料を取られたり、高額な追加費用を請求されたりすることがあります。
なんの資格も取得してない
パソコン整備協会の発行する認定資格をはじめ、何の資格も取得していない修理業者は避けた方が良いでしょう。
優良な業者は、プライバシーマークやISMSといった個人情報の取り扱いに関する規格も取得しています。こうした資格がない業者は技術面、セキュリティ面から見ても依頼しない方が良いでしょう。
口コミでの評価が悪い
口コミも大切な判断材料です。たとえば口コミを調べて、こんなことが書いてあったら修理の依頼は避けるべきでしょう。
・見積もりと全く違う金額を請求された
・頼んでもいない修理を勝手にされた
・修理できなかったのにお金を取られた
・出張料がやけに高かった
・スタッフの態度がわるかった など
SNSの投稿の質が悪い
修理業者がSNSをやっている場合、その投稿も見てみると良いでしょう。優良な業者であれば、修理の事例やお役立ち情報などを発信しているはずです。
もし同業他社をおとしめたり、お客を見下したりするような発言がある場合は、依頼を避けるのがベターです。
自分でできる対処法
パソコントラブルのなかには、自分で対処できるものもあります。ここからは自分でもできる簡単な対処法について紹介します。該当する症状がある人は、ぜひ試してから修理を検討してみてください。
電源が入らない
・電源ケーブルがきちんと接続されているか確認する
・充電が足りない可能性があるため、しばらく電源ケーブルをつないだまま様子を見て再度電源を入れる
動作が重い
・不要なアプリケーションやデータを削除する
・外付けハードディスクでメモリ容量を拡大する
・インターネットの履歴など、キャッシュを削除する
・バックグラウンドで実行しているアプリケーションを停止させる
・デスクトップを整理する
・高速スタートアップを有効にする
画面が固まったとき
・しばらく待ってみる
・変化がなければ電源ボタンを長押しし、強制的にシャットダウンさせ、ケーブルも抜いて2分ほど放置。放電させて再度電源を入れ直す。
マウスポインタや打った文字が画面に反映されない
・キーボードやマウスの電池切れではないか確認(ワイヤレスの場合)
・有線の場合はケーブルがきちんと接続されているか確認
・設定画面でデバイスが認識されているか確認
異音がする
・パソコン側面の通風口にほこりがたまっている場合は、クリーニングする
以上が、主に自分で試せる対処法です。パソコンに詳しい人は自分で分解して部品交換をする場合もありますが、あまりおすすめしません。なぜなら専門的な知識のない人がパソコンの内部を扱うと、取り返しのつかない故障になってしまう場合があるからです。
また内部に熱がこもっている場合など、取り扱いが危険なケースもあるのです。無理に自分で修理しようとせず、修理の専門業者に依頼することをおすすめします。














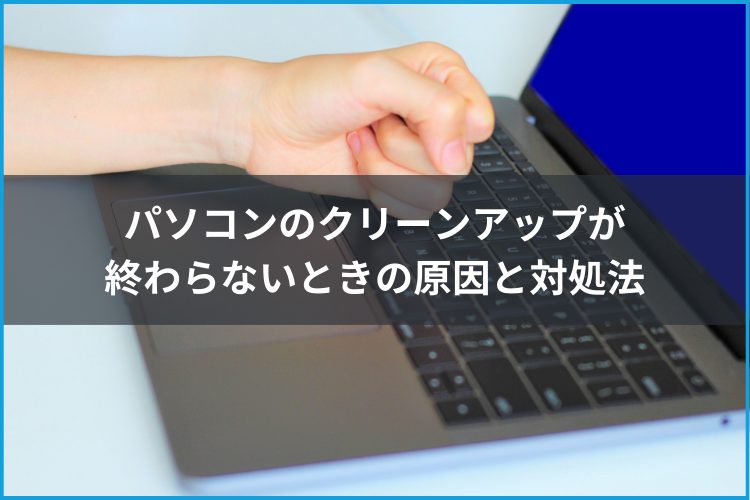

の必ずやっておきたい初期設定.jpg)