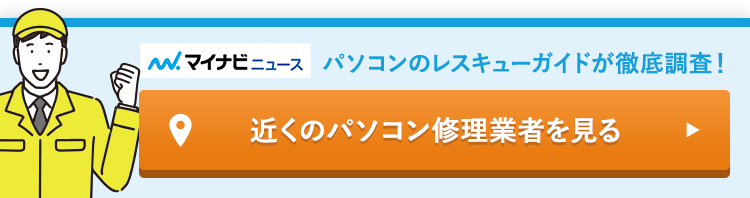パソコンの電源がつかない時の原因
パソコンの電源がつかない時に考えられる原因は、以下5点です。
- 電源周りの故障
- ホコリやゴミ
- バッテリー切れ
- パソコンの帯電
- パソコン内部部品の劣化
電源がつかない原因がわかれば、最適な対処法がわかります。特定が難しい原因もありますが、まずは今回パソコンの電源がつかなくなった原因を確認してみましょう。
電源周りの故障
以下のような電源周りのものが故障していると、パソコンの電源はつきません。
- 電源タップ
- コンセント
- 電源スイッチ
- ケーブル
- OAタップ
- ACアダプター
電源周りの故障・劣化による、接触不良や電力供給の阻害などで電源がつかなくなることがあります。
電源周りの故障が原因か探るときは、電源周りの部品が故障・劣化していないか、そもそもケーブルは繋がっているかを確認しましょう。コンセントやケーブルのように代替できるものであれば、交換してみることで原因の切り分けができます。
ちなみに電源周りだけでなく、USBや外付けハードディスク(HDD)といった周辺機器に不具合がある場合も同様の状況になります。
なお、電源周りのものが故障している場合、パソコン本体の修理・部品の交換が必要です。起動できたらバックアップを取り、メーカーや修理業者へ相談することを検討してください。
ホコリやゴミ
ホコリやゴミなどが原因で、パソコンの電源がつかないことも多くあります。
パソコンの内部には、パソコンの熱を外に逃がすための冷却ファンが内蔵されており、長期間使用しているとホコリやゴミ溜まってしまいます。
パソコン内部にホコリやゴミが溜まると冷却できず、熱がこもったり静電気を発生したりして電源がつかなくなることがあります。
また最悪の場合、トラッキング現象が発生します。トラッキング現象とは、コンセントとプラグの間に溜まったホコリやゴミが空気中の湿気を吸収し、漏電・発火することです。
空気中に湿気が多い時期や、配線が密集していると発生しやすくなります。トラッキング現象が起きると冷却ファンが稼働しますが、熱を冷やせなければ故障します。
そもそもホコリやゴミを溜めないためには、頻繁にパソコンや冷却ファンを掃除することが大切です。
なお、ホコリやゴミが溜まっていなくても、パソコン内部に熱がこもると同じような状況になります。
パソコンを使用する際の適切な室温は、一般的に10〜35度です。室温が10度以下や35度以上の場合は、エアコンや暖房などで調節するとよいでしょう。
バッテリー切れ
主にノートパソコンの話になりますが、パソコンが起動しない原因としてバッテリー切れも挙げられます。
ノートパソコンはバッテリーが劣化していたり、充電不足だったりすると電源がつかなくなります。バッテリーは2〜5年程度で劣化する消耗品です。劣化が進むと充電ができなくなったり、パソコンを起動できなくなったりします。使用頻度や使い方によって劣化のスピードは異なります。
なお、バッテリーが膨らんでいる場合は、劣化や故障が疑われます。内部でガスが発生している恐れがあるので、すぐに使用をやめて新しいものに交換してください。
パソコンの帯電
パソコンが帯電していると、電源はつきません。帯電とは、パソコンの内部に不要な電気が溜まり、静電気を帯びている状態です。以下のような使い方をしていると、パソコンが帯電しやすくなります。
- 電源ケーブルを挿しっぱなし
- 充電しっぱなし
- 接続している周辺機器が多い
- パソコンの長時間使用
帯電すると過剰な電気が流れて制御不能になり、電源に関する動きが不安定になるので電源がつきません。
なお、帯電した状態で電源がついても、画面のフリーズ・ノイズの発生・周辺機器の操作不良・画面映りの悪化・動作の遅れ発生などのトラブルが生じやすくなります。
最悪の場合、データが消失する恐れがあるので、日頃から帯電しないように気をつけましょう。
パソコン内部部品の劣化
パソコンの電源がつかない場合、以下のようなパソコン内部の部品が劣化していることも考えられます。
- マザーボード(システムの中心となるメイン基盤)
- CPU(周辺機器やソフトウェアからの指示の処理やメモリ制御を行う装置)
- ビデオメモリ(映像の出力に特化したGPUに搭載されているメモリ)
- 出力装置(ディスプレイやグラフィックカードなど、コンピュータの情報を人が認識できるように出力する訴追)
- BIOS(起動プログラム)
- OS(Windows・macOSなどパソコンの操作に必要なソフトウェア)
- HDD/SSD(データを記録する装置)
起動時に「ピー」「ピピッ」というビープ音が鳴った場合はマザーボード、画面が表示されないケースはビデオメモリの故障・劣化が疑われます。
またOSが破損しているときは、青い背景に白い文字でエラーコードが生じるブルースクリーンが表示されることが一般的です。HDD/SSDの物理的な破損では、パソコンを落としてから起動しなくなったり異音がしたりします。
内部部品の劣化は、自分で原因を特定しきれないかもしれません。自力では対応できないと感じたら、すぐにメーカーや修理業者へ問い合わせてください。
\最短即日で駆けつけ対応可能!おすすめ業者もご紹介!/
お住まいのエリアからパソコン修理業者を探すパソコンの電源がつかない時の対処法
パソコンの電源がつかないときの対処法は、デスクトップパソコンとノートパソコンで異なります。パソコンの種類ごとに対処法を紹介するので、自分が保有しているパソコンの種類に応じた対処法を実践してみてください。
デスクトップパソコンの場合
デスクトップパソコンの場合、以下2つの対処法が有効です。
- コンセントを抜き、放電を行う
- ホコリやゴミを掃除する
現在デスクトップパソコンの電源がつかず困っている人は、ぜひ実践してみてください。対処法を試しても効果がない場合は自力で対応しようとせず、メーカーや修理業者へ相談しましょう。
コンセントを抜き、放電を行う
デスクトップパソコンの電源がつかないときは、まずコンセントを抜いて放電しましょう。帯電が原因の場合、放電することで電源に関係する動作が制御できるようになり安定化します。
放電するときは、自分自身の体内にある静電気を取り除いてから作業してください。静電気の除去方法は、電気を通す金属製品などを触るだけです。
基本的な放電の手順を紹介します。メーカーや機種によっても若干手順が異なる場合がありますので、メーカーサイトなどで調べておくと安心です。
- パソコンの電源を落とす
- パソコンに接続している周辺機器・ケーブルなどをすべて取り外す
- 電源ボタンやリセットボタンを5〜6回程度押す
- 30分〜1時間程度、放置する
- 電源ケーブルを接続する
- 電源ボタンを押して起動する
しっかり放電するためにも、周辺機器を取り外すときは、何もパソコンに接続されていないようにしてください。
なお、電源ケーブル以外のケーブル・周辺機器は、放電後すぐに接続しないでください。パソコンが正常に起動できたことを確認してから、接続するようにしましょう。
また放電後はパソコンの日付・時刻の設定が初期化されることがあるので、覚えておいてください。
ホコリやゴミを掃除する
ホコリやゴミを掃除すれば、パソコンの内部温度を下げられるので電源がつくようになります。ファンの稼働音が大きい場合や、パソコンの内部に熱がこもっているケースでは特に効果的です。
掃除するときは、エアダスターやクロスなどを活用しましょう。デスクトップパソコンで掃除が溜まりやすい部分は、パソコンの内部やキーボード、ケーブル・USBの差込口などです。
パソコンの内部を掃除するときは、本体のカバーを外したほうがスムーズです。エアダスターやブロワーを使えば空気の噴射でホコリ・ゴミを除去できるので、基盤などを触らずに済みます。静電気対策用手袋を使うと、よりリスクを抑えられます。
パソコンは精密機器であり、基盤などに触れるとデータが消失するリスクがあるので気をつけましょう。
なお、パソコンのファン周りや内部を掃除する際は、必ず電源を切りましょう。電源コードも抜いて、数分程度放置してから本体カバーを開けてください。
またメーカーや機種によっては、パソコン本体のカバーを外すと「分解」扱いになることがあります。分解すると保証が効かなくなるので、事前に保証適応外になるケースを確認しておきましょう。
本体のカバーを外せないパソコンや、掃除スキルに自信がない人は、内部の掃除を業者に任せることもおすすめです。
ノートパソコンの場合
ノートパソコンの場合は、以下3つの対処法が効果的です。
- バッテリーの充電
- バッテリーを取り外し、放電する
- 周辺機器の取り外し
ノートパソコンは持ち運べる利便性の高さがある一方で、電源がつかない原因になる部品が数多くあります。冷静に、1つずつ対処法を試してみてください。
バッテリーの充電
ノートパソコンで電源がつかない場合、まずはバッテリーを充電してみてください。バッテリー切れが原因であれば、バッテリーを充電するだけで問題を解消できます。
バッテリーを充電する方法は、パソコンにACアダプタを接続し、ACアダプタをコンセントに接続するだけと簡単です。少量の充電を繰り返すとバッテリー残量が消耗するリスクがあるので、できる限り毎回フル充電をするようにしましょう。
バッテリーがフル充電するまでの時間は製品によって異なるため、カタログや説明書を確認してください。一般的には、2〜3時間でフル充電が完了します。バッテリーが充電されなければ故障しているので、新しいものに交換してください。
なお、バッテリーを使い切ってから充電するよりも、使い切るまでに充電したほうが劣化を抑えられるといわれています。バッテリーを長持ちさせるためには、頻繁に充電したり充電しながら使用したりすることは避けたほうがよいでしょう。
バッテリーを取り外し、放電する
ノートパソコンの場合はバッテリーを取り外し、放電したら電源がつくこともあります。
デスクトップパソコン同様に、帯電が原因であれば放電をすることでトラブルが解消します。放電する際は、金属などを触って体内の静電を取り除いてから作業を始めてください。
以下の方法を試せば、パソコンの電源がつかない原因の確認も放電も可能です。
- パソコンの電源を切る
- 電源ケーブルを抜く
- バッテリーを取り外せる場合は外す
- 周辺機器を取り外す
- 電源ボタンを5〜6回押す
- 30分〜1時間程度放置したら、電源ケーブルを接続して再起動する
- パソコンが正常に起動したら、電源を落とす
- バッテリーを接続する
問題なくパソコンが起動したら、原因が帯電だったと考えられます。対処も完了するので、元の仕事や作業に戻って問題ありません。
なお、バッテリーを取り外せない場合は、以下の手順でCMOSクリアを行ってください。
- 周辺機器・ケーブルをすべて取り外す
- パソコンのサイドパネルを外し、マザーボードにあるボタン電池をチェックする
- ボタン電池を取り外す
- 1分以上待つ
- ボタン電池を設置する
- サイドパネルや電源コードを再び取り付ける
- パソコンを起動する
- 日付や時刻を再設定する
- 正常に起動したら完了
ボタン電池がカバーや配線と一体型の場合は、自力で行えません。またマザーボードは慎重に扱う必要があるので、パソコンの知識や取り扱い技術が心配な人は自力で行わず、業者に頼みましょう。
周辺機器の取り外し
以下のような周辺機器を取り外すだけで、電源がつくようになる可能性があります。
- 外付けHDD/SSD
- プリンター
- スキャナー
- USBメモリ
- 光学ドライブ
- microSDカード
複数の周辺機器を接続していると電力を使いすぎて、起動するための電力が足りなくなって不具合が起こることも珍しくありません。特にタコ足配線をしているケースは、周辺機器を取り外してパソコンのケーブルだけを差し直して起動するだけで解決することもあります。
外付けHDD/SSD・USBメモリ・microSDカードを取り外す際は、データ消失を防ぐためにも正しい手順で実施してください。
電力の不安定さを解消するためには、壁のコンセント口に直接ノートパソコンのケーブルを接続することもおすすめです。
なお、周辺機器を接続しなければ起動できる場合、取り外した周辺機器に問題があることも考えられます。1つずつ接続して、どの周辺機器に問題があるか確認しておくと、今後困らずに済むでしょう。
パソコンがつかない場合は修理業者へ
パソコンの電源がつかない場合、電源周りの故障や、ホコリ・ゴミの蓄積、バッテリー切れ、帯電、内部部品の劣化が考えられます。原因の特定は難しいですが、熱がこもってたり異音がしたりする場合は原因を把握できる可能性があります。自分のパソコンの電源がつかない原因をいくつか想定してみてください。
その上で、パソコンの種類ごとに適した対処法を実施することが大切です。デスクトップパソコン・ノートパソコンのいずれも、放電を試してみましょう。デスクトップパソコンはホコリやゴミの掃除も効果的です。ノートパソコンはバッテリーの充電や、周辺機器の取り外しを行うだけで解決することもあります。
ただし、解決しない場合やパソコンの取り扱いに不慣れな人は、パソコン修理業者へ依頼してください。修理業者ならスムーズに問題を解決してくれます。またデータ消失のリスクも抑えられるでしょう。
パソコン修理業者を選ぶときは、できる限り資格を持っており、データをバックアップ・保護してくれるかどうかをチェックすると安心です。
あなたにおすすめの記事


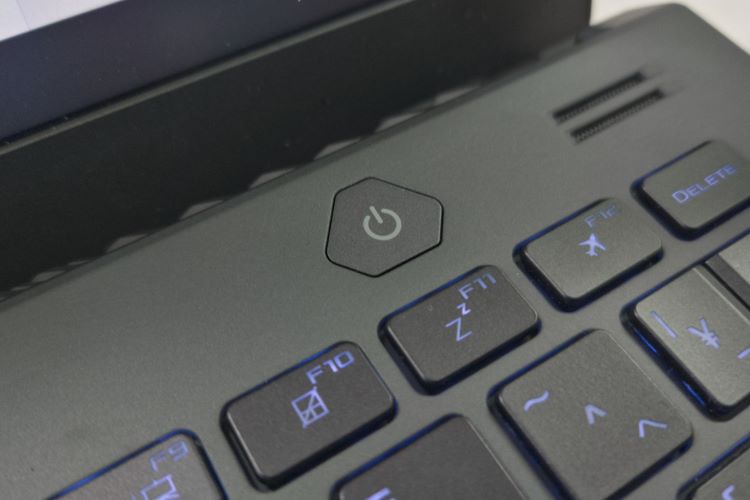
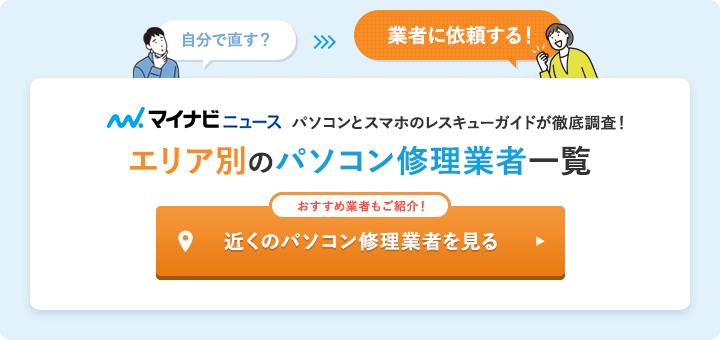
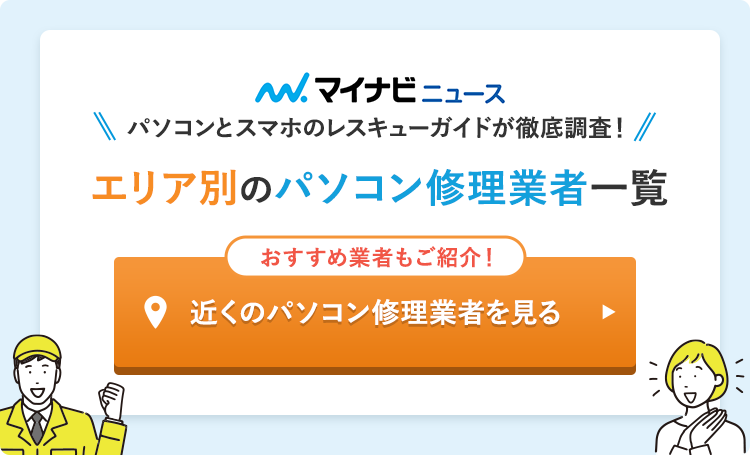

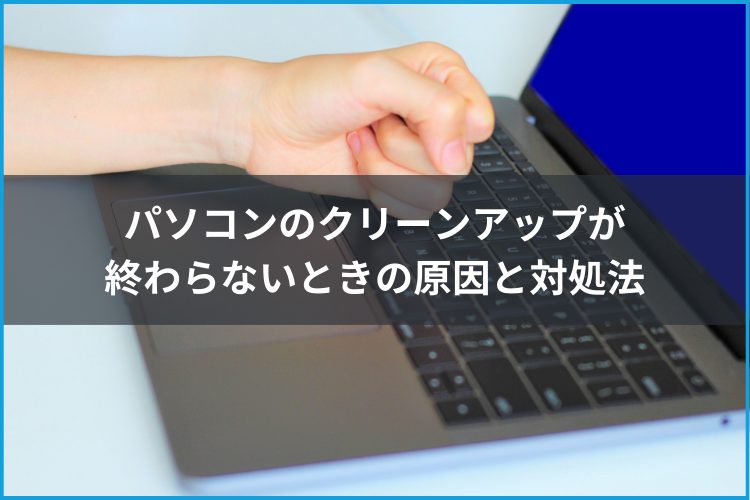
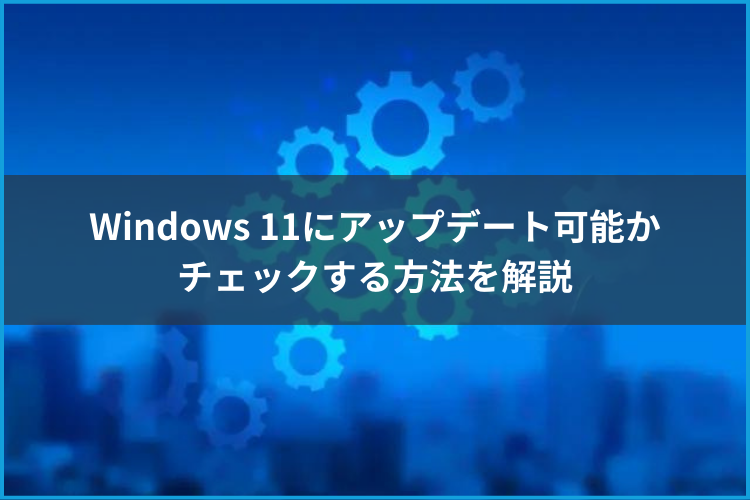
の必ずやっておきたい初期設定.jpg)