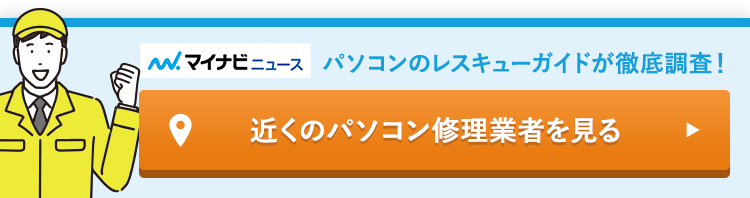パソコン購入後の標準設定から、文字サイズやデスクトップの画像などをもっと自分好みに変えたいなどと思ったことはありませんか?
デスクトップ画像はもちろんのこと、文字サイズやマウスポインターの移動速度の速さなど、意外とパソコンの設定でカスタマイズできることは多くあります。
今回は「画面表示」に関するパソコンの便利な設定やお困りごとの解決方法などをご紹介していきます。
パソコンの基本設定
画面の文字が小さくて見づらい
どの画面でも文字が小さく見えるなら、標準の文字サイズを変更するとよいでしょう。
以下の手順で文字サイズの変更ができます。
- まず「設定」アプリを開く
- 「システム」の中の「ディスプレイ」を選択
- 「拡大縮小とレイアウト」の中の「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」の倍率を調整する
現在が「100%」なら「150%」や「200%」にするなど、現在より大きな数値に変更しましょう。
数字は表示倍率で、ディスプレイの物理的な大きさ(インチ)と解像度(画面内の点の数)の組み合わせによって、「(推奨)」と書かれている標準の倍率設定や、設定可能な最大の倍率は異なります。
推奨の倍率より大きく設定した場合、文字は見やすくなりますが、一部のアプリで表示が画面内に収まらず、正しく操作できなくなることもありますのでご注意ください。
WordやExcelでは、画面右下のスライダーを動かすと作業画面の表示倍率が変わります。
「表示」などのメニューで作業画面の表示を拡大できるアプリもあり、Webページもまた拡大表示をWebブラウザーの「設定」の項目から行うことができます。
画面の明るさを変えたい
画面内での操作で明るさを変更できるパソコンであれば、タスクバーの右端にある「吹き出し」のアイコンをクリックしてアクションセンターを開いて、下部のタイルを「展開」した状態で、一番下に出るスライダーを動かすと明るさの調整ができます。
このスライダーは右に動かすと明るく、左に動かすと暗くなるので、好みの明るさに調整してください。
また、設定アプリの「システム」にある「ディスプレイ」でも、画面のスライダーを動かして明るさの調整が可能です。
パソコンの機種によっては、本体に明るさを変更するボタンがあったり、キーボードに明るさを調整するキーが用意されていたりする場合もあります。
画面がすぐに消える
パソコンを一定時間操作しないと省電力機能が働き、画面が暗くなってしまいます。
自動的に画面の表示をオフにしたり、バソコンをスリープ状態に切り替えたりしているのです。
画面が暗くなるのが早すぎるようであれば、省電力機能が働くまでの時間を延ばしましょう。
「設定」アプリの「システム」にある「電源とスリープ」を開き、「画面」の時間設定を変えることで間隔を操作することができます。
ただし、下の「スリープ」より長い時間は設定できないため、必要に応じて「ディスプレイの電源を切る」「PCをスリープ状態にする」の両方の時間を調整してください。
時間によって画面が暗くなる機能自体を無効にしたいのであれば、選択項目から「なし」を選びます。
ノートパソコンでは「バッテリー駆動時」と「電源に接続時」の2種類が設定できます。
古いWindowsでは、パソコンを一定時間利用しないと自動で画面に写真や模様などを表示する「スクリーンセーバー」という機能がよく使われており、これはWindows 10も同様になります。
「設定」アプリ→「個人用設定」→「ロック画面」の画面の下のほうにある「スクリーンセーバー設定」を選択すると、設定画面が表示されますので種類や待ち時間などを自由に変えてみましょう。
なお、スクリーンセーバーの設定より、ディスプレイの電源を切る設定のほうが優先されますのでご注意ください。
不要な通知を表示しないようにする
Windows標準の仕組みで表示される通知は、「設定」アプリの「システム」→「通知とアクション」で調整できます。
「アプリやその他の送信者からの通知を取得する」を「オフ」にすれば、大部分の通知が表示されなくなります。
ただし、Windowsからの重要な通知や、アプリが独自の方法で表示する通知には影響しません。
アプリごとの通知の設定は、同じ画面の下にある「送信元ごとの通知の受信設定」で調整します。
ここには、Windowsの仕組みで通知を表示するアプリが並んでおり、個別に通知を無効化できます。
また、アプリを選ぶと、細かな設定画面が出ます。
アプリごとの設定では、通知を有効にするかどうかに加えて、右下のタイル(通知バナー)を表示するかどうか対処しなかった場合に「アクションセンター」で表示するかどうか、アクションセンターで表示する数や優先度などの項目を設定できます。
一部の設定は通知のタイルやアクションセンターでも行えるほか「集中モード」をオンにすると、ほとんどの通知表示が止めることができます。
\最短即日で駆けつけ対応可能!おすすめ業者もご紹介!/
お住まいのエリアからパソコン修理業者を探すマウスポインター関連
画面上の矢印(ポインター)を大きくしたい
「設定」アプリの「簡単操作」→「マウスボインター」の画面で、ポインターのサイズや色といった「見た目」を調整できます。
「ポインターのサイズと色を変更する」のスライダーのつまみを動かすと、ポインターの大きさが変わります。
標準では最小になっていて、つまみを右に動かすか、スライダー上をクリックすると、ポインターのサイズが大きくなりますので好みの大きさに変更しましょう。
また、「マウスポインター」の画面では、ポインターの色も変更可能です。
標準では、黒枠付きの白色ですが、白枠付きの黒色、反転色(背後の色に合わせて反転)、指定色のいずれかが選べます。
画面の矢印 (ポインター)の動きが速すぎる
「設定」アプリの「デバイス」を開き、「マウス」と「タッチパッド」のうち、自分が使っているほうを選択します。
開いた画面に「カーソルの速度を変更する」というスライダーがあるので、つまみを左右に動かして速度を調整してください。
なお、「タッチパッド」の項目が存在しない場合は、「マウス」の画面で調整してみましょう。
タッチパッドの設定にメーカー独自の画面を使うパソコンもあります。
その場合は、画面右下の通知領域にタッチパッドのアイコンがあって、クリックするとメニューを呼び出せることが多いようです。
デスクトップ関連
デスクトップの背景や画面全体の色合いを変えたい
デスクトップの背景は、「設定」アプリ→「個人用設定」→「背景」で変更できます。
また、自分が撮影した写真を背景にしたい場合は、エクスプローラーの画面でその写真のファイルを右クリック→デスクトップの背景として設定」を選ぶのが簡単です。
一方、画面全体の色合いは「設定」アプリ→「個人用設定」→「色」で調整します。
画面下部のタスクバーやスタートメニューの色を明るくしたり、アプリのウインドウを暗くしたりする共通設定の項目があり、雰囲気を大きく変更できます。
「色を選択する」を「ライト」にすると全体的に明るく、「ダーク」にすると暗く設定されます。
「カスタム」を選ぶと、「既定のWindowsモードを選択してください」の項目でスタートメニューやタスクバーなどの配色を、「既定のアプリモードを選択します」の項目でアプリの画面配色を、個別に「ライト」または「ダーク」に設定できます。
なお、Windows 10では「色」の初期設定は「ライト」ですが、利用状況やパソコンメーカーの設定などによって異なる場合があります。
消えたごみ箱を再表示させる
意図せずごみ箱のアイコンを消してしまった場合は、デスクトップ画面に再表示させましょう。
デスクトップの背景部分のどこかを右クリックして、表示されるメニューの「表示」を選ぶとさらにメニュー表示されます。
そこに「デスクトップアイコンの表示」という項目があるのでクリックしましょう。
すると、右のメニューの項目の頭にチェックが付き、デスクトップにアイコンが表示されるはずです。
他のアイコンが表示されているのに「ごみ箱」だけが表示されていない場合は、「設定」アプリの「個人用設定」→「テーマ」から「デスクトップアイコンの設定」を選んで設定画面を呼び出し、ごみ箱が非表示になっていないか確認してみてください。
デスクトップに「PC」のアイコンを表示
まずはデスクトップの背景を右クリックし「デスクトップアイコンの表示」が有効な状態になっていることを確認しましょう。
有効であることが確認出来たら「設定」アプリの「個人用設定」→「テーマ」→「デスクトップアイコンの設定」を選ぶと、デスクトップに表示するアイコンを選ぶ画面が表示されます。
ここで「コンピューター」にチェックマークを付け適用ボタンをクリックすれば、デスクトップに「PC」のアイコンが表示されます。
また、この画面内のアイコンを選んで「アイコンの変更」を選ぶと、そのアイコンの外観が変更可能です。
「既定値に戻す」では、元のアイコンに戻すことができます。
アイコンを自由に配置する
アイコンが重なって見つからなくなるのを防ぐ機能として「アイコンの自動整列」という機能があります。
この機能を使用するとアイコンが自動的に並ぶようになってしまい、好きな場所にアイコンを置くことができません。
デスクトップ上のアイコンなら、デスクトップ上の何もない部分を、特定のフォルダー内ならそのフォルダーを開いて、フォルダー内の余白部分を右クリックし、「表示」→「アイコンの自動整列」をクリックしてチェックを外すと、設定を無効にできます。
また、アイコンの位置を少しだけ動かして微調整しようとしても元の位置や別の場所に動いてしまうという場合は、同じメニュー内の「アイコンを等間隔に整列」が有効になっています。
煩わしいようであれば同じように無効にするとよいでしょう。
デスクトップのアイコンを自動で整列させたい
「アイコンの自動整列」を有効にすると、デスクトップ上のアイコンが自動的に整列するようになります。
この機能を有効にすると、アイコンは強制的に左上から縦方向に並びます。
単に、アイコンを等間隔にきれいに並べたいのであれば、同じメニュー内の「アイコンを等間隔に整列」を有効にすると、動かしたアイコンの位置が、自動で縦横まっすぐに並びますので便利です。
アイコンの順番は手作業でも並べ替えることができますが、デスクトップ上の何もない部分を右クリックして表示されるメニューで「並べ替え」を選ぶと「名前」や「更新日時」などを基準に一気に並べ替えが可能です。
デスクトップのアイコンが小さい
アイコンサイズを変更したいときは、デスクトップの背景部分を右クリックして表示されるメニューから「表示」を選択し、「大アイコン」「中アイコン」「小アイコン」の3項目から選びましょう。
「大アイコン」を選べばアイコンが大きくなりますが、大アイコンにしても小さく感じる場合はWindowsの表示全体を拡大する必要があります。
デスクトップのアイコンを上手に整列させたい場合は、「アイコンの自動整列」や「アイコンを等間隔に整列」にチェックを付けます。
フォルダー内のアイコンの大きさは、エクスプローラーの画面で「表示」のリボンから変更しましょう。
\最短即日で駆けつけ対応可能!おすすめ業者もご紹介!/
お住まいのエリアからパソコン修理業者を探すまとめ
今回の記事ではパソコンの画面設定の方法について解説しました。パソコンの画面表示の設定はパソコンの使いやすさに直結している要素です。ぜひ今回の記事を参考に自分好みの設定にカスタマイズしてみてはいかがでしょうか。
あなたにおすすめの記事



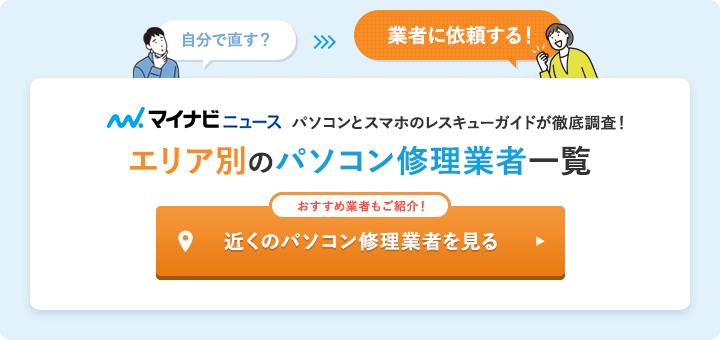
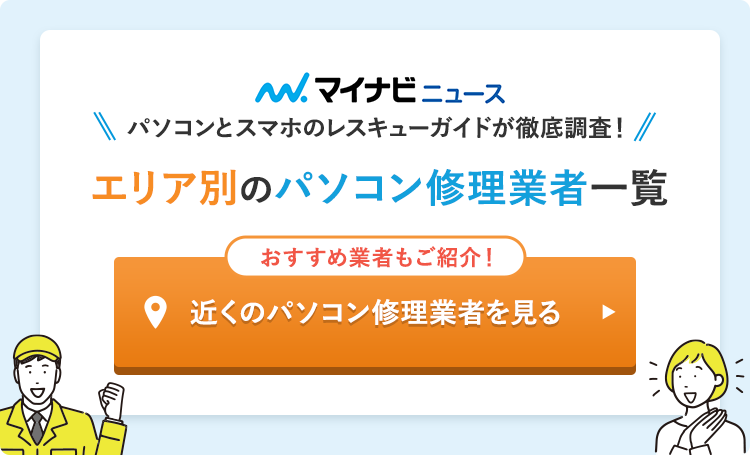

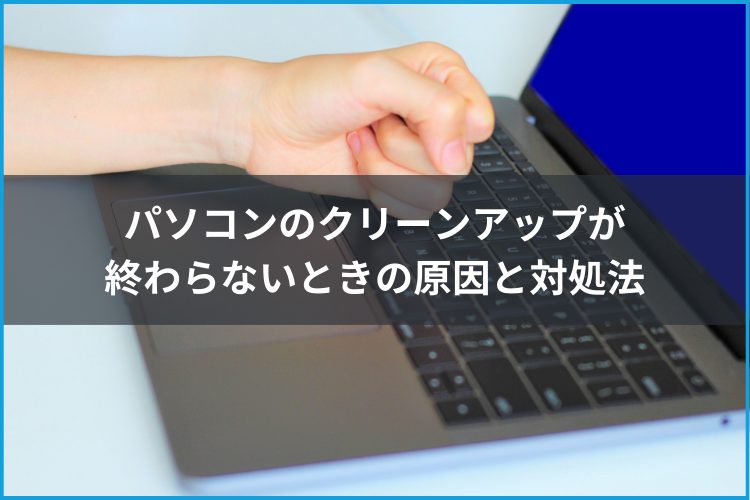
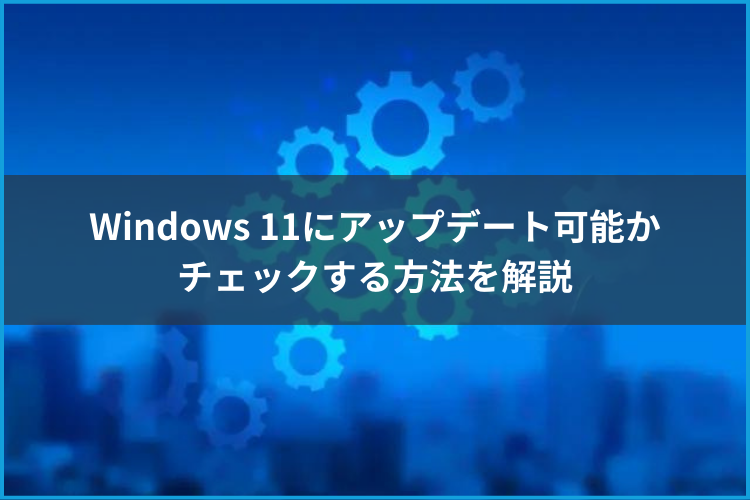
の必ずやっておきたい初期設定.jpg)