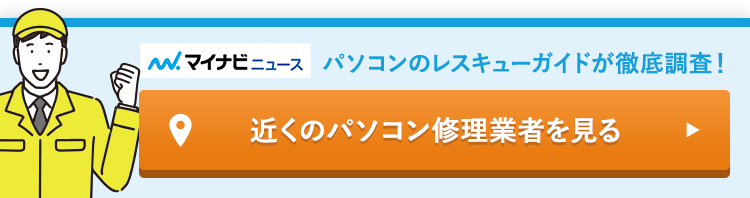パソコンの画面がつかない時にまず確認するべきこと
まず、「パソコンの画面がつかない」とはどういう状態なのかを、落ち着いて確認してみましょう。
一概に「パソコンの画面がつかない」と言っても、原因はさまざまです。
- 電源ボタンを押しても電源ランプが点灯しない
- メーカーロゴは表示されるけど、その後真っ暗になってしまう
- Windowsの起動音は聞こえたけど、画面は何も映らないまま
上記は一例ですが、これらは全て故障の原因が異なります。原因に対して的確な作業ができれば、パソコンの知識がなくても、修理を依頼しなくても、自分で解決できるかもしれません。
また、不具合の状態を把握することで修理を依頼すべきかどうかの判断ができるので、自分のパソコンがどのような状態になっているのか、正確に把握しておきましょう。
確認すべきこととしては次の4つです。
- 電源ケーブルやコンセントは問題ないか
- 省電力モードになっていないか
- ノートパソコンの場合外部ディスプレイ出力になっていないか
- モニターの故障ではないか
それぞれ解説していきます。
電源ケーブルやコンセントの確認
「そんなところなんか大丈夫に決まっているじゃないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、意外と電源ケーブルやコンセント側の不具合は多いのが実情です。特に、ノートパソコンを使用している人は、持ち運びのために電源ケーブルを頻繁にまとめること、使用時の取り回しによって知らず知らずのうちにコネクタ部分に負担がかかる使い方をしていることがあります。
電源ケーブル内部で断線が起きているとバッテリーに充電が行われなくなり、バッテリーの残量切れによって電源は入ってもすぐにスリープやシャットダウンに入ってしまう、ということになりかねません。
デスクトップPCを使っている人でも、本体や付近の家具などを移動したときに、電源ケーブルを引っかけていて本体側のコネクタが半分抜けてしまっていたり、電源タップを使用したりする場合は、電源タップ側の故障により、差込口の通電が不安定になっていることがあります。
まずは、壁のコンセントから直接電源ケーブルを繋ぎ、各コネクタの挿しなおしを行ってみましょう。


省電力モードになっていないか
省電力モードに入っていると、一定時間が経過したときにディスプレイの電源が切れたり、スリープに入ったりすることがあります。
バッテリー駆動になっているノートパソコンでは、バッテリー残量が少なくなると自動的に省電力モードに切り替わり、そのままスリープに入ってしまうことも考えられます。
ディスプレイの電源が切れているだけなら、マウスやキーボードを操作して復旧することが可能です。それでも画面がつかない、かつ、電源ランプがゆっくり点滅している場合は、スリープに入っている可能性があるので、もう一度電源ボタンを押してみましょう。
ノートパソコンの場合外部ディスプレイ出力になっていないか
前回ノートパソコンを使ったときに外部ディスプレイ出力にしたままの状態になっている場合、うっかり外部出力のショートカットを押してしまっている場合があるかもしれません。また、中途半端に外部出力ケーブルが接続された状態で出力切替の動作が不安定になり、正常に画面が切り替わっていない可能性もあります。
外部出力ケーブルを取り外しWindowsキー+Pキーを押して、外部ディスプレイ出力の切り替えメニューが表示されるかどうかを確認してみましょう。
モニターの故障ではないか
電源ランプが点灯していて、起動音や駆動音が聞こえている場合は、モニター(接続ケーブルを含む)の故障も考えられます。モニター自体が完全に故障していると、パソコンの操作は出来ても画面に何も表示されません。
モニターのバックライト部分だけが故障している場合は、一見画面が真っ暗のように見えますが、液晶をよく見るとうっすら画面に何か表示されているのが確認できます。
本当に画面に何も表示されていないかどうか確認してみましょう。
デスクトップパソコンの場合はほかのモニターや接続ケーブルで試してみましょう。またノートパソコンも本体のディスプレイの故障やソフトウェアが原因の場合もあります。
もし外部ディスプレイを持っていたら、表示されるか確認しましょう。
\最短即日で駆けつけ対応可能!おすすめ業者もご紹介!/
お住まいのエリアからパソコン修理業者を探すパソコンの画面がつかないときの対処法
それでもパソコンの画面がつかないときにはどうしたらいいのか、対処法としては次の6つです。
- 周辺機器を外す
- ノートパソコンの場合はバッテリーを外してみる
- 増設機器があれば外してみる
- パソコンの放電を行う
- セーフモードで起動する
- BIOSが起動していない場合
一つずつ詳しく解説していきます。
周辺機器を取り外す
周辺機器を接続した状態だと周辺機器にも電力を使ってしまっているせいで本体に必要な電力が足りなくなり、画面に何も表示されなくなってしまっている可能性があります。
ノートパソコンで、USBマウス、イヤホン、LANケーブル、スマートフォンなどの接続ケーブル、USBフラッシュメモリなどの外部ストレージを本体に接続している場合は、一旦全て取り外してみましょう。
デスクトップPCでは、最低限キーボードかマウスがないと操作ができないので、どちらかひとつを残して、他の接続している周辺機器を取り外してみましょう。
ノートパソコンの場合はバッテリーを外してみる
ノートパソコンで、劣化したバッテリーや残量が極端に少なくなったバッテリーを使用していると、本体への電源供給が不安定になることがあります。このような電源供給の不安定性をなくすため、バッテリーを外してACアダプターからの電源供給のみで起動してみましょう。
増設機器があれば外してみる
ノートパソコンにメモリの増設を行った場合は、その取り付けた増設メモリを外してみましょう。メモリの取り付け方に問題があり、画面がつかなくなることはよくあります。
また、ハードディスク(HDD)やSSDの換装を行っている場合は、同様に取り外すか、純正品に戻してみましょう。
デスクトップPCでは、増設メモリの他にグラフィックボードなどを増設していれば、同様に取り外し、マザーボードに搭載されているHDMIやDVIなどの映像出力端子を使って確認してみましょう。
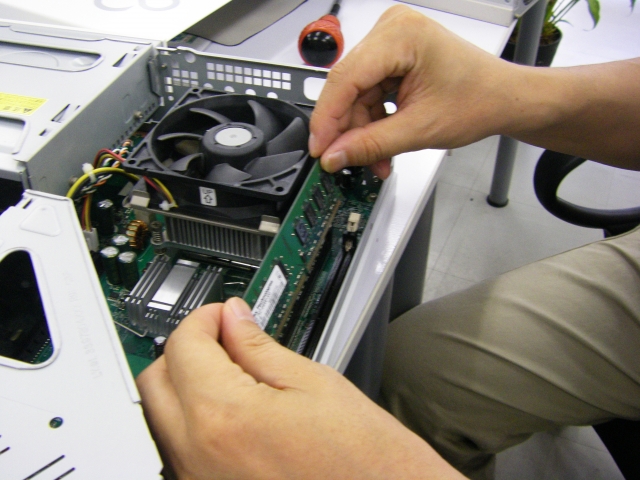
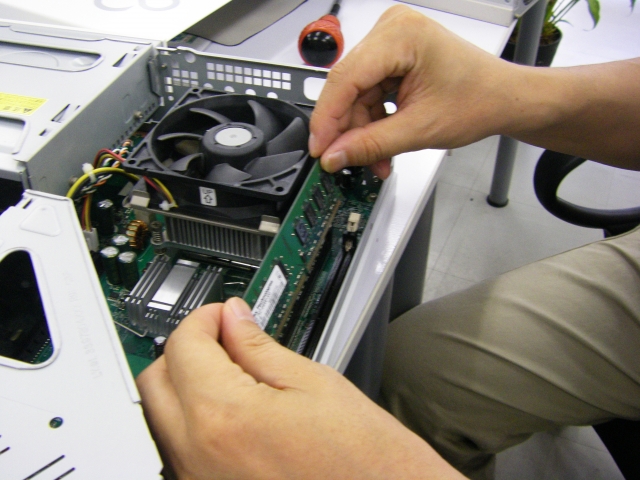
パソコンの放電を行う
一時的な静電気の帯電により、パソコンの起動時に不具合を起こすことがまれにあります。
そのような場合は、パソコン本体から電源ケーブルを抜き(ノートパソコンの場合はバッテリーも外す)、放電させてみましょう。
セーフモードで起動する
電源ボタンを押してメーカーロゴが表示された後に画面がつかなくなる場合、セーフモードで起動できる可能性があります。
もし、周辺機器や増設機器を外した状態でセーフモードの起動ができたら、周辺機器のデバイスドライバーや、常駐プログラムが不具合を引き起こしているかもしれません。
セーフモードの起動方法
Windows 7の場合は、F8キーを連打しながら電源ボタンを押すと、詳細ブートオプションが表示され、「↓」キーを押して「セーフモード」を選択すると起動できます。Windows 8以降は、高速シャットダウン方式を採用しているため、F8キーを連打する方法が使えなくなりました。
セーフモード自体は、Windowsが起動しなくても、「オプションの選択」画面内からアクセスすることができますが、「オプションの選択」画面のアクセス手順はメーカーによってさまざまです。
例1:東芝製ノートパソコンの場合
電源ボタンを押す前に「0(ゼロ)」キーを押し、その状態のまま電源ボタンを押すと、ハードディスクリカバリモードに入り、「オプションの選択」画面から「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→「スタートアップ設定」→「再起動」→「セーフモードを有効にする」の順に選択すると、セーフモードで起動することができます。ノートパソコンの場合は、メーカー側で「オプションの選択」画面までのアクセス手順が独自に設定されていることがほとんどなので、まずはメーカー推奨のアクセス手順を確認しましょう。
例2:Dell製デスクトップPCの場合
電源ボタンを押してDellのロゴが表示されている時に、電源ボタンを長押しして強制的に電源を落とし、これを2回繰り返します。
次に電源を入れると、自動的に「オプションの選択」画面が表示されるので、「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→「スタートアップ設定」→「再起動」→「セーフモードを有効にする」の順に選択すると、セーフモードで起動することができます。
強制的に電源を落とす方法は、日本マイクロソフト株式会社が正式に公開している方法で、Windows 8以降がインストールされた全てのパソコンで行えますが、機械的ダメージを与えかねませんので、メーカー推奨のアクセス手順がない場合の最終手段として行ってください。
BIOSが起動していない場合
ここまでの対処法を試してみても画面が表示されなければBIOSが起動していない可能性があります。
BIOSとはパソコンの電源が入って一番初めに起動するプログラムのことで、主にマウスやキーボード、CPUなどのハードウェアを制御してくれるシステムのことです。
最もよくあるパターンは、このBIOSが動く際に必要なCMOSバックアップ電池が劣化し、起動の際に情報を読み込めなくなるケースです。
CMOS電池には「CR2032」が使われていることが多く、デスクトップ用の場合マザーボードに取り付けられているので比較的簡単に交換が可能です。
また、ノートパソコンの場合も裏面のカバーを開けることで交換することができます。(製品によってはできない場合もあります)
しかしながらCMOS電池がマザーボードに直接はんだ付けされている場合や、ボタン電池でなくパッケージされたボタン電池の場合も一般には販売されていないため、交換することは不可能です。
これらの場合、自身で解決することは難しいでしょう。
そうでなくても、交換にはパソコンの内部を触る必要があったり、分解する必要があったりするためリスクが伴います。
パソコンの知識に不安がある方は初めからメーカーや専門の業者に依頼することをおすすめします。
\最短即日で駆けつけ対応可能!おすすめ業者もご紹介!/
お住まいのエリアからパソコン修理業者を探すそれでも解決しない場合
上記の方法でも解決しない場合は、パソコンの部品が故障してしまっている可能性が考えられますので、修理業者に修理を依頼するか、新しいパソコンの購入をおすすめします。
ご家庭で分解修理を行うことは、事故や怪我の原因になる可能性があり、本来壊れていなかった部分まで壊してしまう可能性があるので、決しておすすめしません。
分解した痕跡があるパソコンの修理は受け付けないメーカーもあるので、修理業者に依頼を検討している場合は分解せず、そのままの状態で依頼しましょう。
修理に出すべきか買い換えるべきか
故障個所によっては、修理に出すと部品代や作業費で修理代が高くなってしまうこともあります。すでに5年以上使っている場合、ゲーミングPCのような高額な機種ではない場合は、これを機に新しく買い換えるのもよいでしょう。
でも、苦楽を共にしているなど思い出が詰まった愛着のあるパソコンをお使いの場合は、ぜひ修理に出して長く使ってあげてください。
まとめ
電源が入るのに画面がつかないトラブルは、さまざまなことが原因で発生する可能性があります。ご家庭で原因を特定することは困難であっても、意外と盲点である部分を見なおすことで解決することもあります。簡単なことからひとつずつ確認をすることはとても大切です。
パソコンはとても早いペースで新しい機種が発売されるので、買い替えのペースも早いものですが、学業や仕事で毎日使うパソコンを壊さず長く使うためにも、日ごろから各部に異変がないかどうかを気にかけて大切にお使いください。
あなたにおすすめの記事



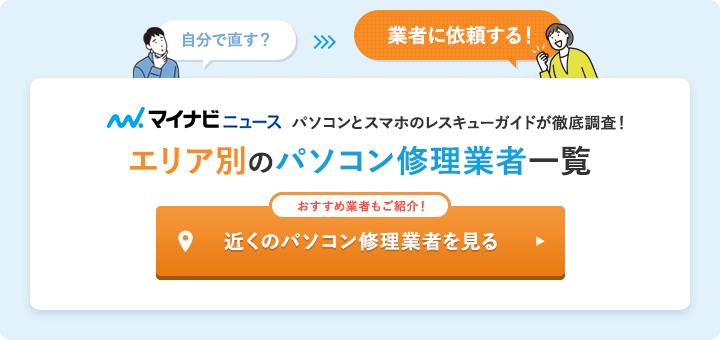
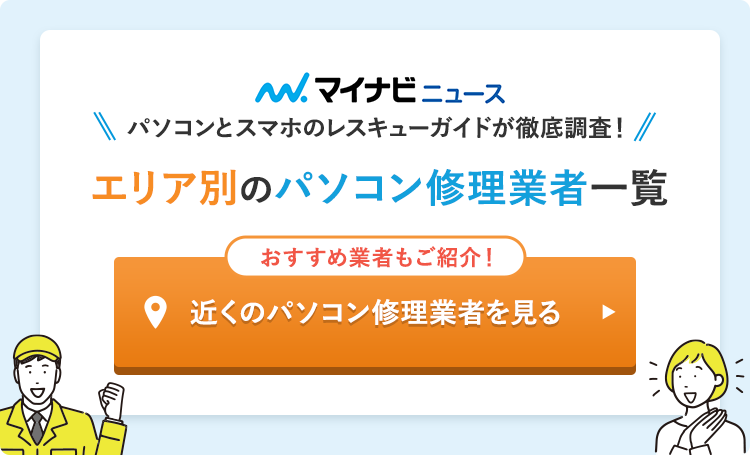

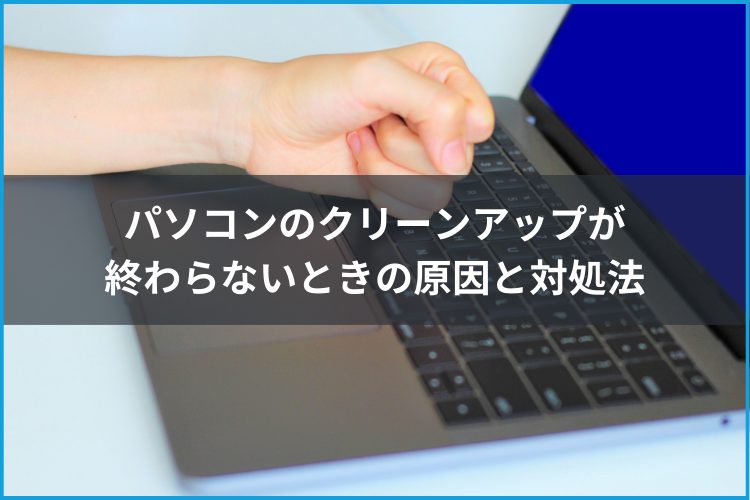
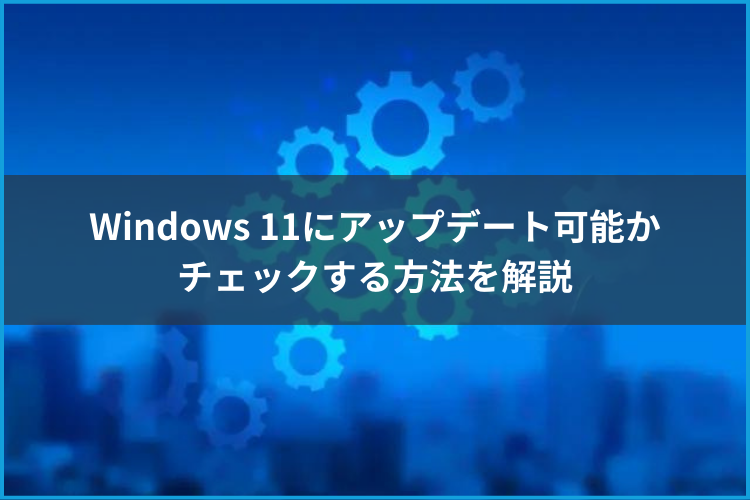
の必ずやっておきたい初期設定.jpg)