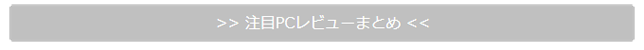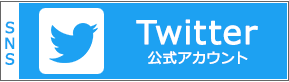修理やリサイクルの依頼もウェブから行える
PCで一番困ってしまうのは故障だろう。いくらPCに詳しいユーザーでも、こればかりは回避できない。マウスコンピューターでは、この故障に対しても迅速な対応ができる体制が整っているほか、処分したい場合に必要なリサイクルの申し込みもウェブサイトから行えるようになっている。
修理工場に送るだけでも対応可能
PCが故障した場合は、特に連絡などは必要ないという。PC本体、製品保証書、付属品、修理依頼シートをセットにして、サポートセンターに送るだけで対応が可能とのこと。この中で重要なのが、「修理依頼シート」になる。これは、ウェブサイトからダウンロードできるほか、本体に付属するマニュアルの最後のページにも付いているもので、名前や住所といった個人情報、購入日、機種名、シリアルナンバー、不具合の内容、BIOSやWindowsにパスワードを設定している場合は、その内容などを記載する。
この中で重要になるのが、「修理代金限度額」。連絡不要で修理を実行してもいい金額を決めるもので、その限度額を超える場合は同社より連絡が入ることになる。もうひとつ大切なのは、HDDの初期化について同意すること。この2つを明記しておけば、マウスコンピューターからの確認連絡が少なくなるため、修理期間が短くできるという。それだけに、多少面倒でも修理依頼シートをしっかりと書くことが、修理を短く済ます秘訣といえそうだ。送料についてはセンドバック方式(送料相互負担)を採用しており、発送時の送料はユーザーの負担となる(初期不良の場合は送料不要)。
 |
| 修理依頼シートへの詳細な記載が修理期間を短くする |
修理で一番気になるのは、期間と必要な費用だろう。有償修理の場合は、まず、作業費として5,775円が必要となる。あとはパーツ代金で、HDDの場合は1万円以下が多いとのこと。そのため、HDDの故障では合計15,000円程度になる。電源ユニットの故障でも同じような金額となり、パーツ単体の故障では15,000~20,000円が目安になるという。
期間については、有償の場合で10日前後。無償の場合は見積もりなどの確認事項が必要ないため、7日前後になるという。ただ、混雑状況によっては、もう少しかかる場合もあれば、短くなることもあるとのこと。また、電話でのサポートで修理が必要と判断された場合は、電話でそのまま修理依頼シートと同じ内容を確かめるため、本体を送るだけで修理対応できるという。
保証によって修理対応も異なる
無償修理となるのは、1年間の保証期間または購入時に有償で申し込める「3年間無償保証」の期間となる。その期間を越えた場合は、有償修理となり、上記のような費用が発生する。このほか、購入時に「ピックアップ修理」に申し込んでいた場合は、修理が必要な本体を引き取りに来てくれるため、送料はかからなくなる。このほか、技術者が出張修理してくれる「オンサイト修理」もあるが、これは個人での利用はほとんどなく、素早い修理対応を求めるネットカフェが加入していることが多いという。
- 修理の種類
保証期間内修理(無償修理)
保証期間外修理(有償修理)
ピックアップ修理(回収修理)
オンサイト修理(出張修理)
ユニークな試みとしては、同社から故障しているパーツの代わりとなるものを発送して、ユーザーに交換してもらうというもの。まだ、試験的にやっている段階というが、解決率90%と高いため今後は正式なサービスにする予定とのこと。パーツの拡張などに慣れたユーザーにとっては、ありがたいサービスだろう。
リサイクルの受け付けも可能
現在、PCは資源の有効活用のためリサイクルが義務づけられている。マウスコンピューターでは、その受け付けも行っており、ウェブサイトの「PCリサイクル申込フォーム」から申し込みが可能だ。フォームにシリアルナンバーを入力することで、リサイクル費用の有無がまず判断され、次に必要な情報を入力。すると、ゆうパックの伝票が送られてくるので、ユーザーが自分でPCリサイクル業者に発送するという流れとなる。なお、電話でも申し込みの受け付けは可能とのこと。
 |
| 専用のフォームからリサイクルを申し込める |
どんどん発展していくユーザーサポート
最後に、佐藤氏は「電話は以前よりもずっとつながりやすくなったので、どんどん活用いただきたいです」という。また、トークスクリプトのノウハウをサポートセンターのページにも反映させ、ユーザーが画面に表示される質問に答えていくだけで、修理が必要となった場合、その金額の表示と申し込みまで行えるサービスを予定しているとのこと。もし、これが完成すれば、電話やメールでトラブルの内容を説明しなくても、解決までたどり着けることになる。これだけ充実していると、製品の購入を考えている人にはかなり安心感があるのではないだろうか。また、すでに購入経験がある人も知らないサポート情報があったのではないかと思う。今後の充実ぶりにも、ぜひとも期待したい。
[PR]提供: