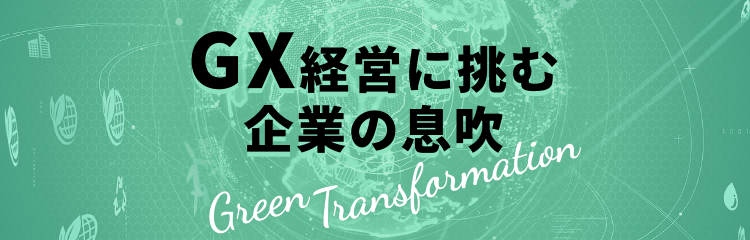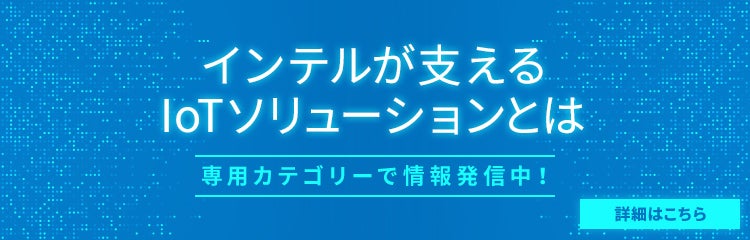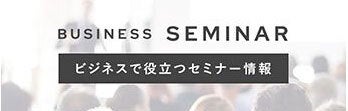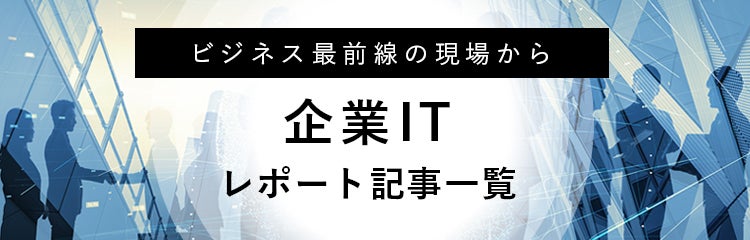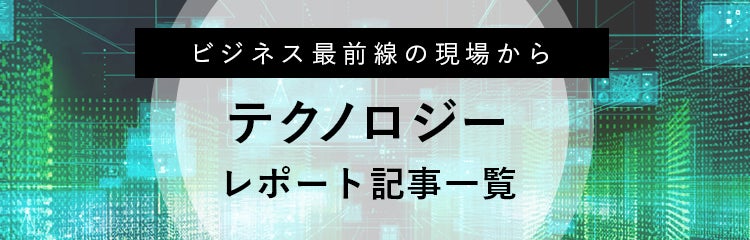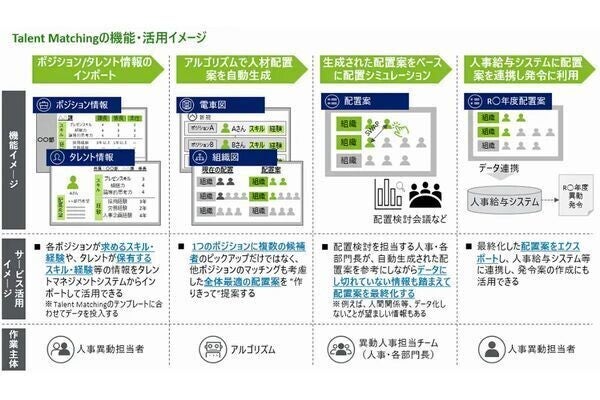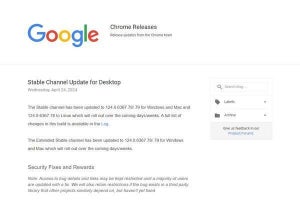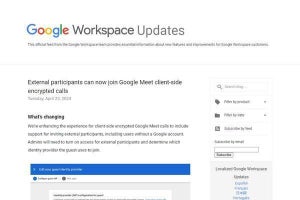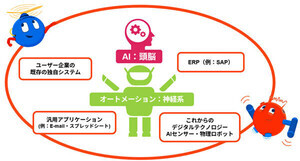注目記事
連載
Pick up (PR)
セミナー情報
2024年 4月8日(月)~26...
オンライン

[4/8-4/26配信]セールステックセミナー
【Jump Over】 顧客ニーズの理解で効果的なセールスを
2024/4/25(木)14:00 - 15:00
オンライン
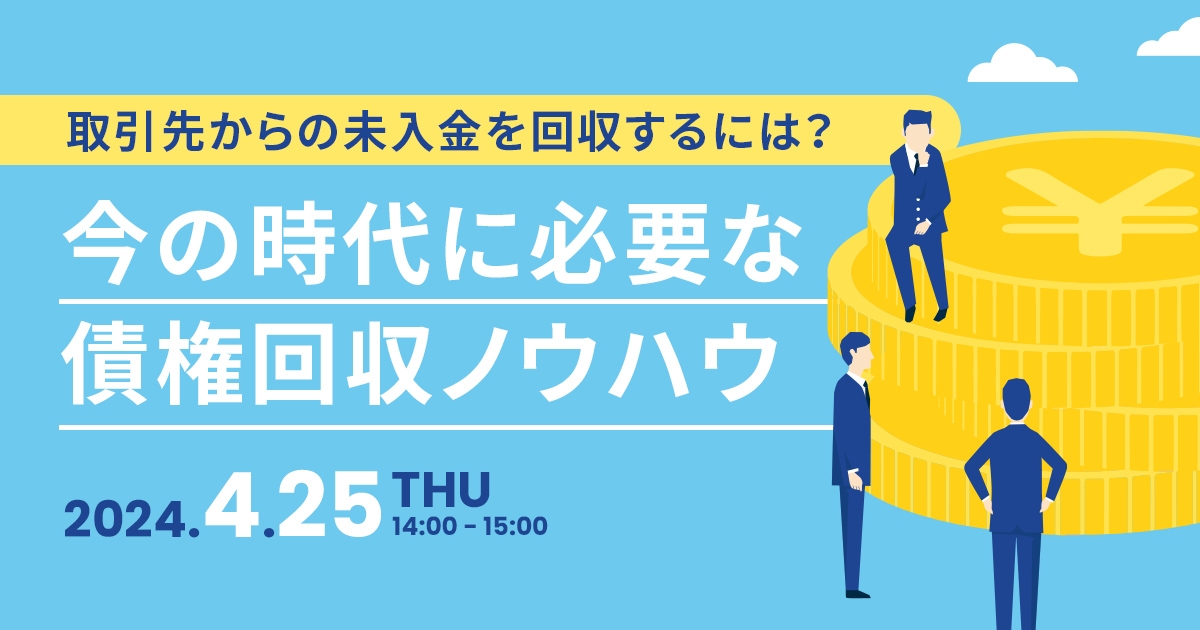
今の時代に必要な債権回収ノウハウ
取引先からの未入金を回収するには? 今の時代に必要な債権回収ノウハウ
2024年4月18日(木)13:00~14:00
オンライン

新年度のバックオフィスDX
来年こそはノンストレスで過ごす!新年度のバックオフィスDX
4月18日(木) 16:00-17:00
オンライン

サイバーリスクの削減法に迫る