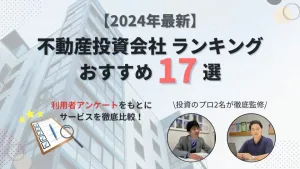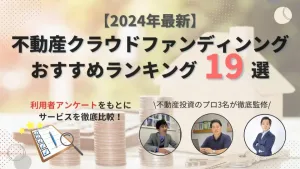投資にもいろいろな種類がありますが、少額から気軽に不動産投資できて初心者に人気があるのがREIT(リート)です。投資を始めるためには最初に投資口座を作る必要があります。
口座を開設後に取引を行いますが、その都度手数料がかかります。できるだけ手数料が低い口座を選ばないと大きな手数料を引かれるため、口座選びに迷う場合は手数料で選ぶとよいでしょう。
本記事では、REITについて種類やメリット・デメリット、選び方のポイントやおすすめ銘柄まで詳しく解説します。REITに興味のある方は本記事を参考にしてください。
REIT(リート)・J-REITとは

ここではREIT・J-REITについて、メリット・デメリットとあわせて説明していきます。
REIT(リート)とは
REITとはReal Estate Investment Trustの略称で、不動産に対する投資信託を指します。投資家から集めた資金で不動産を購入して運用を行い、得た利益を投資家に分配する金融商品のことです。
REITのメリットとデメリットについては以下を参照してください。
| メリット | デメリット |
|
|
REITは他の不動産投資と比べると、少額から投資を始めることができ、ネット証券を利用する場合は数百円から投資が可能です。そのため、少額の資金でさまざまな物件に投資することができます。
また、不動産を購入して投資を行うわけではないので、管理の手間もいりません。さらにREITは物件を証券で保有するため、資金が必要となった場合には市場ですぐに売却できます。
ただし、メリットが多い反面デメリットも存在します。例えば、REITで投資に充てる資金を金融機関からの融資で調達することはできないため、自己調達が必須です。全額自己資金で行わなければならないので少額から始めるケースが多くなり、その場合は多額の利益を得ることが難しくなります。
また、REITを運営している不動産法人が倒産したり上場廃止となったりした場合は、投資したREITの価格が下がって元本割れとなるリスクも。このようなメリットやデメリットから、REITは少額から投資を始めたい人や手間をかけずに投資したい人におすすめします。
J-REITとは
J-REITとは投資家から資金を集めて不動産を購入し、運用して得られる家賃収入や利益を投資家に分配する仕組みです。アメリカで発祥したREITの頭にJAPANの「J」を付けてJ-REITと呼ばれています。
アメリカのREITと違う点は、不動産の賃貸・保有に特化しており不動産開発は禁止されているところです。またが業務運営は外部の資産運用会社に委託して行われます。
投資の専門家監修記事!信頼できるおすすめの不動産投資会社ランキング
「【2024年最新】おすすめ不動産投資会社ランキング17選!各会社の口コミ・悪質な投資会社の見極め方も徹底解説」
「不動産投資に興味があるけど、どの会社を選べば良いか分からない」「悪質な不動産投資会社に騙されたくない」という人に向けて、不動産投資会社17社を利用した人の満足度を基に、おすすめの投資会社をランキングで紹介!
さらに、投資専門家に聞いた信頼できる投資会社の選び方や、投資額10億円の投資家インタビューも紹介しているので、ぜひご覧ください。
REITの種類について

REITには以下の3種類あります。
- 特化型
- 複合型
- 総合型
それぞれの特徴について下記の表にまとめました。
| 種類 | 特徴 |
| 特化型 |
|
| 複合型 |
|
| 総合型 |
|
REITは、不動産の種類とその組み合わせによって投資結果に差が生まれます。以下のような、一般的な投資対象物件を例にその理由を説明します。
- オフィスビル
- 住居
- ホテル
- 商業施設
- 物流施設
例えば、投資対象物件をホテルとした場合は観光者数、商業施設とした場合は市民経済と密接につながっており、これらは社会動向に大きな影響を受けます。反対に住居のように需要の変動が小さい不動産は、社会動向による影響が少なく安定しているといえます。
このことから、特化型は単一の不動産投資をするため社会動向の影響を受けやすく、ハイリスクハイリターンという特徴があります。一方複合型と総合型は、収益性と安定性を狙える不動産を組み合わせて投資するため、リスクの分散を図ることが可能です。リスクや予算と照らし合わせて、適切な運用方法を選びましょう。
投資初心者におすすめの記事!Amazonギフト券がもらえる不動産投資セミナー
「【2024年】Amazonギフト券(アマギフ)がもらえる人気の不動産投資セミナー10選|怪しい投資会社の見極め方も解説」
不動産投資セミナーは、不動産投資の基礎知識を得たり、優良な投資物件を紹介してもらえる利点がありますが、「セミナーに参加したら投資しないといけないの?」「営業がしつこくて怪しいのでは?」というイメージを抱いている人も多いのではないでしょうか。
上記の記事では、Amazonギフト券がもらえる不動産投資セミナーを10選紹介しています。セミナーや面談不要でアマギフがもらえる会社や、信頼性の高いセミナーを厳選しているので、ぜひご覧ください。
REITの選び方のポイント

さまざまなREITの銘柄があるなかで、どのように選んだらよいのかを解説します。ポイントは次の3つです。
- 投資先の種類で選ぶ
- 利回り
- 時価総額やNAVで選ぶ
では詳しく見ていきましょう。
投資先の種類で選ぶ
REITには3つの種類がありますが、まずはその3種類からどのタイプにするか絞り込みましょう。そのうえで不動産の情報を調べていくとスムーズです。
築年数が古すぎる場合は入居割合に影響します。保有している物件が多ければリスクも分散しやすくなるので、特に築年数や入居割合、REITが保有している物件数などを考慮したうえで、タイプに合わせて選ぶとよいでしょう。
利回り
投資を行う際は利回りを重視することも大切です。投資額に対して1年間でどの程度の利益が得られるのかが、利回りでわかります。例えば利回りが5%で50万円投資した場合は年間25,000円の利益が得られますが、2.5%の場合は年間12,500円の利益しか得ることができません。
しかし、利回りが高い物件を選ぶことは重要ですが、そこだけに囚われすぎるのも危険です。利回りはあくまでも指標であり、一時的な状態を表しているだけです。利回りが高い物件には高いなりの理由があります。
例えば立地が悪い物件であったり、建物が古くメンテナンスされていなかったりする可能性があります。一時的に利回りが高いだけで後々下がる可能性もあるので、なぜ利回りが高いのかをきちんと調べてから選ぶことが重要です。
時価総額やNAV倍率
時価総額やNAV倍率で選ぶこともポイントの1つです。REITにおける時価総額とは不動産投資法人の市場価値を表したものです。
投資口価格数に発行済投資口数を掛けることで算出しますが、その時価総額が大きいほど多くの投資家が投資している可能性が高いとされています。また多くの投資家が利用しているときは、値崩れもしにくく安定しているため換金性も高くなります。
NAV倍率とはNet Asset Value倍率の略称で、J-REITにおいては重要な指標の1つです。不動産投資信託1口あたりの投資金額が、1口あたりの純資産額に対してどのくらいであるかを指しています。この倍率が1倍よりも高い場合は割高とされ、反対に1倍を切っている場合は割安とされ買い時ともいわれます。
1万円からお手軽に不動産投資!おすすめの不動産投資クラウドファンディング
「【投資専門家が監修】人気の不動産クラウドファンディングおすすめ19選比較|口コミ評判と実績・選び方も解説」
「不動産投資に興味があるけど、少額から手軽に始めたい」「不動産クラウドファンディングって本当に儲かるの?」という人に向けて、不動産クラウドファンディング19社を利用した人の満足度を基に、おすすめのサービスをランキングで紹介!
さらに、投資専門家に聞いた信頼できるサービスの選び方や、利回りが高いサービスも紹介しているので、ぜひご覧ください。
REIT・J-REITのおすすめ銘柄

REIT・J-REITについて選び方がわかったら、次は銘柄を探してみましょう。ここではREIT・J-REITのおすすめ銘柄について解説していきます。
REIT(海外)のおすすめ銘柄3選
まずは海外のREITでおすすめの銘柄を3つ紹介します。
- ワールド・リート・セレクション(アジア)
- ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
- eMAXIS Slim先進国リートインデックス
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)は岡三証券が取扱っている銘柄で、主に香港・シンガポール・マレーシア・フィリピン・韓国・インドを対象とした不動産投資信託証券に投資しています。
決算は年12回で購入手数料は無料です。2022年5月20日時点での基準価額と総資産額、直近分配金は下記のとおりです。
| 基準価額 | 総資産額 | 直近分配金 |
| 5,034円 | 391億7,800万円 | 35円 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)は、ニッセイアセットマネジメントが取扱っている銘柄で、主に海外のREITを主要投資対象としています。決算は毎月25日です。
2022年5月20日時点の基準価額・総資産額・直近分配金は次のとおりです。
| 基準価額 | 総資産額 | 直近分配金 |
| 3,096円 | 1,040億3,700万円 | 30円 |
eMAXIS Slim先進国リートインデックス
eMAXIS Slim先進国リートインデックスは三菱UFJ国際投信が運営しています。主に日本を除く先進国に上場している不動産投資信託に投資を行っており、S&P先進国REITインデックスに連動する投資成果を目指して運用しています。この銘柄もワールド・リート・セレクション(アジア)同様に、購入手数料は無料で毎月決算を行っています。
2022年5月20日時点での時点の基準価額・総資産額・直近分配金は下記のとおりです。
| 基準価額 | 総資産額 | 直近分配金 |
| 11,979円 | 168億9,400万円 | 0円 |
J-REIT(国内)のおすすめ銘柄3選
次に日本版REITであるJ-REITのおすすめ銘柄を3つ解説します。
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)は大和アセットマネジメントが運営しています。東京証券取引所が算出して公表している、東証REIT指数に連動する投資成果を目指して運用している銘柄です。
毎月15日に決算を行い収益を分配しています。2022年5月20日時点での時点の基準価額・総資産額・直近分配金は下記のとおりです。
| 基準価額 | 総資産額 | 直近分配金 |
| 2,775円 | 3,983億5,900万円 | 60円 |
eMAXIS Slim国内リートインデックス
eMAXIS Slim国内リートインデックスは三菱UFJ国際投信が運用している銘柄で、eMAXIS Slim先進国リートインデックス同様に購入時に手数料はかかりません。
東証REIT指数に連動する投資成果を目指して運用しており、年に1回決算を行って利益を分配しています。2022年5月20日時点での基準価額・総資産額・直近分配金は下記のとおりです。
| 基準価額 | 総資産額 | 直近分配金 |
| 9,674円 | 102億8,300万円 | 0円 |
ニッセイJリートインデックスファンド
ニッセイJリートインデックスファンドは、ニッセイアセットマネジメントが運用している銘柄で、購入・換金ともに手数料はかかりません。
主に国内の不動産投資信託証券に投資するファンドで、東証REIT指数に連動する成果を目指して運用しています。決算は毎年1回行われ利益が分配されます。
2022年5月20日時点での時点の基準価額・総資産額・直近分配金は下記のとおりです。
| 基準価額 | 総資産額 | 直近分配金 |
| 19,945円 | 157億600万円 | 0円 |
REITを始めるための3ステップ

REITは、以下の3ステップで簡単に始めることができます。
- 証券口座を開設する
- 証券口座に資金を入れる
- REITを選んで購入する
REITは証券会社に証券口座を開設しなければ始めることができません。利用したい証券会社を選び、必要な書類をそろえて申請しましょう。証券会社の窓口かネットで申請することができます。
無事に証券口座が開設できたら口座に必要な資金を入金することで、REITを購入することが可能です。次に購入する銘柄を選んで購入してみましょう。
REITでおすすめの証券口座3選

ここで、REITでおすすめの証券口座を3つ紹介していきます。それぞれの特徴や料金を比較して自分に合う証券口座を見つけましょう。
| 証券会社名 | 特徴 | 約定10万円ごとの手数料 | 約定20万円ごとの手数料 | 約定50万円ごとの手数料 | 約定100万円ごとの手数料 | 約定300万円ごとの手数料 |
| LINE証券 | スマホだけで投資が完了 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 記載なし |
| GMOクリック証券 | 定額プランで取引手数料が抑えられる | 0円(1日定額プラン)
90円 |
0円(1日定額プラン)
100円 |
0円(1日定額プラン)
260円 |
0円(1日定額プラン)
460円 |
1,691円(1日定額プラン)
880円 |
| DMM.com証券 | 最短で当日に取引可能 | 88円 | 106円 | 198円 | 374円 | 660円 |
LINE証券
LINE証券は気軽に少額から投資できる証券会社です。スマホユーザーでも利用しやすいように、見やすくて使いやすいLINEアプリで入金から投資、出金まで行うことができます。
スマホ証券利用率No.1の証券会社で、貯まったLINEポイントは1ポイント1円で投資に利用可能。LINEPayでの入出金は無料で行えます。LINEユーザーにとって、使いやすく便利なサービスを提供しているのが特徴です。
また、口座開設とクイズに正解することで3,000円相当の株がもらえるキャンペーンや、10,000円以上の取引で現金1,000円プレゼントなどのキャンペーンも行っているため、ぜひチェックしてみてください。
LINE証券はこんな人におすすめ!
- スマートフォンだけで投資したい人
- LINEPayやLINEポイントを利用している人
- 少額から投資してみたい人
GMOクリック証券
GMOクリック証券は、取引コストが業界最安水準であると評判の証券会社です。約定100万円までは取引手数料が無料ですが、1約定ごとのプランでも10万円までなら90円と少額で利用できます。
投資信託なら100円と少額からの投資が可能で、投資初心者で高額な取引が不安な人でも手軽に利用できるのが特徴です。
GMOあおぞらネット銀行とGMOクリック証券の口座を連携させることで、GMOあおぞら銀行の預金金利が110倍になります。またGMOグループの株式会社保持者は株主優待として、売買手数料キャッシュバックなどお得なサービスがある点も魅力です。
GMOクリック証券はこんな人におすすめ!
- 取引手数料を抑えたい人
- GMOあおぞら銀行の口座を所有している人
- 少額で投資を始めてみたい人
DMM.com証券
業界最安水準の手数料で取引できるのがDMM.com証券の魅力です。取引手数料を全額キャッシュバックする方法により、25歳以下の人は現物取引手数料が実質無料となっています。米国株式も手数料無料で投資できるので、米国株に興味のある人にもおすすめです。
口座開設から取引までは「スマホでスピード本人確認」により最短で当日に可能です。また初心者でも安心して取引が行えるように、24時間対応でメール・電話・LINEでのサポートを行っています。
パソコンやスマートフォンでも取引は可能ですが、スマホアプリではパソコン同様のスクリーニング機能などが使えます。その他にも、複雑な操作をせずに取引できる「かんたんモード」で手軽に投資が可能です。
DMM.com証券はこんな人におすすめ!
- 手数料を抑えて取引したい人
- 米国株に興味のある人
- スマートフォンでもパソコンでも利用してみたい人
NISA、ETFの違いとは

不動産投資にはREIT以外にもいくつか方法がありますが、ここではREITとNISA、EFTを比較します。そもそもREITはNISAやETFと何が違うのか、それぞれの特徴を解説するので、自分に合う投資方法を検討しましょう。
REITとNISAの違い
NISAとは、非課税口座であるNISA口座内で、毎年一定金額内で購入した株式や投資信託の売買で得られる利益が、非課税になる制度です。NISAはREIT同様に少額からの投資が可能ですが、購入したNISAの投資対象にはREITも含まれています。
REITの分配益・譲渡益に対する課税は20.315%です。一方NISA口座内で購入して得られた利益に対する課税は、毎年120万円最長5年間非課税となるのが大きな特徴といえます。
ただしNISAでは損益通算ができません。損益通算とは同一年分で出た損失と利益を相殺することで、申告する利益を少なくすることができるものです。このように、メリットだけでなくデメリットも存在することは覚えておくとよいでしょう。
REITとETFの違い
ETFは上場投資信託の一種で、証券取引所に上場しており株式と同様の購入ができます。NISAのようにETFを利用して、複数のREITに分散投資が可能です。
ETFでREITを利用することで、REITETFと呼ばれる場合もありますが、REITと異なり日経平均株価や東証株価指数に連動して運用を行っています。ETFの投資対象指数はさまざまな銘柄で構成されているため、1つのETFを購入するだけで分散投資ができ、リスクを抑えた投資が可能です。REITETFも少額から購入できる投資方法です。
REITETFは、税法で費用を差し引いた利益すべてを分配金として支払われますが、不動産市況や金利に影響されやすいといった特徴もあります。
まとめ

REITは少額からの不動産投資ができるため、自己資金で始めやすい投資方法です。運用は専門家が行うので時間を取られる心配もありません。実物の不動産とは異なり、流動性・換金性ともに優れています。
また特化型REITなら売却益を狙いやすく、複合型、総合型REITでの投資ならリスク分散も可能で、一人ひとりのスタイルに合わせた不動産投資を実現できます。本記事で紹介したおすすめの銘柄や証券口座を参考に、不動産投資の第一歩としてREITを始めてみませんか?
※「マイナビニュース土地活用・不動産投資」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.fsa.go.jp/news/30/20190328_summary.PDF
・https://www.fsa.go.jp/news/r4/kokyakuhoni/20230120/kpi_toushin_230120.pdf
・https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html
・https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001411696.pdf
・https://www.fsa.go.jp/
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。