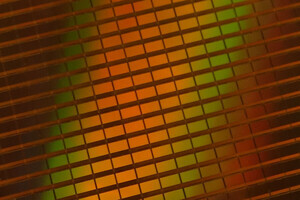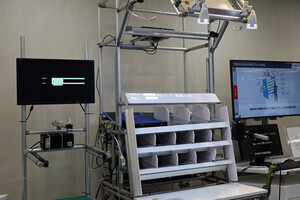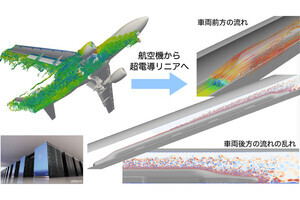できたばかりのアニメーション制作会社の処女作が、アカデミー賞にノミネートされた――そんな鮮烈な話題で一躍注目を浴びたのが、堤大介氏とロバート・コンドウ氏の共同監督によるオリジナル短編アニメーション映画『ダム・キーパー』。『トイ・ストーリー3』や『モンスターズ・ユニバーシティ』のアートディレクターをつとめたふたりが、ピクサーから独立してはじめて発表した作品だった。
まるでこの展開自体がアニメの中の出来事であるかのような、ドラマチックなエピソード。それに惹かれて、同賞の授賞式開催地の米国、堤監督の母国・日本など各国のメディアが注目(もちろんそこにマイナビニュースも含まれる)。はた目には順風満帆に見えるが、同作の監督のひとり・堤大介監督が絵の道を志したのは、何と大学に入ってから。絵を仕事にしている人としては、かなり遅まきのスタートだ。
今回は、活動の拠点であるアメリカを離れ来日していた堤大介監督に、ロングインタビューを敢行。堤氏が絵の道に進んだきっかけから、世界に名だたるピクサーに在籍しながら独立した理由、日本のアニメーション制作会社と協業する理由などについて聞いていく。 全3回に分けてお届けする本インタビュー。第1回は、堤氏がなぜ、アメリカのアニメーション業界で働くに至り、世界最高峰のスタジオとも言えるピクサーを飛び出し、独立したのか。そのいきさつに迫った。
――最初に、これまでの経歴、堤さんが絵を仕事として選んだきっかけについて、お話しいただけますでしょうか。
高校生まで日本で暮らし、日本の学校に通っていて、ずっと野球に取り組んでいました。学生のころもらくがきをするのは好きだったんですが、まわりにうまい友人が何人かいて、特に、仲が良かった子はものすごく上手で。だから、自分が絵の道に進むというのはまったく考えていなかったですね。
きっかけは、高校卒業後にアメリカ留学したことでした。それまで野球一筋、受験勉強というものに取り組んでこなかったので、そこから受験をして、日本の大学へ進むのは難しく、自然に留学という道を選びました。
――例えば一浪して日本の大学に進むという選択もあったと思うのですが、アメリカ留学を選ばれたのはなぜですか?
その当時、留学ブームであったという時代背景もありましたが、母親の方針に影響を受けたところが大きいです。彼女は日頃「しなさい」と言う方ではなかったのですが、「高校を卒業したら、とりあえず家を出てください」とは言われていました。
皆がみんなそうではないですが、日本では大学受験のために必死に勉強して、入学したらサークルに入って遊ぶというような印象もあり、それを母はあまりよく思っていなかったようです。また、僕の姉も留学していたこと、留学すれば受験勉強をしなくて済むという打算もあって、渡米することを決めました。
――英語は勉強してから渡米されたのでしょうか?
野球部の引退後に時間があったのでTOEFLの勉強こそしましたが、アメリカに行った当初はまったく話せませんでしたね。
いまだに覚えているのは、留学したてのある時、「ピザを食べたい」と思って、テイクアウトのピザ屋に行ったんです。店員さんに「ピザ」と伝えたら、一切れだけ買うつもりが、超巨大な物が丸ごと出てきてしまって…。ですが、「間違っている」と言うこともできず、やむを得ずそのまま受け取って、自転車だったので片手でかついでどうにか持ち帰りました。そのくらい、英語はできませんでしたね。
――現地で生活される中で、どんどん身につけていかれたんですね。
僕は極端な性格なので、やるときはとことんやる方で、野球にも熱中して取り組んでいました。なので、英語も渡米してからですが、とことん身につけようとしました。しゃべれないとどうにもならないだろう、と。
留学当初は同じ日本人の留学生とはまったくしゃべりませんでしたね。仮にしゃべるとしても日本語ではなく英語で話しかけるという、今考えれば嫌な学生だったと思います。正直後悔している部分もあるのですが、そういう極端なことをしていた時期もあるくらい、英語を身につけようと必死でした。
――それまでずっと野球一筋だった堤さんが絵を志すきっかけになったのは何だったのでしょうか?
語学学校時代、地域に開放されていた絵のクラスで、地元のおばあちゃんに褒められたことが絵を志すきっかけでした。
ですが実際に美大へ進んだら、僕はクラスの中で画力が一番下なんです。当然ですよね、絵を始めたのが遅すぎたんです。しかも、僕が取っていたクラスの先生は名物先生で、クラスからよく生徒を追い出したりしていました。僕もまさにそのターゲットにされて、2度彼のクラスから追い出されたことがあります。
――そんな仕打ちを受けて、絵をやめたくなったりはしなかったのでしょうか?
それまでずっと野球をやっていたこともあって、良薬口に苦しといいますか、ラクだったらダメな気がしてしまうところがあって。例えるなら、あまり興味がなかった女の子にそっけなくされて追いかけてしまうみたいなもので、逆に見返してやろうと思って取り組んでいました。
その方はすごく有名な方で、その先生の授業の映像が教材ビデオとして売られることもあるくらいです。そのビデオはクラスの上位から代表3人を選んで指導するというもので、最終的に僕はその代表に選ばれました。
でも、彼は僕をクラスから追い出したことは覚えてないと思うんですよ。選出したタイミングで、「最初は無理だと思ったが、よくぞここまで」というような、指導者としてのコメントも特になく(笑)。学習過程の終盤では、僕の絵が良い例として使われたりしていたので、いつの間にか認めてくれていたんでしょうね。
ただ、僕はその先生について、指導者としては失格だと思っているんです。でも、ダメな先生だから生徒は学べない…というのはおかしいですよね。「いい先生に恵まれなかった」という言い訳で、自分が損するのは嫌じゃないですか。ダメな先生からだって得られるものは絶対にあります。彼はアーティストとしては本当にすごい人で、盗めるところは盗めるようにがんばりました。
――少し話はそれてしまうのですが、奥さまが宮崎駿さんのご親戚ということを耳にはさんだのですが、アニメ業界を目指されたきっかけは、宮崎駿さんと何か関係はありますか?
いいえ、関係はないです。妻は確かに宮崎さんの親戚ですが、彼女とは小学一年生のころの同級生で、僕がまだ「宮崎アニメ」を観た事がない時に出会っているんです。(編集注:当時、スタジオジブリ開設前で、宮崎駿氏はまだ『となりのトトロ』等オリジナルの劇場アニメーション制作を開始する前だった)
なのでキャリアの開始には関わりはありません。僕にとって、宮崎さんはただただ憧れている、神様のような存在です。
――では、何をきっかけにアニメーション制作に携わることを決めたのでしょうか?
僕がアニメ業界に入ったきっかけは、絵を描いてアメリカに残るにはどうしたらいいか?と考えた結果でした。会社で働かないとビザが下りないので。絵が描ければいいやという安易な気持ちで始めたものの、初めてみたらもうとにかく面白くて。個人でやるより、チームで取り組む方が自分に向いているなと感じました。
――就職された後、ピクサーへの転職を遂げ、トイ・ストーリー3でアートディレクターを務めるなど、外から見ればこれ以上ない、非常に華々しい職歴であったと感じます。またご家族がいらっしゃる状況で独立を決断するのは相当な勇気が必要であったと想像します。それにも関わらず、ピクサーを去って会社を興した理由はどこにあったのでしょうか?
ピクサーから離れないと、これ以上成長できないと感じたからです。
とはいえ、ピクサーに残っていたら成長できなかったかというと、そんなことはなかったと思います。ピクサーで取り組んでいたことは、もちろん大変な仕事でしたから。でも、自分の可能性に大きな賭けをするなら今やらないと、トライできなくなると考えたんです。
アメリカの場合、一度アニメーション作品の制作に入ると3年程かかります。なので、次の作品に参加していたら、家族の状況で言えば、息子が小学校に入るタイミングになります。もろもろのことを考えて、今しかないと。
――著名クリエイターの直筆イラストを1枚のスケッチブックに描きこんでもらう「スケッチトラベル」など、ピクサー在籍時も意欲的なプロジェクトを実行されていましたが、それでもなお、会社を離れた理由をお伺いしたいです。
スケッチトラベルやトトロの森保全などのプロジェクトを通じて、自分で人をまとめて物事を動かすことが好きだと気がつきました。これらは仕事の傍ら取り組んできたプロジェクトですが、どこかで「自分の力を本当の意味で試してみたい」、つまりフルタイムで自分のプロジェクトをやりたいという願望が芽生えたんだと思います。
「ダム・キーパー」の制作も、本業のかたわらで取り組んだことです。毎日がチャレンジで。本当に大変な思いをしました。何かプロジェクトを動かす時、ふつうは準備万端でやりたいものですが、この作品は準備どころではなく、やってみて初めて問題が発覚するような、その繰り返しだったんです。
これまでピクサーではアートディレクターの仕事に専念していたので、短編とはいえ映画にまつわるすべてを作っていくのは初めてで、次々と噴出する問題をひとつずつクリアにしていくうちに、どんな問題がやってきても、その時に考えればいいやという覚悟ができてくるんです。そうして瞬時に問題を解決できる「筋肉」のようなものが備わってくると、日々自分がそこで成長しているということが感じ取れる、ということに気がついたんです。ジムで体を鍛える時も、筋肉を極限までいじめることで、回復したときに筋肉が増えるのと同じで、極限まで無理だということを克服したときに、次のレベルに行けるんです。
そうした経験をする中で、ピクサーの仕事では、問題を克服する筋肉を養う機会が無くなってきていることが分かってしまったんです。僕は7年、ロバートは12年ピクサーに在籍していて、ふたりとも社内ではそれなりの評価をもらっていました。もちろん簡単な仕事ではないですが、こうすればできるというような自信も出てきて、会社の方も、このふたりに任せればできるというような雰囲気になっていて、だからこそ、挑戦とは遠いところにいると感じることが多くなりました。
――その「気づき」を促した決定的な出来事は何かあったのでしょうか?
『ダム・キーパー』を作るため、僕たちは3カ月間会社から休みをもらったんですが、所定の期間だけでは終わらなかったので、制作途中にピクサーの仕事に復帰したんです。戻った初日、ピクサーの景色がそれまでとはまったく変わって見えました。
ピクサーは制作スタッフが仕事をしやすいよう、あらゆるものが整っているいわば「理想郷」で、それまでのチャレンジの日々とはあまりに対照的でした。この体験が、独立への決意につながったと感じています。
もちろん、それからすぐに辞めたわけではなくて、悩みました。それに、家族である妻のサポートがなければ絶対に決心できなかったと思います。
――共同設立者で、ピクサー在籍時も共に『ダム・キーパー』を制作していたロバート・コンドウさんも、同じタイミングで独立を決意されていたのでしょうか。
ロバートは本当に優秀なクリエイターですから、僕としては一緒に起業できたらという願いはありました。ですが正直なところ、彼が一緒に来てくれるかどうか、いざ話を持ちかけるまで分かりませんでした。というのも、彼はカリフォルニアで生まれ育ち、卒業後の最初の仕事がピクサーで…という、大きな変化を選んで来なかった人でしたから。あとでロバートに聞いたら、僕が誘わなければ辞めなかったと言っていました。
――ピクサーという大企業を辞するにあたって、やはり「引き際」というのはどの会社でも難しいこととは思いますが、スムーズに進行できましたか?
ふたりとも責任ある仕事を任されていましたし、特に僕は次の映画の制作に入っていたので、ある程度時間をかけて引き継ぎをしました。社内の雰囲気という意味でも、僕が辞めるといった時に、多くの同僚が納得してくれました。
実は、僕は退職の直前、社長から直々にメンターシップを受けていました。なので、彼に直接辞意を伝えたのですが、「分かっていた」というようなことを言っていただけました。メンターシップは将来のピクサーのリーダーを育成するためのプログラムなので、その時間を無駄にしたと叱責されてもおかしくない状況だったのに。
僕らは『ダム・キーパー』を作っている時、ピクサーの近所にあるとても小さな、そして到底キレイとは言えない小さな部屋を借りて、そこで制作を行っていました。社長はそこへも足を運んでくださって、「今が一番大切な時間だから、大切にしなくてはいけない」と言ってくださいました。ピクサーのような大きな会社であれば、メンターシップのような特別な機会でもなければ、社長と密にコミュニケーションを取ることは大変難しいですから、とても貴重な経験になりました。
そして、メンターシップを通じて、自分が彼のようになるためには、現状のままでは無理だということを痛感しました。社長をはじめ尊敬しているクリエイターたちはどこかでリスクを冒して、自分に対してチャレンジしている。そして、その裏には自らへの「なぜ」創るのかという問いかけがあり、その理由を明確にして動いている。だからこそ僕は独立したんです。