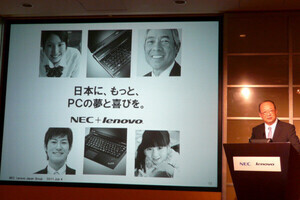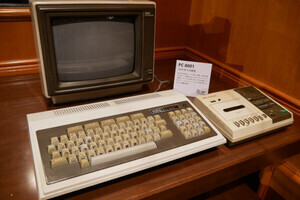NECのコンピュータ技術を象徴する取り組みのひとつに、スーパーコンピュータがある。
1978年、世界を変えた1GFLOPSをめぐる攻防
NECは、1978年6月に、科学技術庁航空宇宙技術研究所の計算センターから、数値風洞シミュレータ用コンピュータの共同開発を打診されたのをきっかけに、スーパーコンピュータの開発に着手した。航空機の設計開発に欠かせない風洞実験を、スーパーコンピュータの数値シミュレーションによって置き換えるという野心的な試みであり、このとき、求められる性能は、1GFLOPSに設定された。
その前年となる1977年に開発された最初のスーパーコンピュータであるクレイ・リサーチのCRAY-1の性能は140MFLOPSであり、1GFLOPSという目標は、とてつもなく大きな目標であった。
NECでは、心臓部分に当たる超高速LSIの開発や、半導体実装技術の開発などに着手するために、全社をあげた先端技術開発プロジェクトをスタート。1983年4月には、570MFLOPSのSX-1と、1.3GFLOPSのSX-2を発表した。
だが、SX-2では、1GFLOPS超えを証明する演算速度の実測に手間取り、1985年1月に、富士通が1GFLOPSを超えるスーパーコンピュータの実測に成功し、先を越されてしまったのだ。NECは、それから約1年後の1985年12月に、SX-2で1.3GFLOPSの実測に成功。ここで初めて、NECは世界最高速の実力を示すことができたのである。
1986年以降、東北大学や運輸省港湾技術研究所、大林組、住友金属工業などが、SX-2を相次いで導入。海外では米ヒューストン地域研究センターにも導入された。
なお、SX-2は、1987年に、円周率で小数点以下1億3355万4000桁までを計算し、当時のギネス記録に認定されている。
さらにNECは、1989年4月には、SX-3を発表。国産スーパーコンピュータとしては、初めてマルチプロセッサによる並列処理を実現し、22GFLOPSの世界最高速の性能を達成している。
その後も、SXシリーズは進化を遂げ、1994年11月には最大構成でテラFLOPSの領域に初めて到達したSX-4を発売。1998年のSX-5、2001年のSX-6、2002年のSX-7、2004年のSX-8と進化し、2007年9月には、第7世代となるSX-9を発表。2013年11月には「SX-ACE」により、マルチコア型ベクトルCPUを初めて搭載し、当時としては、世界一のコア性能と、世界一のコアメモリ帯域を実現した。
現在、NECでは、大容量の高速メモリと高速行列計算を可能とするベクトル型スーパーコンピュータ「SX-Aurora TSUBASA」を製品化している。
NECが長年スーパーコンピュータ開発で培ったLSI技術と高密度実装技術、高効率冷却技術などを結集したベクトルエンジン(VE)を複数搭載した省電力サーバーで、VEをPCIeカード型としたことで、これを筐体に差し込んで利用できるようにしたのが特徴だ。VEを1基搭載し、デスクトップとして利用できるエッジモデルから、複数のVEを搭載したオンサイトモデル、データセンターモデルをラインアップ。科学技術計算やビッグデータ解析での高速処理のほか、気象予報や地球環境変動解析、流体解析、ナノテクノロジー、新規素材開発などのシミュレーション、AI活用においても、高い実効性能を実現している。
地球シミュレータ、世界最速の1000倍を目指した国家プロジェクト
NECのスーパーコンピュータの取り組みで見逃せないのが、1997年にスタートした地球シミュレータへの参画だ。
スーパーコンピュータによって仮想の地球を作り、冷夏や暖冬などの気候変動を予測。エルニーニョなどの海洋現象の予測や、台風の正確な進路予想などを行うほか、生態系変動予測、地球内部の変動メカニズムの解明などにより、人間社会と地球の持続性に貢献することを目的とした国家プロジェクトだ。NECは、その開発に協力し、2002年にこれを完成させた。
地球シミュレータで求められたのは、当時の世界最高速のスーパーコンピュータの1000倍の性能という途方もないものだった。
プロジェクトスタート時点で、NECの最新スーパーコンピュータは、1994年に発表していたSX-4であったが、地球シミュレータで求められる性能を実現するには、32個のチップで構成していたSX-4のプロセッサを、ひとつに集約するという大きな進化が必要であった。また、プロセッサ内の配線を、従来のアルミ配線から、より電気抵抗が少なく遅延時間を短縮できる銅配線へと変更するとともに、約20mm四方のチップに、5700万個のトランジスタを実装しなくてはならなかった。NECでは、LSIのパッケージング技術に、ビルドアップ配線基板を採用し、約30倍の配線収容性や配線幅の微細化による高密度化を実現して、こうした課題を解決していった。
さらに、開発当初は、空冷方式を予定していたが、これでは十分な冷却ができないことが明らかになったため、試行錯誤の結果、内部に封入した冷媒の沸騰と凝縮によって放熱する「沸騰型ヒートシンク」という新たな技術を開発。技術的限界を超えることに成功したのだ。
このとき、NECでは、26以上の部門と11以上の関係会社から延べ1000人が参加。まさに、NECグループの総力を結集した一大プロジェクトとなった。
2002年に稼働した地球シミュレータは、35.86TFLOPSの性能を達成し、スーパーコンピュータの計算性能としては、ほかを寄せ付けない圧倒的な世界1位を獲得。ニューヨークタイムズは、地球シミュレータが誕生した衝撃を、旧ソビエト連邦が米国に先駆けて人工衛星「スプートニク」を打ち上げたことになぞらえて、「コンピュートニク」と呼んだほどだった。地球シミュレータの世界ランキング1位は、その後、2年半にわたって維持された。
だが、NECは、地球シミュレータに続く、スーパーコンピュータプロジェクト「京」には関しては、スタート時点では参加していたものの、2009年5月にプロジェクトからの撤退を決めた。莫大な開発コスト負担を抱えた技術主導のビジネスモデルを維持することが、限界に達していたのが理由だった。リーマンショックの影響を受け、2008年度に2966億円の最終赤字を計上したNECにとって、研究開発費の縮小が避けられないなか、プロジェクトからの撤退は苦渋の決断だったといえる。
しかし、地球シミュレータで培った技術と経験は、その後のNECのコンピュータ事業に生かされている。Express 5800シリーズの高性能サーバーに地球シミュレータで培った技術が活用されているほか、省電力技術や空調技術、そしてネットワーク技術にも、地球シミュレータでの経験が生かされている。さらに、NECが得意とする顔認証などのセーフティ技術の開発や、クラウドサービスを提供するデータセンターの構築にも生かされているという。
なお、NECは、地球シミュレータの進化においては、貢献を続けており、2009年にはNECのSX-9/Eを活用したES2を稼働。2015年のES3では、SX-ACEで構成した世界最大規模の分散メモリ型ベクトル並列計算機として稼働させた。また、2021年から稼働している現行のES4は、NECのVector EngineやNVIDIAのGPUであるA100を組み合わせたマルチアーキテクチャー型スーパーコンピュータとして開発。SX-Aurora TSUBASA B401-8を684台(5472基のVEを搭載)などにより、最大理論性能として19.5PFLOPSの計算能力を実現した。従来システムの約15倍の性能を実現する一方で、消費電力はほぼ同等、設置面積は約半分しており、地球環境や海洋資源、海域地震および火山活動に関する研究開発などに使用されている。
地球シミュレータの経験が、NEC独自といえる数々の技術の進化につながっているのは間違いない。
時代は「量子コンピュータ」へ、独自の道を切り拓くNECの現在
一方、NECは、1999年に、量子コンピュータの基礎である「個体素子量子ビット」を世界で初めて実証した企業でもある。
これは、量子コンピュータの実用性に道を開く画期的な取り組みであり、NECは、「量子コンピューティングの元祖」といってもいいだろう。
2003年には、2ビット論理演算ゲートの動作に世界で初めて成功し、2007年にはビット間結合を制御可能な量子ビットの実証にも成功。量子アルゴリズムに従った量子演算を可能にしている。
さらに、2014年には、超伝導パラメトロン回路を用いて、量子ビットの高精度、高速、非破壊な単一試行読み出しに成功し、世界で初めて、高感度読み出し可能なパラメトロンと量子ビットの融合を実現したのだ。
NECでは、この超伝導パラメトロン素子による超伝導回路を用いた国産8量子ビット量子アニーリングマシンを2023年6月に開発。インターネットを介して外部利用可能な国産量子アニーリングマシンは日本初となった。
その一方で、スーパーコンピュータを活用して、組み合わせ最適化問題を解くことができるシミュレーテッドアニーリングマシン(疑似量子アニーリング)も開発。NEC独自の疑似量子アニーリングプラットフォームを通じたNEC Vector Annealingサービスも展開している。
NEC Vector Annealingサービスは、ベクトル型スーパーコンピュータ「SX-Aurora TSUBASA」を活用。許容解の存在範囲を高速検索するシミュレーテッドアニーリングエンジンを組み合わせて、大規模処理と高速処理を可能にする疑似量子アニーリングプラットフォームとして提供している。
さらに、「SX-Aurora TSUBASA」に搭載する複数のVEを高速に接続することで、30万ビットに規模を拡大。たとえば、約500都市を対象にした巡回セールスマン問題といった従来は解くことが難しかった課題を、高速に解くことができるようになったという。これらのサービスは、クラウド型とオンプレミス型で提供。シミュレーテッドアニーリングマシンの特徴を活かして、人員スケジューリングの最適化のほか、配車スケジュール、配送ルート、荷積み、生産計画、金融ポートフォリオの最適化などに応用されている。
社会課題の解決に向けても量子技術は活用されている。
NECが、東北大学や北海道大学などと共同で開発している「津波災害デジタルツイン」では、「SX-Aurora TSUBASA」による疑似量子アニーリング技術および量子アニーリング技術を併用して、津波災害発生時の社会への影響を予測するほか、被害を最小化したり、回避したりするために最適な対応を、組み合わせ最適化問題として導き出すことに取り組んでいる。量子技術により得られた最適解が、現実世界での望ましい災害対応となるように検証を実施しているところだ。2027年度には、「津波災害デジタルツイン」の完成を目指している。
そして、NECでは、量子ゲート型量子コンピュータ領域においても、研究開発を進めている。NECでは、科学技術振興機構(JST)による研究開発プロジェクト「超伝導量子回路の集積化技術の開発」に参加し、超伝導量子回路の集積化技術の開発に取り組んでいる。この技術を活用することで、超伝導量子ビットの大規模化や高集積化が可能になると見込まれている。長期的な取り組みにはなるが、2050年には、大規模な超伝導量子コンピュータの実現を目指すという。
「量子コンピューティングの元祖」であるNECは、いまでも量子技術の進化に向けて、研究開発の歩みを進めている。