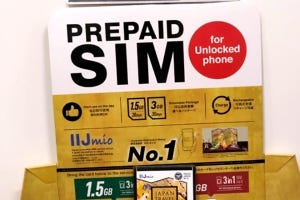「格安スマホ」などと呼ばれ、スマートフォンの通信料金が劇的に安くなるとして大きな注目を集めた仮想移動体通信事業者(MVNO)。ですが、最近、MVNOの名前を聞くことはあまりなくなってきています。なぜでしょうか。
ブームから一転、大手の攻勢で伸び悩む
2015年ごろ、「格安SIM」「格安スマホ」といった言葉が大きな注目を集めたことが記憶に新しい人も多いのではないでしょうか。
「格安SIM」は、携帯電話大手からネットワークを借りてサービスを提供するMVNOの通信サービス、「格安スマホ」はそれにSIMフリーのスマートフォンをセットで販売する販売手法を指しています。MVNOの通信サービスは、通信料金が携帯電話大手の半分から3分の1という劇的に安い水準であるというだけでなく、携帯電話大手と同じくスマートフォンとのセット販売という分かりやすい販売スタイルが導入されたことで、消費者から大きな注目を集め人気を獲得するに至りました。
格安スマホのブームに乗り、多くのMVNOが次々と誕生しました。その多くは、インターネットイニシアティブ(IIJ)やビッグローブなど、固定ブロードバンドサービス向けのインターネットサービスプロバイダーでした。なかには、イオンリテールの「イオンモバイル」や、DMM.comの「DMM mobile」など異業種からの参入があったり、プラスワン・マーケティングの「FREETEL」などベンチャー企業が参入したりするなどして、たちまちMVNOは活況を呈することになります。
ですが、格安スマホが市場を席巻してから約4年が経った現在、MVNOにかつての勢いが見られなくなっています。総務省の「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(平成30年度第4四半期(3月末))」によると、2019年3月末時点でMVNOの契約数は1312万に達しており、現在も伸びが続いているのは確かなのですが、その伸びが大きく落ち込んでいるのです。
そのことを示す例の1つが、MVNO大手となるIIJの個人向け通信サービス「IIJmio」の契約数です。同社の決算資料を見ると、2017年ごろまでは回線契約数の伸びが1万単位で伸びていたのですが、2018年以降はそれが大幅に鈍り、一時は純増数が四半期でわずか1,000にとどまるなど、伸び悩みが鮮明になっているのです。
なぜMVNOが伸び悩んだのかといえば、携帯電話大手の反撃を受けたからです。MVNOは低価格を武器に、通信料金が高いとされる携帯電話大手から顧客を奪って成長してきました。ですが、顧客を奪われる側の携帯電話大手が危機感を強め、低価格のサービスを大幅に強化したのです。
なかでもMVNOに大きなインパクトを与えたのが、いわゆる「サブブランド」の存在です。ソフトバンクの「ワイモバイル」ブランドや、KDDI傘下のUQコミュニケーションズが展開する「UQ mobile」がそれに当たります。携帯電話大手はMVNOに対抗するべく、サブブランドサービスの充実やプロモーションなどを大幅に強化。低価格を求めて他社に流出しようとする顧客を、自社グループに留める戦略に打って出たことで、独立系のMVNOに流れる顧客が減少したわけです。
一方で、MVNOに参入する事業者は増加の一途をたどっています。実際、先の総務省の資料によると、MVNOサービスの事業者数自体は2019年3月末時点ですでに1,000社を超えている状況なのです。携帯電話大手から流れる顧客が減少しているにもかかわらず、それを奪い合うライバルの増加が止まっていないことが、MVNO全体で苦境に陥った要因といえるでしょう。
MVNOが生き残るには独自性が必要
そうした状況を受け、MVNOの淘汰・再編もかなり進んでいるのですが、その軸となっているのは、実は自社グループに顧客をとどめるべく、仲間のMVNOを増やしたい携帯電話大手だったりします。実際、2016年にはKDDIがビッグローブを子会社化し、2018年にはLINEの子会社だった「LINEモバイル」が、ソフトバンクの子会社化となるにいたっています。
なかでも買収に積極的なのが、2019年10月に携帯電話会社として新規参入する予定の楽天モバイルです。楽天モバイルは2017年に、経営危機にあったプラスワン・マーケティングのMVNO事業を買収(同社は同年に経営破たん)。2019年7月には、DMM.comから「DMM mobile」などの事業譲渡を受けることを発表しており、携帯電話事業参入を前に、他社MVNOを買収して顧客拡大を推し進めているのです。
MVNOは、このまま携帯電話大手やその系列会社に顧客を奪われ、存在感を失ってしまうのでしょうか。そうならないためにも求められるのは、やはりMVNOならではの独自性をいかに打ち出すかに尽きるでしょう。
MVNOは携帯電話大手と比べ、企業体力が弱く、しかもネットワークを借りている立場であることからサービスの自由度が低いなど、弱点も多く正面を切って争うのには限界があります。であれば、やはり携帯電話大手ができない、やりたがらない部分のサービスを取り込んでいくというのが、MVNOの生き残る道となるのではないでしょうか。
その代表例として最近注目されているのが「eSIM」です。最新の「iPhone XS」「iPhone XR」には、通常の物理的なSIMに加え、eSIMと呼ばれる組み込み型のSIMが搭載されているのですが、eSIM向けのサービスはオンラインで完結し、解約が容易なことから、携帯電話大手はサービス提供に消極的です。
ですが、IIJは2019年7月18日より、そのeSIM向けデータ通信サービスのベータ版を提供。これを利用すれば、消費者は手持ちのiPhoneにIIJの回線を追加し、携帯電話大手の契約と電話番号は維持したまま、データ通信だけをeSIM側に登録したIIJの回線でこなすことにより、通信料を大幅に抑えるといった使い方ができるようになるのです。
-

IIJは、eSIM向けの通信サービス「データ通信専用SIM eSIMプラン(ベータ版)」の提供を2019年7月18日より開始。SIMを差し替える必要なく、iPhone XSなどでIIJのデータ通信回線を追加できる
こうした使い方は確かにニッチではありますが、そうしたニッチ市場に入り込める柔軟性とフットワークの軽さこそが、MVNOに求められている要素といえるのではないでしょうか。今後もMVNOにとって厳しい時期が続くと思われますが、一方で技術や環境も変化してきているだけに、いかにそうした部分で商機を見出すかが、今後MVNOには強く求められるといえそうです。