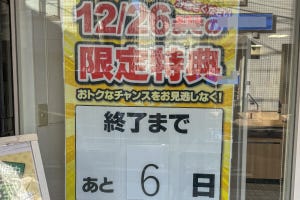2023年末に電気通信事業法が一部改正され、いわゆる「1円スマホ」撲滅に向けた新たな規制がなされたのですが、その直後からソフトバンクが「新トクするサポート(バリュー)」を開始し、再びスマートフォンの大幅値引きを実現しています。なぜ、法改正後も大幅値引きが可能になったのでしょうか?
1年後の端末返却を前提に激安価格を実現
2019年の電気通信事業法改正で大幅な規制がなされたスマートフォンの値引き販売ですが、その法の目をすり抜ける形で2021年ごろから「1円スマホ」と呼ばれる販売手法が復活。ですが、この仕組みは誰でもスマートフォンを安く買える仕組みであるため、“転売ヤー”による買い占めを招くなど社会問題化していました。
そこで、総務省が再びスマートフォンの値引き規制に向けた議論を進め、2023年11月22日に電気通信事業法施行規則等の一部改正を公表。おもな狙いは1円スマホの撲滅であることは間違いなく、法に触れることなくスマートフォンを大幅に値引くのに欠かせない、端末の元の価格を大幅に値引く「白ロム割」と呼ばれる割引手法にメスが入れられています。
それゆえ、この法改正が施行された2023年12月27日以降は、それ以前のようなスマートフォンの値引き手法を実施できなくなり、1円スマホは姿を消すと見られていました。ですが、そこに新たな手法を持ち込んで大幅値引きを継続したのがソフトバンクです。
それは、同社が2023年12月27日より提供している、新しい端末購入プログラム「新トクするサポート(バリュー)」です。従来の端末購入プログラム「新トクするサポート」は、スマートフォンを48回払いで購入し、25回目の支払い時に端末を返却すると残りの支払いが免除される仕組みでしたが、新トクするサポート(バリュー)は48回払いで購入し、13回目の支払い時に端末を返却すると残債が免除される仕組みとなっています。
それゆえ、新トクするサポート(バリュー)は、1年ごとにスマートフォンを買い替える人に適した端末購入プログラムといえます。ただ、実は同種のコンセプトの端末購入プログラムは、NTTドコモが2023年9月から「いつでもカエドキプログラム+」として提供しています。仕組みにいくつか違いはあるものの、ソフトバンク独自のものというわけではありません。
ですがソフトバンクは、この新トクするサポート(バリュー)をスマートフォンの大幅値引きに活用しているようです。例として、同社が販売しているシャオミの「Xiaomi 13T Pro」を挙げると、同機種の価格は111,600円ですが、新トクするサポート(バリュー)を適用して購入すると1~12回目の支払額は1,833円なのに対し、13~48回目の支払額は2,489円と割高に設定されています。
それゆえ、13回目に端末を返却すると割高な料金の支払いが免除されるため、支払総額は21,996円で済む計算となります。加えて、同社のオンラインショップで購入する場合は、番号ポータビリティによって適用される「オンラインショップ割」(21,984円引き)が加わるので、12カ月分の支払額は毎月1円、つまり実質12円でXiaomi 13T Proが利用できる計算となります。
ソフトバンクはいかにして法の隙を突いたのか?
とはいうものの、ソフトバンクは法改正前にも新トクするサポートを活用し、前半の支払額を安く設定することで、24カ月後にプログラムを適用すればスマートフォンを激安に利用できる仕組みを導入していました。では一体なぜ、法改正後はそれを1年にする必要があったのでしょうか?
その理由は、端末の買取価格にあります。端末購入プログラムは、ユーザーから返却された端末を中古市場に売却することで残りの支払いを不要にする仕組みなので、実質的にはユーザーから端末を買い取っているわけです。
その買取価格は、携帯各社が中古市場と買取時の年数を考慮して事前に決めているのですが、スマートフォンは年数が経過すれば価値が落ちるので、年数が経つほど買い取り額も安く設定しなければいけません。それゆえ、24カ月での返却を前提とした新トクするサポートでは買取価格が安くなってしまうので、大幅値引きすると法改正後の規制に抵触してしまう可能性があり、姿を消したのです。
ですが、買い取り時期が1年後に前倒しされれば、2年後と比べ買い取り額は大幅にアップします。実際、先の事例で言いますと、ソフトバンクはXiaomi 13T Proを1年後に69,300円で買い取るよう設定がなされているようです。
販売価格と買取価格の差額を計算すると、42,300円となります。法改正により、通信契約とセットで端末を購入した時の値引き額上限は、従来の一律22,000円から端末価格によって変化する仕組みへと変化しており、税込みで88,000円を超える端末は44,000円の値引きが可能。それゆえ、差額が44,000円以下であれば、こうした値引きを実施しても問題ないわけです。
それゆえ、この仕組みが好評を得るようであれば、同種の値引き施策は競合他社にも広まり、大幅値引きは今後も維持される可能性が高いでしょう。ただ、すべてのスマートフォンにこの仕組みを適用できるかというと、そこには難しさもあります。
先の事例で触れたように、この仕組みを用いて大幅値引きを実現するには、販売価格と買い取り価格の差額が法で定められた上限を超えないことが大前提となります。そしてもう1つ、携帯各社のビジネスを考慮するならば、値引いた後の価格が十分安く、ユーザーへのアピールにつながることも条件になってくるでしょう。
実際、ソフトバンクが新トクするサポート(バリュー)の対象としている4機種を見ると、法で定められた上限の値引き額を最大限適用可能であり、なおかつその中で値段が安い10万円台前半のものだけを対象とすることで、激安価格を実現してユーザーの関心を惹こうとしていることが分かります。
-

記事中の事例として説明したXiaomi 13T Proは11万円台で販売されていることから、法律上の上限である44,000円を最大限適用できるうえ、一連の仕組みの適用で大幅値引きによるお得感を打ち出しやすい
それゆえ、この条件から外れた機種、例えば端末価格が20万円以上するなど非常に高額な機種や、逆に1年後の買い取り価格が安く、値引き上限額も低いミドル・ローエンドモデルは対象になりにくいと考えられます。幅広い価格帯のスマートフォンを値引く柔軟性のあった、従来の1円スマホのようにはいかない、というのも正直なところではないでしょうか。
そうしたことから、新たな手法の登場で大幅値引きは継続するが、対象機種は限られるので大きくは広がりにくい、というのが筆者の見方です。ただ、総務省はスマートフォンの大幅値引きに非常に厳しい姿勢を撮り続けていることに変わりはなく、少しでも開いた隙間を全力で塞ぎにかかってくる可能性はあるといえます。