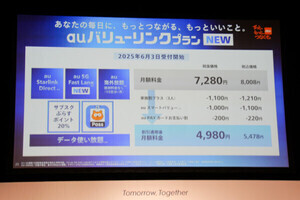メーカー各社から夏商戦に向けたスマートフォンが発表されたが、ミドルクラスより屋やや段が高い、8~10万円程度のミドルハイクラスに注力するメーカーが増えている。昨今話題のAIを活用した機能を提供するのに一定の性能が求められることがその背景にあるようだが、価格高騰が進む昨今にあって性能強化による端末の高価格化は消費者にも厳しい。ミドルクラス以下のスマートフォンにAI関連機能を提供するには何が必要だろうか。
「iPhone 16e」だけではないミドルハイスマホ増加の背景
夏の商戦期を控え、スマートフォンメーカー各社からの新製品発表が相次いでいる。最上位のフラッグシップモデルから、低価格のローエンドまでさまざまな種類のスマートフォンが発表されたが、中でも2025年、複数のメーカーが力を入れており数が増えているのがミドルハイクラスのスマートフォンだ。
ミドルハイクラスとは、最上位のハイエンドモデルより性能が低いが、ミドルクラスよりは性能が高いという位置付け。搭載するチップセットの性能でいえば、クアルコムであれば「Snapdragon 7」シリーズ、メディアテックであれば「Dimensity 8000」シリーズを搭載したモデルとなり、メーカーによっては「ハイエンド」と呼ぶケースもあるようだ。
だが2024年の同時期の新製品を振り返ると、ミドルハイクラスのモデルも増えていたとはいえ、どちらかといえば5~6万円のミドルクラスのスマートフォンに力を入れるメーカーが多かった。それから1年が経過し、メーカー側がより高額なミドルハイクラスに力を注ぐようになったのはなぜかといえば、理由の1つはアップルの「iPhone 16e」である。
2025年2月に発売されたiPhone 16eは価格が9万9800円と高額なことから日本の消費者の失望感を呼んだが、それでも圧倒的人気を誇るiPhoneの低価格モデルということもあって販売は好調なようだ。それゆえ他のメーカーもiPhone 16eに対抗するべく、同じ価格帯となるミドルハイクラスの強化を図ったものと考えられる。
だがもう1つ、より大きな影響を与えているのはAIの存在である。昨今大きな話題となっているAIだが、個人情報を多く扱うスマートフォンではプライバシーへの配慮が強く求められる。それゆえメーカー側もスマートフォンにAI関連の機能を導入する上で、可能な限りデバイス上でAI関連の処理をこなすことに重きを置く傾向が強い。
デバイス上でAI関連の処理をするにはチップセットやメモリに高い性能が求められるのだが、充分な性能を備えるハイエンドモデルは既に20万円を超えてしまうため一般消費者が手にするのは難しい。一方で、ミドルクラスの性能ではAI、とりわけ注目度の高い生成AI関連の処理で性能不足が否めない。
それゆえ現時点でAI関連機能に力を入れたスマートフォンを提供するには、ある程度高い性能を備えながら10万円を切るなど、比較的購入しやすいミドルハイクラスのスマートフォンが最もバランスが取れているとメーカー側が判断し、強化に動いているのではないだろうか。
-

FCNTは最新のAI機能を取り入れたハイエンドスマートフォンが、20万円近くにまで高騰していることから、ミドルハイクラスのチップセットを搭載し価格を10万円以下に抑えたarrows Alphaを提供したとしている
低価格モデルに有効なクラウドAI、だが課題も
ただこのことは、AIによってスマートフォンに求められる性能が高まったことで、スマートフォンの価格が高騰する可能性が出てきたことも示している。物価高で厳しい状況にある消費者にとって、メーカーがミドルクラス以下の低価格スマートフォンに対する注力を弱めてしまうことはデメリット以外の何物でもない。
それだけに期待されるのは、AIを活用した機能をミドルクラス、あるいはそれ以下のモデルでも満足して利用できるようにすることだが、現状ではスマートフォンの性能に依存しない、クラウド上のAIを活用することが、その有力な手段となる。実際、オッポは日本でAI技術を活用したサービス「OPPO AI」を提供するに当たり、ミドルクラス以下の機種でも利用することに重きを置き、デバイス上のAI処理は使わず、全てクラウド上でAI処理をするという選択をしている。
それゆえ2025年6月19日に発表されたオッポの新機種では、メディアテック製のミドルハイクラス向けとなる「Dimensity 8350」を搭載した「OPPO Reno14 5G」だけでなく、ミドルクラス向けの古いチップセット「Snapdragon 6 Gen 1」を搭載して価格を抑えた「OPPO Reno13 A」でもOPPO AIが利用できるという。両機種で提供される機能にやや違いはあるものの、クラウドの活用に重きを置くことで、幅広い機種でAI関連の機能を提供しようとしていることが分かる。
ただクラウドのAIを活用するとなると、プライバシー情報がスマートフォンの外に出てしまうことを懸念する声が出てくるのも確かだ。それだけにオッポ側もセキュリティには強く配慮しており、クラウドAIの処理にはグーグルと連携し、「Confidential Computing」という暗号化技術を用いたGoogle Cloudのプライベートクラウドを用いているという。
そしてもう1つ、クラウドで処理するAI関連機能を提供する上では、メーカー側がクラウドを維持契約し続ける必要があり、継続的にコストがかかることから無料で提供し続けられるのか? という点も課題になってくるだろう。継続利用のため、将来的にはユーザーから一定のコストを徴収するケースも出てくるかもしれないが、低価格に重きを置いたモデルでそれが受け入れられるかは未知数だ。
もちろん、ミドルクラスやローエンド向けのチップセットでAI関連の機能強化が進み、デバイス上でのAI関連処理が当たり前のものとなっていけば、そうしたことを気にする必要もなくなっていくだろう。だがスマートフォンでAI関連のニーズがまだ高いとは言えない現状では、そうした動きが急速に進むとも考えにくい。
-

クアルコムは2025年2月に、生成AI処理に対応したミドルクラス向け最新チップセット「Snapdragon 6 Gen 4」を発表しているが、こちらを搭載したスマートフォンが市場に投入されるには時間がかかる
それだけに、AI関連の機能を本格的に活用するならミドルハイクラス以上のスマートフォンが必要、という傾向はしばらく続くものと考えられる。メーカーの視点に立つならば、そのことがスマートフォンの購入単価を押し上げるメリットに働く一方、低価格モデルが手薄になることで販売数自体の落ち込みが懸念される所かもしれない。