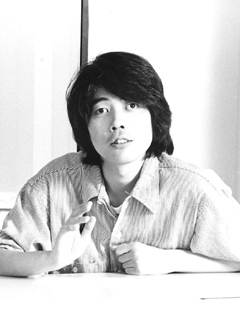日本マイクロソフトが政府、自治体分野における取り組みに関する記者説明会を開催、同社執行役員 常務 パブリックセクター事業本部長の佐藤亮太氏が説明した。
同社はこの日本という国が正しい未来にどう向かって行けばいいのかというテーマに対してその橋渡し、そのかけはしになりたいという。そのために、課題にあわせた最適なDXアプローチを提案し、組織文化の変革支援を行い、さらには信頼して使える最新のテクノロジーを提供する。
たとえば、行政機関向けにはモダナイズ化と内製化によってDXの基盤となる組織風土のトランスフォーメーションを促進、さらにはAIトランスフォーメーション(AX)を加速するなど、日本国内のあらゆるパブリックセクターに対してさまざまな支援を提供しているという。
日本の多くのITが外資企業に依存している
先日は、LINEヤフーのサービスが総務省から通信の秘密の保護及びサイバーセキュリティの確保の徹底に向けた措置として、2度目の行政指導を受けたことが話題になった。それに伴って、こうした公共サービスが外資出自のサービスに強く依存する状態でいいのかどうかなどといったことも議論された。
だが、今回の日本マイクロソフトの説明でもわかるのは、この日本という国のありとあらゆるITは、そのほとんどが、すでに外資企業に依存しているということだ。日本マイクロソフトだけでなく、GoogleやAppleなどによるインフラやプラットフォームが、日本の行政に依存しているのはご存じの通りだ。いや行政に限らずあらゆるパブリックセクターがだ。
さまざまな現場で使われるパソコンも、その多くは外資企業によるもので、日本企業によるものはわずかだ。それに日本企業が作ったことにしているパソコンであったとしても、内部の重要な部品のほとんどは他の国に依存している。
そもそも、部品の出自はもちろん、完成品のハードウェアの組み立ても海外だ。極端な話、今、日本が鎖国したら、この国のITを維持するのは難しい。そのくらいすべてが外資に依存しているのだ。
米国商務省産業安全保障局(BIS)は、特定の国に拠点を置く事業体を輸出管理規則(EAR)上のエンティティー・リスト(EL)に登録し、それらに米国製品(物品、ソフトウエア、技術)を輸出・再輸出・みなし輸出などを行う場合には、同保障局の事前許可が必要となるようにしているが、万が一、その対象に日本が含まれたとしたらどうなってしまうのだろうなどと、考えただけでもこわくなってくる。
結局のところ、この国日本のITが破綻しないように維持していくためには、どうしたって外資に頼るしかないわけで、考えようによってはものすごく弱い立場だともいえる。
複雑な手続きこそAIの領域だ
特に今はAIの導入についての議論が賑やかで、その結果として、今後、政府、自治体分野でも積極的にAIが活用されていくだろう。今、国や自治体などで何かをやろうとすると、気が遠くなるような手続きが必要で、まして、それを自治体をまたぐとか、複数の省庁の管轄下に入るといったことをするとなれば、その事務手続きだけの煩雑さは想像に難くない。
実は、そういう部分こそAIが役に立ってくれるにちがいないわけで、それを阻止するような動きは許されるべきではないのだが、それでもそのAIが外資依存では大丈夫なのかといった議論が起こるのは仕方なさそうだし、その方向性やロジックも気になる。
いずれにしても、今はとにかくこの国日本が敵国を作るようなことを最大限の努力で回避しながら、この国を守っていく必要がある。そうしながら、最善の道を探していくしかない。