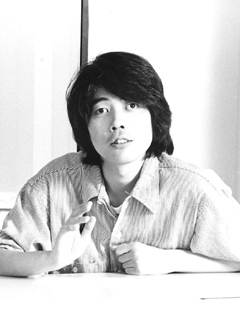ノートパソコンが一台あれば、オンライン会議はカンタンにできる。今どきのノートパソコンなら、普通はカメラとマイクが内蔵されているので、他に用意するものはない。もちろんスマホにもカメラ、マイクが内蔵されている。通信機なのだから当たり前だ。その簡単さから、コロナ禍においては、TeamsやZoomといった会議アプリが飲み会にまで使われた。
あれから1年たったのに、今、大阪など3府県に加え、東京、京都、沖縄の3都府県に「まん延防止等重点措置」が適用されるなど、コロナに関連した状況はあわただしい。こういう状況だから、せっかく新年度、新学期が始まり、気分を変えて新しい生活を始めようにも、あいかわらずの、オンラインに依存せざるを得ない暮らしが続きそうだ。
マイクを通じた自分の声、相手にどう聞こえてる?
オンライン会議では、ノートパソコンやスマホなどの機器を使って会議に挑むわけだが、自分の声がどのように相手に伝わっているかを気にしたことはあるだろうか。オンライン会議の肝は、なんといっても音声だ。音声は、コミュニケーションにおいてきわめて重要な役割を果たす。自分の顔がどんなにくっきりと美しい高画質で映っていたとしても、音声がクリアでなければ台無しだ。悪印象さえ与える影響がある。そうなっては元も子もない。
デンマークを本拠にする業務用ヘッドセット大手のJabraが「オンライン会議と相手に抱く印象に関する調査」をした結果、オンライン会議が急増する中で、2人にひとりがオンライン会議について不満があり、発言タイミングに困ったり、相手の声が聴きづらいことに不満を感じていたという(「Jabra(GN オーディオジャパン㈱)調べ」)。ビジネス商談などでオンライン会議をする場合には、その商談の成否が音声の品質に関わる可能性があるということだ。このことを、ささいな問題だと軽視していると、大きな問題につながるかもしれない。
オンライン会議前に音声チェックをしてみよう
TeamsやZoomには、自分の音声がどのように相手に届いているかをチェックするための機能が装備されている。いわゆるエコーテストと呼ばれるもので、仮想的な相手を設定し、自分が発声した音声をシステムが録音、それを再生してくれるというものだ。これをチェックすれば、相手に自分の声がどのように聞こえているかを確認することができる。
風呂場でしゃべったときのように部屋の壁に反響してエコーで聞きづらくなっていないか、また、声が小さすぎはしないか、マイクから離れすぎた感じはしないかどうかなど、また、オーディオ的な要素以外 に、そもそも自分のしゃべり方は相手に聞きやすいかどうかなどを確認してみよう。
在宅勤務などで、人と接する時間が少なくなっていると、しゃべることそのものの質が低下している可能性もある。口の筋肉や滑舌などが衰えていないだろうか。
スマホとパソコン両方で会議に参加する手も
自分のパソコンやスマホのマイクがどこにあるのかをチェックし、向きや距離などを変えてみるのもひとつの方法だ。もっともカメラとマイクを別々に位置調整できないことが多いので、その方法は難しい。どうしてもうまくいかないときには、それこそJabraなどのヘッドセットやスピーカーフォンを使って音声は別系統にするとか、Webカメラを別に導入するといった方法もある。
各種機器には便利のためにマイク、スピーカー、カメラが一体化されて内蔵されているが、これらは別々だって何の問題もない。位置の調整などで対応できない場合は、必要に応じて外付けすることで、今よりもずっとクリアな音質で自分の声を相手に届けることができるようになるかもしれない。
さらにはスマホとパソコンを併用するという手もある。両方で同時に会議に参加して、オーディオ/ビジュアルについてはスマホに委ね、画面共有などはパソコンでというのも効率的だ。ただし、Zoomのように二台目のデバイスで会議に参加すると、一台目が退室してしまうような仕様のシステムもある。アプリのアップデートは頻繁に行われているので、そのうち問題は解消されるとは思うが、これも試しておくといい。
トラフィック量が伸びなかった真相は……
インターネットプロバイダー大手のIIJ技術研究所のエンジニアが、コロナとインターネットトラフィックのトレンドを定期的に解析して解説している。先日、その最新状況が更新された。
-

IIJの固定ブロードバンドサービスにおける、毎月の平均トラフィック量推移(2017年1月から2021年3月まで、IIJの発表ページより)
2020年の今頃は、緊急事態宣言が出たとことで、人の移動が止まって在宅率が向上し、平日昼間のトラフィックが大きく増えたが、それはその時期だけの特異な現象で、その他の期間については従来の成長曲線にのって順調に延びたにすぎないという。トラフィックは年率40%で上昇したものの、それは想定内のトラフィック増であり、危惧するようなものではないということらしい。
これだけオンライン会議が増えているのに、インターネットトラフィックはそれほど爆発していない。IIJの分析によれば、インターネット接続におけるボトルネックの制約などで、本来の伸びが抑えられているという疑いもあるということだが、果たして真相はどうなのか。
オンライン会議が急増しても日本のインターネットはビクともしないと安心していいのか。やばいくらいに急増しないことには日本のデジタルトランスフォーメーションは進まないのだから、むしろ、そこに危機感を持つべきと考えるべきなのか。