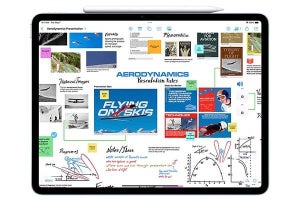Appleは2024年5月7日、ライブストリーミングで新型iPad ProとiPad Air、アクセサリーを発表しました。プレス向けには世界3拠点でイベントが開かれ、ニューヨーク、上海とともに、ロンドンのApple Batterseaに世界30カ国のプレスが集められ、ライブストリーミングの視聴と実機のタッチアンドトライが行われました。ロンドンでのイベント開催は、Appleの40年の歴史の中で初めてだったそうです。
-
ロンドンのApple Batterseaで開かれたAppleのイベントで、新型iPad ProとiPad Air、Apple Pencil Proなどの新製品がお披露目された。さらに、M4チップを新たに開発し、まずiPad Proに搭載することも発表した
今回話題が多かったのは、iPadの最上位機種であるiPad Pro。なかでも意外だったのが、iPad Proに搭載された最新のAppleシリコン「M4」チップの存在でした。
Appleは、Macを独自設計のチップに移行すると2020年に宣言。M1チップを発表して以来、まずMacに新チップを搭載してきました。その後、M1、M2チップをiPad ProやiPad Airに搭載し、チップそのものをMacとiPadで共有してきました。2024年2月にアメリカで発売されたVision ProにもM2チップが用いられています。
そうした経緯からすると、新しいM4チップがMacではなくまずiPad Proに搭載されたことは、これまでのパターンとは異なっています。その理由について探っていきましょう。
M4チップとは?
Macに先んじてiPad ProにM4チップを搭載した理由を3つ挙げるとしたら、以下の3点でしょう。なかでも、ディスプレイ改良のウェイトが高いと考えます。
- ディスプレイのため
- 消費電力低減のため
- AIの優位性拡大のため
M4チップは、4つ(もしくは3つ)の性能コアと6つの効率コアの10コア構成のCPUと、M3と同様にダイナミックキャッシングやレイトレーシングのハードウェアアクセラレーションに対応する10コアGPU、そして16コアのニューラルエンジンを搭載しています。
M2・M3との構成の違いはおもにCPUで、これまで性能・効率ともに4コア構成だったところ、M4では効率コアがさらに2コア増えました。
M3チップで採用された3nmプロセスの第2世代で製造されており、チップそのものの設計が見直されています。製造プロセスが変更されるため、チップ全体の設計の見直しに及んでいる可能性が高い、と見ることができます。
また、M3からM4への進化の重要なポイントの1つは、長らく100GB/sだったメモリ帯域幅が、120GB/sに向上している点です。ユニファイドメモリはメインメモリ、グラフィックスメモリを兼ねることから、メモリ帯域幅の拡大はパフォーマンスの向上に直結すると考えられます。
メディアエンジンについてもM3を踏襲しており、iPad向けとしては初めて、AV1のハードウェアデコードに対応。SafariなどのWebブラウザ上での高画質な動画再生を行う際の消費電力の軽減に寄与すると考えられます。加えて、8Kに対応するハードウェアビデオデコードが盛り込まれた点も新しい要素でした。
最高のiPadを作り出す
今回、AppleがiPad Proで目指したのは「最高のiPadを実現する」ことでした。
2018年に、現在のフラットなデザインにたどり着き、意匠の面でこれ以上の進化を予測することが難しくなりました。そのうえで、M4モデル以前のiPad Proが抱えていた問題点は2つありました。
1つ目は、11インチモデルのiPad ProがXDR(Extended Dynamic Range)ディスプレイを備えていなかったこと。12.9インチiPad Proには、液晶パネルとミニLEDバックライトを組み合わせて、高コントラストを実現したLiquid Retina XDRが搭載されていましたが、同じProを冠するにもかかわらず、11インチモデルでは省かれていました。
このディスプレイは、MacBook Pro 14インチ・16インチでも採用されており、同じテクニックはAppleのディスプレイの最高峰ともいえるPro Display XDRでも用いられていました。ただ、iPadに搭載するには厚みが増してしまい、11インチモデルに収めるにはスペースが足りなくなってしまうか、厚みが大幅に増してしまいます。消費電力も上がるため、それまでと同じバッテリー持続時間を確保しようとすると、より多くのバッテリーを備える必要があり、厚みの増加につながるからです。
もう1つの問題は、iPad Pro 12.9インチモデル(M2)が非常に重たい、ということでした。Proモデルの最上位機種ということで、高品位なディスプレイの搭載を優先した結果だったといえるでしょう。
Tandem OLEDによる問題解決
11インチモデルへのXDRディスプレイの搭載と、13インチモデルの軽量化を目指したAppleは、iPadへの有機ELディスプレイの搭載に白羽の矢を立てました。しかし、iPhoneのようにサイズの小さなスクリーンではないため、反応速度と安定した高輝度をもたらすには工夫が必要でした。
そこで、Appleは「Tandem OLED」と呼ばれる、2枚の有機ELパネルを重ねるテクニックを用いることになりました。Appleはこれを「Ultra Retina XDR」と名付けています。iPadへの搭載は初めてですが、有機ELパネルの使い方としては数年来の技術といえます。
Tandem OLEDは、複数のパネルで輝度を稼げるため、大きな画面でも安定した明るさを確保できます。また、応答速度向上にも寄与するといいます。有機ELパネルで起きやすいとされる焼き付きのリスクについても、表示を2つのパネルで分担することから軽減されるとしています。
なにより、ディスプレイパネル自体を薄型化できるため、iPad Pro 13インチモデルは1.3mmの薄型化を実現し、厚さはわずか5.1mmにまでなりました。実際に持ってみると、驚くべき薄さだと感じます。
加えて、課題となっていたiPad Pro 11インチへの搭載も可能となりました。11インチモデルのXDRディスプレイは初搭載となるため、その品質向上の幅は驚くべきもの。まるでステッカーを貼り付けたような発色の良さ、引き締まった黒は、iPad Proがまるで違うデバイスのように感じられました。
新ディスプレイのために、新チップを搭載
しかし、ここで別の問題が生じます。Tandem OLEDは、M3を含めた既存のAppleシリコンでは制御できないという問題です。
これまでも、ディスプレイを制御する「ディスプレイエンジン」はAppleシリコンに搭載されてきました。可変リフレッシュレート機能「ProMotion」を用いた省電力化や、焼き付き防止のアルゴリズムの実行を司ってきた存在です。
ところがTandem OLEDは、単純にいえば、常時2つのディスプレイを同期して同時に制御するようなもので、これが既存のディスプレイエンジンでは力不足になってしまったのです。そこでiPad Pro向けに用意したのがM4だった、というわけです。
iPad Pro 13インチの薄型化と、11インチへのXDRディスプレイ搭載を図るために、有機ELパネルを採用したい。しかし、そのためのディスプレイ制御がM3では実現できない。そこで、iPad ProはM3をスキップし、新チップであるM4を採用。これが、Macよりも先にiPad ProにM4チップを採用した背景なのです。
機械学習処理とリアルタイム処理
M4チップ搭載のiPad Proは、毎秒38兆回の機械学習処理を行うことができるニューラルエンジンも売りとなっています。
今後iPad上では、クリエイティブな作業をサポートするうえで、機械学習処理やAIを取り入れるアプリの増加が不可欠となっています。他社のPCやスマホでも、CPU、GPUとともに「NPU」(Neural Processing Unit)の搭載が話題になってきました。
Appleは、すでにA11 Bionicチップから、iPhoneやiPadにニューラルエンジンという機械学習コア(NPU)を搭載し、Appleシリコンに移行したMacにも搭載してきました。高度な機械学習処理を取り入れる裾野は十分に広がっており、開発者がこうした機能をアプリに取り入れる環境や、投資に見合うメリットが得られるマーケットが醸成されています。
今回、iPad版のLogic Proでは、自動的に伴奏を付けたり、演奏のパートをボーカルや楽器ごとに分離する機能をデモしていました。
興味深かったのは、Final Cut Proの新バージョン。被写体の切り抜きを、フィルターを適用するようにワンタッチでこなす処理にも驚かされました。しかし、それ以上に新しかった機能は、複数のiPhoneやiPadをFinal Cut Proから遠隔操作するライブマルチカメラ収録でした。
iPhoneやiPad側には、Final Cut Cameraという独立したアプリを導入し(Appleはアプリを「遅めの春」に配信するとしている)、複数のカメラの映像をiPad Proにリアルタイムで流し込み、カメラのズームなどをコントロールしながら収録する映像を選択できる機能です。
複数の高解像度映像をリアルタイムに同時に処理できるパワフルさもまた、M4チップのポテンシャルを活かした新しい映像制作方法といえるでしょう。
M4は今後どうなる?
Macへの搭載をスキップしてiPad Proに採用されたM4チップ。ディスプレイへの対応を強調している一方で、それ以外の処理性能面ではM3に対して大きなアドバンテージを持っていないようにも見受けられます。
そのうえで、M4が今後Macに採用される可能性はなきにしもあらずですが、2枚のOLEDディスプレイを同期させて表示させる、強力な機械学習コアを備えている、映像のリアルタイム処理などに長けている、といった特徴を見ていくと、MacよりもVision Proにふさわしいチップであるようにも思えます。
6月には毎年恒例のWWDC(世界開発者会議)が控えており、最新OS、そしてティム・クックCEOが各所で指摘する「生成AIのトレンドに対するAppleなりの答え」の行方も気になるところです。そうしたなかで、M4が果たす役割がどのように拡がるか、注目したいと思います。