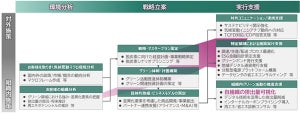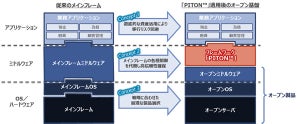多様性を包括するトータルデザインとは?
IT業界、建築業界のいずれにおいても多様性が求められているという点で意見が一致したところで、次は、「多様性を包括するトータルデザイン」というテーマで、トークが行われた。
隈氏は、「建築物は多様な人が中にいるだけでなく、外にも多様な人がいる。その人たちのことも考えながら、建築物をつくらなくてはいけない。同様に、環境問題も周りの人のことを考える必要があり、周りの人が広がっていくと地球にたどりつく。これからはそういう視点が必要。これまではそこまで考えずに、建築は行われていたが、今は変わってきた」と語った。
隈氏の話を受け、木場氏は「NTTデータは社会インフラの構築に貢献してきたと聞いており、暮らしや町全体のデザインを先導していらっしゃる点で建築と共通していると感じる。さらに、『社会に欠かせない仕組みを作っている』『世間に新しい価値を提供している』という点もITと建築は同じではないか。使命感はどう考えていらっしゃるか」と述べ、本間氏の発言を促した。
本間氏は、「金融分野や公共分野など、社会インフラを数多く構築してきたが、業界内がつながるインフラが中心だった。これから、社会課題を解決していくために、社会全体のデジタル化を推進していこうと考えている。そのためには、業界内のつながりを越え、地域や社会全体がつながることが大事になってくる。これにより、生活者が便利で、使っていて心地が良いサービスを提供できるようになる」と語った。
本間氏の話を受け、木場氏が「これからの建築やITの主役は使う側になるのだろうか」と隈氏に投げかけたところ、同氏は次のように答えた。
「今まですべてのビジネスが上から目線だったが、これからは逆にならなければいけない。建築や都市でも逆転が起こり始めていて、下から逆向きに作っていくことを考えていかなくてはいけない。コロナ禍でこの転換が加速すると思われる。これまでの設計図や都市計画図は鳥観図といって、上から眺めたものだった。しかし、地面の目線で都市を考えると、上から見たまっすぐな道が必ずしも良いわけではない。下から歩いているときはヒューマンな感じがするような目線に変わってきている」
本間氏が話した「協業」について、隈氏は「建築は人間が使うものであり、専門家だけで考えていてはいけない。幅の広い視点がないと、建築を作ってはいけなかった。これまでは、専門家が作ればよいモノができるという間違った思い込みがあった。これからは、人間の目線が必要ということで、あらゆる業界、業種との連携が必要になる。実際、そういう動きは起こっており、デジタルの専門家や緑の専門家とつながり始めている」と話した。
“新しいこれから”とは、どんな社会なのか?
最後に、基調講演のテーマである「新しいこれから」とはどのような社会か、また、それを実現するかについて、2人は意見を交わした。
本間氏は、「これからは、サステナブルな社会の実現が必要になる。すべての企業は、企業価値の向上だけでなく、社会課題の解決が求められる。こうしたことを前向きにとらえていくことが重要と考えている。そして、デジタルとグリーンは成長ドライバーになる。電子商取引など、デジタル面で日本は少し出遅れてしまったと言われているが、これから社会全体のデジタル化を推進していくチャンスといえる。世界がうらやむ仕組みを作って、世界に打って出るチャンスともいえる。そして、グリーンでも、世界がうらやむ仕組みを作ることが重要」と語った。
加えて、本間氏は酒田市との防災の取り組みを例に挙げ、地域社会の中で、住民や家族とつながり、自治体とつながり、タクシーなどの移動手段とつながることで、人々が支えあう仕組みにつながり、これは隈氏がいう「DXでヒューマンに戻る」ということに近いと述べた。
では、「DXでヒューマンに戻る」とはどういうことなのだろうか。隈氏は次のように説明してくれた。
「初めは、コンピュータは大きな箱にあるものだったが、小さくなってきて身近になってきたことで、人間にとって仲間としていいモノになってきた。コンピュータは人間を人間に戻してくれる道具ということが、これからの常識になっていくと思う」
また、隈氏は建築が環境に与えるインパクトについて、「建築をつくればつくるほど環境は悪くなると思われてきたが、建築を作ることで環境をよくする道も出てきた。こうしたことを踏まえて作ると、建築は環境にいいインパクトを与えるものになる。昔の日本建築は森と共に循環するシステムを作っていた。こうしたことを見直す空気が出てきている」と語った。
さらに、本間氏の「日本は出遅れていた」という言葉を受けて、隈氏は「日本がリードする時代が来るのではないかと思っている。日本は緑を大切にしてきたし、長屋などのコミュニティの知恵もあった。これからの社会が求めている環境やコミュニティに対し、日本人は資質を持っている。それを生かしていくと、IT業界でも建築業界でも、日本は世界のリーダーになれるのではないだろうか」と話した。
続けて、本間氏は「これからは、さまざまなステークホルダーがつながってくるが、つなげるは日本のお家芸。われわれもITとデジタルを活用してつながる社会、よりよい社会を作っていきたい」と述べた。
そして、隈氏は「江戸時代、建築と通りがつながった連続体を作っていた。しかし、20世紀に通りが自動車のためだけの場所になり、すべてぶつ切りにされてしまった。これは日本人に不便を強いることになった。そこで、これらをもう一度つなげなおしていけば、建築が人間につながった世界をつくることができると考えている。今、交通・モビリティが変わりつつあるので、緑が人間の空間に戻ってくると考えられる。そうなると、東京も今までとは違う柔らかさをもつようになるだろう」と語った。
コロナ禍で広がったリモートワークも都市が再生する機会になるという。だから、「新型コロナウイルスは悪いことばかりをもたらしているわけではなく、都市を再生させるチャンスを与えてくれた」と、隈氏は話した。
本間氏は「コロナ禍でオンラインとリアルの双方が発展してきた。オンラインでできることも確認できたし、リアルの素晴らしさもわかった。これからは、双方のよいところを組み合わせたベストミックスな社会を作っていくことが大事」と述べた。
新型コロナウイルスによって、新しい世界(ニューノーマル)が生まれたと言われているが、私たちはもう後戻りはできない。そうなると、今あるものを生かしながら、いかにしてよりよい社会を作っていくべきかということを考えていく必要があるだろう。